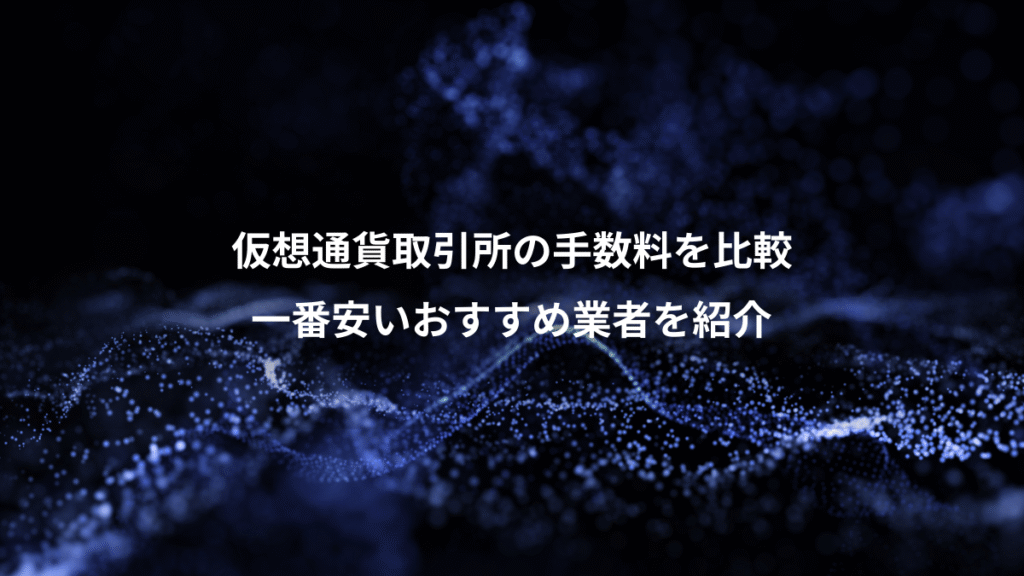仮想通貨(暗号資産)への投資を始める際、多くの人がまず注目するのはビットコインやイーサリアムといった銘柄の価格動向でしょう。しかし、長期的に安定した利益を目指す上で、価格変動と同じくらい、あるいはそれ以上に重要となるのが「手数料」の存在です。
仮想通貨取引では、売買のたびに発生する「取引手数料」をはじめ、日本円を入出金するための「入出金手数料」、他のウォレットへ仮想通貨を送る「送金手数料」など、さまざまな種類のコストが発生します。これらの手数料は一回一回は少額に見えるかもしれませんが、取引の回数が増えれば増えるほど、雪だるま式に膨らみ、せっかく得た利益を大きく削ってしまう「手数料負け」の原因になりかねません。
特に、短期的な売買を繰り返すトレードスタイルや、複数の取引所・ウォレット間で資金を移動させる場合、手数料の差は最終的なパフォーマンスに直接的な影響を及ぼします。したがって、仮想通貨取引所を選ぶ際には、どの手数料が、いつ、どれくらいかかるのかを正確に把握し、自身の投資スタイルに合った最もコストパフォーマンスの高い取引所を見極めることが、成功への第一歩と言えるでしょう。
この記事では、仮想通貨取引で発生するあらゆる手数料を網羅的に解説するとともに、国内の主要な仮想通貨取引所の手数料を徹底的に比較します。さらに、手数料を可能な限り安く抑えるための具体的なコツや、手数料以外の重要な取引所の選び方まで、初心者から経験者まで役立つ情報を詳しくご紹介します。
これから仮想通貨取引を始める方も、すでに取引を行っているがコストを見直したい方も、この記事を最後まで読むことで、手数料に関する知識を深め、より賢く、効率的に資産を運用するための最適なパートナーを見つけられるはずです。
目次
【一覧表】仮想通貨取引所の手数料を徹底比較
仮想通貨取引所を選ぶ上で、手数料は最も重要な比較ポイントの一つです。しかし、手数料には取引手数料、入出金手数料、送金手数料など複数の種類があり、各取引所が設定する料金体系も複雑なため、一目で全体像を把握するのは容易ではありません。
そこで、このセクションでは国内の主要な仮想通貨取引所の手数料を一覧表にまとめ、それぞれの特徴を比較しやすく整理しました。ご自身の取引スタイル(短期売買がメインか、長期保有か、頻繁に入出金するかなど)をイメージしながら、どの取引所が最もコストを抑えられるかを確認してみましょう。
| 取引所名 | 取引手数料(取引所/BTC) | 販売所の実質手数料(スプレッド) | 日本円入金手数料 | 日本円出金手数料 | 仮想通貨送金手数料 |
|---|---|---|---|---|---|
| GMOコイン | Maker: -0.01% Taker: 0.05% |
狭い傾向 | 無料 | 無料 | 無料 |
| DMM Bitcoin | 取扱なし (BitMatch手数料あり) |
やや広い傾向 | 無料 | 無料 | 無料 |
| Coincheck | 無料 | やや広い傾向 | 銀行振込:無料 コンビニ/クイック入金:770円〜 |
407円 | 通貨ごとに変動 (例: BTC 0.0005 BTC) |
| bitFlyer | 約定数量×0.01~0.15% | やや広い傾向 | 銀行振込:無料 クイック入金:330円 |
220円~770円 | 通貨ごとに変動 (例: BTC 0.0004 BTC) |
| SBI VCトレード | Maker: -0.01% Taker: 0.05% |
狭い傾向 | 無料 | 無料 | 無料 |
※上記の情報は2024年5月時点の各社公式サイトの情報に基づいています。手数料は変更される可能性があるため、最新の情報は必ず各取引所の公式サイトでご確認ください。
※販売所のスプレッドは市場の状況により常に変動します。上表の「狭い/広い」は一般的な傾向を示すものであり、絶対的な評価ではありません。
表から読み取れるポイントの解説
この比較表を見ると、各取引所の手数料戦略には明確な違いがあることがわかります。
まず、GMOコインとSBI VCトレードは、日本円の入出金手数料と仮想通貨の送金手数料が無料に設定されており、資金移動のコストを徹底的に抑えたいユーザーにとって非常に魅力的です。さらに、取引所形式では「Maker注文」を行うと手数料がマイナス(-0.01%)となり、取引をすればするほど手数料が受け取れるという大きなメリットがあります。これは、取引の流動性を高めるユーザーを優遇する仕組みであり、頻繁に取引を行うアクティブトレーダーにとって有利な条件です。
一方で、DMM Bitcoinも入出金・送金手数料が無料ですが、取引所形式のサービスは提供しておらず、現物取引は販売所形式(またはBitMatch注文)のみとなります。レバレッジ取引に強みを持つという特徴があり、トレードスタイルによって評価が分かれるでしょう。
CoincheckとbitFlyerは、国内でも特に知名度が高く、利用者数も多い取引所です。Coincheckは取引所形式の取引手数料が無料である点が強みですが、日本円の出金や仮想通貨の送金には所定の手数料がかかります。bitFlyerは取引量に応じた手数料体系を採用しており、取引が活発なユーザーほど手数料が安くなります。両社ともに初心者向けの使いやすいアプリや豊富な情報提供に定評がありますが、GMOコインやSBI VCトレードと比較すると、入出金や送金のコストはやや高めになる傾向があります。
結論として、どの取引所が「一番安い」かは、ユーザーの取引スタイルによって異なります。
- 取引所形式で頻繁に売買し、コストを最小限にしたい方:GMOコイン、SBI VCトレード
- レバレッジ取引をメインに考えている方:DMM Bitcoin、GMOコイン
- 初めて仮想通貨を購入し、まずは使いやすさを重視したい方:Coincheck、bitFlyer
- 日本円や仮想通貨を頻繁に移動させる予定がある方:GMOコイン、SBI VCトレード、DMM Bitcoin
このように、ご自身の投資計画と照らし合わせて、最もメリットの大きい取引所を選ぶことが重要です。次のセクションでは、この一覧表で挙げた取引所の中から、特に手数料の安さで定評のある5社をさらに詳しく掘り下げて解説していきます。
手数料が安い!おすすめ仮想通貨取引所5選
前章の比較表を踏まえ、ここでは特に手数料体系においてユーザーメリットが大きいと評価される国内の仮想通貨取引所5社を厳選し、それぞれの特徴、メリット・デメリット、そしてどのようなユーザーにおすすめなのかを詳しく解説します。各社の最新情報を基に、手数料だけでなく、取扱銘柄やサービス全体の魅力にも迫ります。
① GMOコイン
GMOコインは、東証プライム上場のGMOインターネットグループが運営する仮想通貨取引所です。金融サービスの運営ノウハウを活かした信頼性の高さと、業界トップクラスの手数料体系で、初心者から上級者まで幅広い層から支持を集めています。
手数料に関する最大の特徴は、その「安さ」を徹底的に追求している点です。まず、日本円の即時入金・出金手数料が無料であるため、取引で得た利益をコストを気にせず銀行口座に移動できます。さらに、仮想通貨の預入(入庫)・送付(出庫)手数料も無料です。これは、他の取引所や自身のウォレットへ仮想通貨を移動させる際に発生するネットワーク手数料をGMOコインが負担してくれることを意味し、DeFi(分散型金融)やNFTゲームなどを利用するユーザーにとっては非常に大きなメリットとなります。
取引手数料においても、ユーザーに有利な設定がされています。現物取引の「取引所」形式では、Maker(指値注文などで板に流動性を提供する側)になると-0.01%のマイナス手数料が適用されます。つまり、取引が成立すると、取引金額の0.01%を手数料として受け取れるのです。一方で、Taker(板にある注文を約定させる側)でも0.05%と、比較的低水準の手数料に抑えられています。
もちろん、初心者にも使いやすい「販売所」も提供していますが、こちらはスプレッド(売買価格差)が実質的な手数料となります。しかし、そのスプレッドも他の取引所と比較して狭い傾向にあると評判です。
手数料以外の魅力としては、国内最大級の取扱銘柄数を誇り、ビットコインやイーサリアムといった主要通貨はもちろん、将来性の高いアルトコインまで幅広く取引できます。また、「ステーキング」や「貸暗号資産」といった、保有しているだけで収益(インカムゲイン)を得られるサービスも充実しており、長期保有を考える投資家にも最適です。
【GMOコインがおすすめな人】
- 取引コストを1円でも安く抑えたいアクティブトレーダー
- 日本円や仮想通貨の入出金を頻繁に行う人
- Maker注文を活用して、手数料を受け取りながら取引したい人
- ステーキングや貸暗号資産で長期的な収益を狙いたい人
参照:GMOコイン公式サイト
② DMM Bitcoin
DMM Bitcoinは、DMM.comグループが展開する仮想通貨取引所で、特にレバレッジ取引に強みを持つことで知られています。初心者でも直感的に操作できるシンプルな取引ツールと、手厚いカスタマーサポートが特徴です。
手数料面での最大のメリットは、多くの手数料が無料である点です。日本円のクイック入金・出金手数料、そして仮想通貨の入庫・出庫(送金)手数料がすべて無料です。これにより、GMOコインと同様に、資金移動にかかるコストを心配する必要がありません。
ただし、取引形態には注意が必要です。DMM Bitcoinの現物取引は「販売所」形式のみとなっており、「取引所」形式は提供されていません。そのため、売買時にはスプレッドが発生します。このスプレッドが実質的な取引コストとなります。
その代わりとして、DMM Bitcoinは「BitMatch注文」という独自の注文方法を提供しています。これは、DMM Bitcoinが提示するミッド(仲値)価格を参考に、ユーザー同士の注文をマッチングさせる仕組みです。スプレッドが発生する販売所取引と比べて、取引コストを大幅に抑えられる可能性があります。ただし、一定時間内にマッチングが成立しなかった場合は、成行で約定するため、意図した価格と乖離する可能性も考慮する必要があります。
レバレッジ取引に関しては、国内最多クラスの銘柄数を取り扱っており、多様な戦略を立てることが可能です。建玉を翌日に持ち越した場合に発生するレバレッジ手数料(ロールオーバーポイント)は発生しますが、これはレバレッジ取引では一般的なコストです。
【DMM Bitcoinがおすすめな人】
- レバレッジ取引をメインに考えている人
- 入出金や送金の手数料を無料にしたい人
- 「BitMatch注文」を活用して取引コストを抑えたい人
- シンプルで分かりやすい取引ツールを求めている初心者
参照:DMM Bitcoin公式サイト
③ Coincheck(コインチェック)
Coincheck(コインチェック)は、アプリダウンロード数国内No.1を誇るなど、特に初心者からの人気が高い仮想通貨取引所です。マネックスグループ傘下という安心感と、洗練されたUI/UXのスマートフォンアプリが人気の理由です。
手数料体系を見ると、Coincheckは特定の条件下で強みを発揮します。まず、「取引所」形式における取引手数料は、Maker・Takerを問わず無料です。これは、スプレッドの広い販売所を避け、コストを抑えて取引したいユーザーにとって大きなメリットです。ただし、Coincheckの取引所で扱っている銘柄はビットコインをはじめとする一部の通貨に限られており、多くのアルトコインは販売所での取引となります。
日本円の入金については、銀行振込を利用すれば手数料は無料です(振込元の銀行手数料は自己負担)。しかし、コンビニ入金やクイック入金を利用する場合は、770円からの手数料が発生するため注意が必要です。また、日本円の出金には一律407円の手数料がかかります。
仮想通貨の送金手数料は、通貨ごとに設定されています。例えばビットコインの場合は0.0005 BTC(2024年5月時点)となっており、送金額に関わらず固定です。これは、GMOコインやDMM Bitcoinのように無料ではないため、頻繁に外部へ送金するユーザーはコストを意識する必要があります。
手数料以外のCoincheckの魅力は、取扱銘柄の豊富さと、仮想通貨取引以外のサービスの充実度にあります。「Coincheck IEO」では新規プロジェクトのトークンを先行販売し、過去には大きな価格上昇を記録した事例もあります。また、「Coincheck NFT」というNFTマーケットプレイスも運営しており、取引所の口座から直接NFTの売買が可能です。
【Coincheckがおすすめな人】
- 初めて仮想通貨を購入する初心者
- 使いやすいスマートフォンアプリで取引したい人
- ビットコインなどを「取引所」で手数料無料で取引したい人
- IEOやNFTなど、新しいサービスに興味がある人
参照:コインチェック公式サイト
④ bitFlyer(ビットフライヤー)
bitFlyer(ビットフライヤー)は、国内最大級のビットコイン取引量を誇る、日本で最も歴史のある仮想通貨取引所の一つです。長年の運営実績と強固なセキュリティ体制から、多くのユーザーに信頼されています。
bitFlyerの手数料体系は、ユーザーの取引スタイルによってコストが変動する特徴があります。まず、「取引所」形式の取引手数料は、直近30日間の取引量に応じて変動します。取引量が多ければ多いほど手数料率が下がる仕組みで、アクティブなトレーダーを優遇する設計です。最高でも0.15%程度であり、決して高すぎる水準ではありません。
一方で、初心者向けの「販売所」のスプレッドは、市場の流動性が高い分、比較的安定していますが、やはり取引所形式に比べるとコストは高くなります。
日本円の入出金手数料については、三井住友銀行からのクイック入金は330円、それ以外の銀行からは無料(振込手数料は自己負担)です。出金手数料は、三井住友銀行宛てであれば安く(220円~440円)、それ以外の銀行宛ては高め(550円~770円)に設定されています。
仮想通貨の送金手数料も通貨ごとに設定されており、例えばビットコインは0.0004 BTC(2024年5月時点)と、業界標準レベルです。
bitFlyerの最大の魅力は、その流動性の高さとプロ仕様の取引ツール「bitFlyer Lightning」の存在です。取引量が多いため、注文が成立しやすく、スリッページ(注文価格と約定価格の乖離)が起きにくいというメリットがあります。「bitFlyer Lightning」では、現物取引に加えて、FXや先物取引も可能で、多彩なインジケーターを使った高度なチャート分析が行えます。
【bitFlyerがおすすめな人】
- 流動性の高さを重視し、安定した取引環境を求める人
- プロ仕様のツールで本格的なチャート分析やトレードをしたい上級者
- ビットコインの取引量が国内トップクラスである安心感を重視する人
- Tポイントをビットコインに交換したいなど、独自のサービスを利用したい人
参照:bitFlyer公式サイト
⑤ SBI VCトレード
SBI VCトレードは、ネット証券最大手のSBIグループが運営する仮想通貨取引所です。SBIグループが培ってきた金融機関としての高いセキュリティ基準と信頼性を背景に、堅実なサービスを提供しています。
手数料体系は、GMOコインと非常に似ており、ユーザーにとって極めて有利な設定となっています。日本円の入出金手数料、そして仮想通貨の入出庫(送金)手数料がすべて無料です。これにより、日本円の入出金やDeFi利用のための仮想通貨の移動を、コストを一切気にせず行えます。
取引手数料も魅力的で、「取引所」形式ではMaker注文で-0.01%のマイナス手数料、Taker注文で0.05%と、業界最安水準を実現しています。コストを抑えたいトレーダーにとって、GMOコインと並ぶ最適な選択肢の一つと言えるでしょう。
SBI VCトレードの強みは、手数料の安さだけではありません。「ステーキング」サービスの対象銘柄が非常に豊富であることが挙げられます。ステーキングは、対象の仮想通貨を保有しているだけで、毎月報酬が自動的に得られる仕組みです。複雑な手続きは不要で、ただ口座に保有しておくだけで良いため、長期投資家や手間をかけずに収益を得たいユーザーから高い評価を得ています。
また、「貸暗号資産(レンディング)」サービスも提供しており、自分の保有する仮想通貨をSBI VCトレードに貸し出すことで、貸借料を受け取ることができます。このように、売買差益(キャピタルゲイン)だけでなく、資産運用による収益(インカムゲイン)を狙えるサービスが充実しているのが大きな特徴です。
【SBI VCトレードがおすすめな人】
- 金融大手グループの安心感と高いセキュリティを求める人
- ステーキングや貸暗号資産で安定したインカムゲインを得たい長期投資家
- GMOコイン同様、各種手数料を徹底的に抑えて取引したい人
- 少額からコツコツと積立投資を始めたい人
参照:SBI VCトレード公式サイト
仮想通貨取引所で発生する手数料の種類
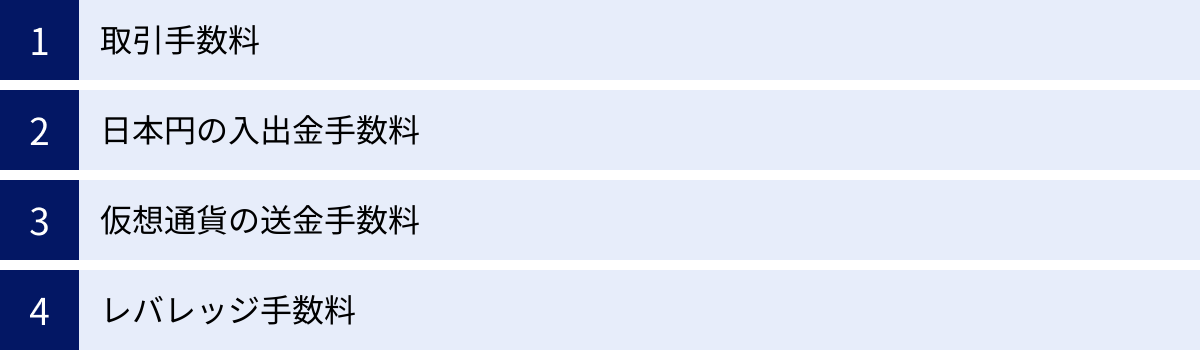
仮想通貨取引所のコストを正しく比較・評価するためには、まずどのような種類の手数料が存在するのかを正確に理解しておく必要があります。一言に「手数料」と言っても、その性質や発生するタイミングはさまざまです。ここでは、仮想通貨取引において一般的に発生する主要な手数料を4つのカテゴリーに分け、それぞれ詳しく解説します。
取引手数料
取引手数料は、仮想通貨を売買するたびに発生する最も基本的なコストです。この手数料は、取引所の利益の源泉となる重要な部分であり、その課金方式は「販売所」と「取引所」という2つの取引形式によって大きく異なります。
販売所の手数料(スプレッド)
「販売所」とは、ユーザーが仮想通貨取引所を相手に仮想通貨を売買する形式です。証券会社から株を買うようなイメージで、取引所が提示する価格で手軽に購入・売却できるため、特に初心者に好まれます。
販売所では、「取引手数料」という名目での請求は「無料」となっていることがほとんどです。しかし、実質的な手数料として「スプレッド」が存在します。スプレッドとは、同一の仮想通貨における「購入価格(Ask)」と「売却価格(Bid)」の差額のことです。
例えば、ある取引所がビットコイン(BTC)を「購入価格:705万円」「売却価格:700万円」で提示していたとします。この場合、差額の5万円がスプレッドです。ユーザーが705万円で1BTCを購入した直後に、すぐに売却しようとしても700万円でしか売れないため、その瞬間に5万円の損失が確定します。このスプレッドが、取引所の利益となり、ユーザーにとっては見えないコストとなるのです。
スプレッドの幅は、取引所や通貨の種類、さらには市場の流動性(取引の活発さ)や価格の急変時など、さまざまな要因で常に変動します。一般的に、流動性が低いアルトコインや、相場が荒れている時はスプレッドが広がる(大きくなる)傾向があります。販売所の手軽さは魅力ですが、このスプレッドという隠れたコストが取引の利益を圧迫する可能性があることを、十分に理解しておく必要があります。
取引所の手数料(Maker/Taker)
「取引所」とは、仮想通貨を買いたいユーザーと売りたいユーザーが直接マッチングして取引を行うプラットフォームです。株式市場の板取引と同じ仕組みで、ユーザーは「いくらで、どれくらいの量を売買したいか」という注文を出し、条件が合致すれば取引が成立します。
取引所形式では、スプレッドは存在せず(厳密には買値と売値の最良気配値の差である「気配値スプレッド」はありますが、販売所のスプレッドとは性質が異なります)、代わりに明確な「取引手数料」が課金されます。この手数料は、多くの場合「Maker(メイカー)手数料」と「Taker(テイカー)手数料」の2種類に分けられています。
- Maker(メイカー):取引板(オーダーブック)に新しい注文を出すことで、市場に流動性を提供するユーザーを指します。例えば、「現在の価格より少し安い価格で買いたい」という指値注文を出し、それがすぐに約定せずに板に残る場合、その注文者はMakerとなります。取引所は市場の活性化に貢献するMakerを優遇するため、手数料を安く設定したり、場合によってはマイナス手数料(手数料がもらえる)にしたりします。
- Taker(テイカー):取引板に既にある注文を約定させることで、市場から流動性を取り除く(Takeする)ユーザーを指します。例えば、「今すぐ買いたい」という成行注文や、板に並んでいる売り注文と同じ価格で買い注文を出す場合、その注文者はTakerとなります。一般的に、Taker手数料はMaker手数料よりも高く設定されます。
コストを抑えたいのであれば、スプレ-ッドの大きい販売所を避け、取引所でMaker注文を狙うのが最も賢い戦略と言えます。
日本円の入出金手数料
仮想通貨を購入するための元手となる日本円を取引所の口座に入金したり、取引で得た利益を自分の銀行口座に出金したりする際に発生するのが、日本円の入出金手数料です。
入金手数料
取引所の口座に日本円を入金する際に発生する手数料です。入金方法は主に以下の3つがあり、それぞれ手数料体系が異なります。
- 銀行振込:ユーザーが自身の銀行口座から、取引所が指定する口座へ直接振り込む方法です。取引所側が徴収する入金手数料は「無料」としている場合が多いですが、振込元の金融機関で発生する振込手数料はユーザー負担となります。
- クイック入金(インターネットバンキング入金):提携している金融機関のインターネットバンキングを利用して、24時間365日ほぼリアルタイムで入金できる便利な方法です。利便性が高い反面、取引所によっては330円程度の固定手数料がかかる場合があります。ただし、GMOコインやSBI VCトレードのように、このクイック入金手数料も無料としている取引所もあります。
- コンビニ入金:コンビニエンスストアの端末を操作して現金で入金する方法です。手軽ですが、一般的に手数料は高めに設定されています。
出金手数料
取引所の口座から、自分の銀行口座へ日本円を引き出す際に発生する手数料です。これは、多くの取引所で有料となっており、220円~770円程度の固定額が設定されているのが一般的です。出金額に関わらず一律の料金がかかるため、少額の出金を頻繁に行うとコストがかさみます。また、bitFlyerのように、出金先の金融機関によって手数料が異なる場合もあります。GMOコイン、SBI VCトレード、DMM Bitcoinなどは、この出金手数料も無料としており、大きな強みとなっています。
仮想通貨の送金手数料(入庫・出庫)
自分の取引所の口座から、他の取引所や個人のウォレット(MetaMaskなど)へ仮想通貨を移動させる際に発生する手数料です。一般的に、仮想通貨を受け取る側(入庫)は無料で、送る側(出庫)に手数料がかかります。
この手数料は、取引所の利益になるものではなく、その仮想通貨のブロックチェーンネットワークを維持しているマイナー(またはバリデーター)に支払われる「ネットワーク手数料(ガス代)」が原資となっています。ネットワークが混雑していると、この手数料は高騰する傾向があります。
各取引所は、このネットワーク手数料を考慮して、通貨ごとに固定の送金手数料を設定しています。例えば、「ビットコインの送金は1回あたり0.0004 BTC」といった形です。
重要なのは、GMOコインやSBI VCトレード、DMM Bitcoinのように、この送金手数料を「無料」としている取引所がある点です。これは、ユーザーが支払うべきネットワーク手数料を取引所側が肩代わりしてくれていることを意味します。NFTやDeFiを利用するために頻繁に仮想通貨を外部ウォレットに送金するユーザーにとっては、この手数料が無料であるかどうかは、取引所選びの非常に重要な判断基準となります。
レバレッジ手数料(建玉管理手数料)
レバレッジ取引とは、口座に預けた証拠金を担保にして、その数倍の金額の取引ができるハイリスク・ハイリターンな取引方法です。このレバレッジ取引において、購入または売却したポジション(建玉)を決済せずに翌日に持ち越した場合(日をまたいだ場合)に発生するのが「レバレッジ手数料」です。
「建玉管理手数料」や「ポジション手数料」、「スワップポイント(マイナスの場合)」など、取引所によって呼び方はさまざまですが、基本的には同じ性質のコストです。一般的に「建玉の評価額 × 0.04% / 日」のように、日割りで計算されます。
例えば、100万円分のビットコインの買いポジションをレバレッジで保有している場合、1日あたり400円(100万円 × 0.04%)のレバレッジ手数料が発生します。1ヶ月(30日)持ち続ければ、12,000円ものコストになります。この手数料は、ポジションを保有している限り毎日発生し続けるため、レバレッジ取引で長期的にポジションを保有する戦略は、手数料負担が非常に大きくなるということを覚えておく必要があります。
仮想通貨取引所の手数料を安く抑える4つのコツ
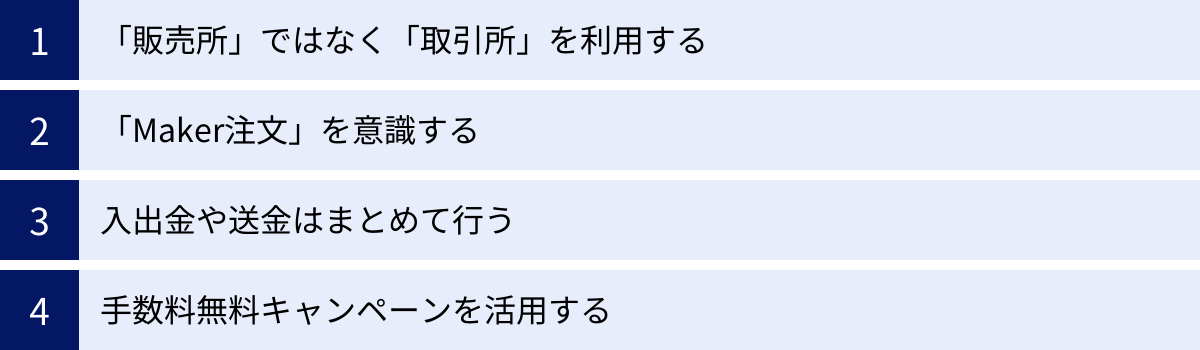
仮想通貨取引において、手数料は利益を最大化するための重要な管理項目です。取引に慣れてくると、わずかな手数料の差が長期的なリターンに大きな影響を与えることに気づくでしょう。ここでは、誰でも実践できる、仮想通貨取引所の手数料を安く抑えるための具体的な4つのコツを解説します。
① 「販売所」ではなく「取引所」を利用する
手数料を抑えるための最も基本的かつ効果的な方法は、「販売所」ではなく「取引所」で取引することです。
前述の通り、「販売所」は操作がシンプルで初心者にも分かりやすい反面、「スプレッド」という実質的な手数料が価格に含まれています。このスプレッドは、取引手数料が明示されている「取引所」形式に比べて、はるかに高額になることがほとんどです。
具体例で考えてみましょう。ある時点で、ビットコイン(BTC)の市場価格が700万円だったとします。
- 販売所の場合:購入価格が703万円、売却価格が697万円といったように、市場価格を挟んで広い価格差が設定されていることがあります。この場合のスプレッドは6万円です。
- 取引所の場合:Taker手数料が0.05%だとすると、700万円分のBTCを購入する際の手数料は3,500円(700万円 × 0.05%)です。
この例では、販売所を利用すると取引所に比べて56,500円も余分なコストがかかる計算になります。取引金額が大きくなれば、この差はさらに開きます。
最初は「取引所」の画面にある「板(オーダーブック)」を見て難しく感じるかもしれませんが、基本的な仕組みは単純です。買いたい人はできるだけ安く、売りたい人はできるだけ高く注文を並べているだけです。コストを意識するなら、多少の手間をかけてでも「取引所」の使い方をマスターすることが不可欠です。多くのアルトコインは販売所でしか扱っていない取引所もありますが、ビットコインやイーサリアムなど主要な通貨を取引する際は、必ず「取引所」形式が利用できないか確認する習慣をつけましょう。
② 「Maker注文」を意識する
「取引所」形式の利用に慣れてきたら、次の一歩として「Maker注文」を積極的に狙うことを意識してみましょう。
「取引所」の手数料には、市場に流動性を提供する「Maker」と、その流動性を利用する「Taker」で差が設けられていると解説しました。多くの場合、Maker手数料はTaker手数料よりも安く設定されており、GMOコインやSBI VCトレードのようにMaker手数料がマイナス(-0.01%など)になっている取引所も存在します。マイナス手数料は「リベート」とも呼ばれ、取引が成立すると、手数料を支払うどころか、逆に取引金額に応じた報酬を受け取れることを意味します。
Maker注文になるのは、主に「指値注文」で、かつその注文がすぐに約定せずに取引板に並んだ場合です。例えば、現在のBTC価格が700万円の時に、「699万円になったら買いたい」という指値注文を出せば、それは板に並び、Makerとして扱われる可能性が高くなります。
逆に、「いますぐ売買したい」という場合に使う「成行注文」や、板に既にある注文にぶつける形の指値注文は、Takerとして扱われます。
ただし、Maker注文には注意点もあります。それは、指定した価格に到達しなければ、いつまでも注文が約定しない可能性があることです。価格がどんどん上昇してしまい、結局買えなかったという「機会損失」のリスクが伴います。
したがって、「急いで売買する必要はないが、有利な価格で取引したい」という場面ではMaker注文を狙い、「価格の急騰・急落に対応してすぐに売買したい」という場面ではTaker注文(成行注文など)を利用するなど、状況に応じて注文方法を使い分けることが、賢いトレーダーの戦略です。
③ 入出金や送金はまとめて行う
取引手数料だけでなく、日本円の入出金手数料や仮想通貨の送金手数料も、積み重なると大きな負担になります。これらの手数料の多くは、取引金額の大小にかかわらず、「1回あたり〇〇円」や「1回あたり〇〇BTC」といった固定額で設定されています。
例えば、出金手数料が1回407円の取引所で考えてみましょう。
- 1万円を10回に分けて出金した場合:407円 × 10回 = 4,070円の手数料
- 10万円を1回で出金した場合:407円 × 1回 = 407円の手数料
同じ10万円を出金するにもかかわらず、こまめに行うだけで手数料は10倍にもなってしまいます。これは、仮想通貨の送金においても同様です。
したがって、これらの手数料を節約するための基本戦略は、「取引は計画的に行い、資金移動はできるだけまとめて一度に行う」ことです。必要な資金をあらかじめ計算し、ある程度まとまった金額になってから入出金や送金を行うように心がけましょう。
もちろん、GMOコインやSBI VCトレードのように、これらの手数料がすべて無料の取引所を利用すれば、この点を気にする必要はなくなります。ご自身の資金管理スタイルに合わせて、これらの手数料が無料の取引所を選ぶことも、非常に有効なコスト削減策です。
④ 手数料無料キャンペーンを活用する
多くの仮想通貨取引所は、新規顧客の獲得や取引の活性化を目的として、定期的にお得なキャンペーンを実施しています。これらのキャンペーンをうまく活用することも、手数料を抑えるための有効な手段です。
キャンペーンの内容は多岐にわたります。
- 口座開設キャンペーン:新規に口座を開設するだけで、現金やビットコインがプレゼントされる。
- 取引手数料無料キャンペーン:特定の期間中、取引手数料が無料になる。
- 入金キャンペーン:一定額以上を入金すると、ボーナスがもらえる。
- 特定の銘柄の取引キャンペーン:新しく上場した銘柄などの取引で、手数料が割引されたり、報酬がもらえたりする。
これらのキャンペーン情報は、各取引所の公式サイトや公式SNSで告知されます。複数の取引所の口座を開設しておき、それぞれのキャンペーン情報を常にチェックし、最も有利な条件で取引できる取引所をその都度使い分けるというのも一つの賢い方法です。
ただし、キャンペーンには「期間指定」や「対象者」、「最低取引量」などの条件が設定されていることがほとんどです。応募が必要な場合もあるため、必ず適用条件の詳細をよく読んでから利用するようにしましょう。少しの手間で大きなメリットを得られる可能性があるので、積極的に情報を収集し、活用することをおすすめします。
手数料以外も重要!仮想通貨取引所の選び方
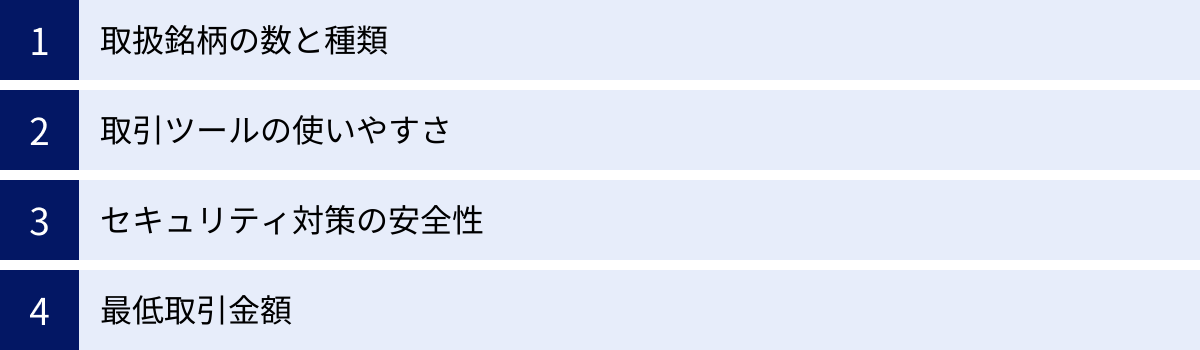
手数料の安さは仮想通貨取引所を選ぶ上で非常に重要な要素ですが、それだけで決めてしまうのは早計です。手数料が安くても、使い勝手が悪かったり、セキュリティに不安があったり、自分の投資したい銘柄がなかったりすれば、元も子もありません。ここでは、手数料という観点以外に、総合的に自分に合った取引所を見つけるための4つの重要なポイントを解説します。
取扱銘柄の数と種類
仮想通貨は、代表的なビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)以外にも、数千種類以上の「アルトコイン」が存在します。将来的に大きな成長が期待できるユニークなプロジェクトや、特定の機能に特化したコインなど、その種類は多岐にわたります。
取引所によって、取り扱っている仮想通貨の銘柄数や種類は大きく異なります。ビットコインなどの主要通貨しか扱っていない取引所もあれば、数十種類のアルトコインを揃えている取引所もあります。
取引所を選ぶ際には、まず自分が投資してみたいと考えている銘柄を取り扱っているかを確認することが第一歩です。もし、まだ特定の銘柄を決めていない場合でも、取扱銘柄が豊富な取引所を選んでおけば、将来的に投資の選択肢が広がります。新しいプロジェクトに関心を持ったときに、その銘柄をすぐに取引できる環境があるかどうかは、投資機会を逃さないために重要です。
また、単に数が多いだけでなく、「どのような種類の銘柄を扱っているか」もポイントです。例えば、
- Coincheckは、エンジンコイン(ENJ)など、NFTやメタバース関連の銘柄に強いことで知られています。
- GMOコインやSBI VCトレードは、ステーキング(保有しているだけで報酬が得られる仕組み)に対応した銘柄を多く取り扱っており、長期保有によるインカムゲインを狙う投資家に向いています。
- IEO(Initial Exchange Offering)に積極的な取引所もあります。IEOは、取引所が審査を行った上で先行販売する新しいトークンのことで、将来有望なプロジェクトに早期から参加できる可能性があります。
このように、各取引所の取扱銘柄のラインナップには特色があります。自分の投資戦略や興味の方向性と合致する銘柄を揃えている取引所を選ぶことが、満足度の高い取引につながります。
取引ツールの使いやすさ
実際に仮想通貨を売買する際に毎日触れることになるのが、PCのウェブブラウザやスマートフォンアプリなどの「取引ツール」です。この取引ツールの使いやすさ(UI/UX)は、取引の快適性や正確性、ひいては投資の成果にまで影響を与える重要な要素です。
取引ツールに求められる要件は、ユーザーのスキルレベルやトレードスタイルによって異なります。
- 初心者の方:まずは直感的で分かりやすいインターフェースが重要です。「購入」「売却」のボタンがどこにあるか一目で分かり、現在の資産状況や価格のチャートがシンプルに表示されるツールがおすすめです。Coincheckのアプリは、その洗練されたデザインと操作性の高さから、多くの初心者に支持されています。
- 中級〜上級者の方:より高度な分析やスピーディな取引が求められます。豊富なテクニカル指標(移動平均線、MACD、RSIなど)が利用できる高機能なチャートや、注文方法の多様さ(OCO注文、IFD注文など)、板情報の見やすさなどが重要になります。bitFlyerの「bitFlyer Lightning」やGMOコインの「WebTrader」は、プロのトレーダーも満足させる機能を備えています。
多くの取引所では、口座開設しなくても公式サイトで取引画面のデモを見ることができたり、アプリのレビューを確認したりできます。自分のレベルに合わない複雑すぎるツールはストレスの原因になりますし、逆に機能が少なすぎると分析の幅が狭まります。自分がストレスなく、かつ効率的に取引できるツールを提供しているかどうかは、手数料と同じくらい慎重に検討すべきポイントです。
セキュリティ対策の安全性
仮想通貨はデジタルデータであるため、常にハッキングや不正アクセスのリスクに晒されています。大切な資産を預ける取引所を選ぶ上で、セキュリティ対策の安全性は絶対に妥協できないポイントです。
取引所のセキュリティレベルを確認するには、以下のような点をチェックすると良いでしょう。
- 金融庁への登録:日本国内で仮想通貨交換業を営むには、金融庁への登録が法律で義務付けられています。登録済みの業者は、顧客資産の分別管理や厳格なセキュリティ体制が求められており、最低限の安全基準を満たしていると言えます。必ず登録業者であることを確認しましょう。
- コールドウォレットでの資産管理:コールドウォレットとは、インターネットから完全に切り離された状態で仮想通貨を保管する方法です。ハッキングのリスクを大幅に低減できるため、顧客から預かった資産の大部分をコールドウォレットで管理しているかどうかは非常に重要です。
- 二段階認証(2FA):ログイン時や出金時などに、ID・パスワードに加えて、スマートフォンアプリなどで生成される一時的な確認コードの入力を求める仕組みです。ユーザー自身が設定できる最も基本的で強力なセキュリティ対策であり、対応していることは必須条件です。
- マルチシグ:仮想通貨を送金する際に、複数の秘密鍵を必要とする技術です。一人の署名だけでは送金できないため、内部犯行や鍵の紛失・盗難に対する耐性が高まります。
過去には国内外で取引所のハッキング事件が何度も発生しています。SBI VCトレードやGMOコインのように、金融業界で実績のある企業グループが運営している取引所は、長年培ってきたセキュリティのノウハウを持っており、安心感が高いと言えるでしょう。各社の公式サイトには、通常「セキュリティ」に関するページが設けられているので、どのような対策を講じているかを事前にしっかりと確認することが大切です。
最低取引金額
「まずは少額から仮想通貨投資を試してみたい」と考えている初心者の方にとって、「いくらから取引を始められるか」という最低取引金額も重要な選択基準になります。
最低取引金額は、取引所や取引形式(販売所か取引所か)、そして通貨によって異なります。
- 数百円程度から始められる取引所:CoincheckやbitFlyer、SBI VCトレードなどは、多くの銘柄で「500円」や「0.0001 BTC」といった非常に少額からの購入に対応しています。お小遣い程度の金額から気軽に始められるため、初心者にとってのハードルは非常に低いと言えます。
- 数千円以上の資金が必要な場合も:取引所によっては、最低取引単位がやや高めに設定されていることもあります。
特に「積立投資」を考えている場合は、毎月無理なく続けられる金額で設定できるかどうかが重要です。多くの取引所が月々1,000円程度から積立サービスを提供しています。
自分の投資予算を考慮し、無理のない範囲でスタートできる取引所を選ぶことで、精神的な負担なく仮想通貨投資の第一歩を踏み出すことができます。
仮想通貨の手数料に関するよくある質問
ここまで仮想通貨の手数料について詳しく解説してきましたが、まだ細かい疑問点が残っている方もいるかもしれません。このセクションでは、手数料に関して特に多く寄せられる質問にQ&A形式で分かりやすくお答えします。
手数料が完全に無料の取引所はありますか?
結論から言うと、取引に関わるすべてのコストが完全に無料になる仮想通貨取引所は存在しません。
GMOコインやSBI VCトレードのように、日本円の入出金手数料や仮想通貨の送金手数料を無料にしている取引所はあります。しかし、これらの取引所もビジネスとして運営されているため、どこかで利益を上げる必要があります。その主な収益源が、「販売所」で発生するスプレッド(売買価格差)や、「取引所」でTaker(テイカー)が支払う取引手数料です。
たとえ取引手数料が「無料」と謳われていても、それは特定の条件下(例:Maker注文の場合、キャンペーン期間中など)に限られることがほとんどです。また、見えにくいコストであるスプレッドは必ず存在します。
したがって、「手数料無料」という言葉だけに惑わされず、どの手数料が無料で、どの手数料がかかるのか、そしてスプレッドを含めた実質的なトータルコストはいくらになるのかを総合的に判断することが重要です。
「手数料」と「スプレッド」の違いは何ですか?
「手数料」と「スプレッド」は、どちらもユーザーが負担するコストですが、その性質は異なります。
- 手数料:「取引手数料」「出金手数料」のように、名目が明確に定義され、料金が「取引額の〇%」や「1回あたり〇〇円」といった形で明示されているコストです。主に「取引所」形式での売買や、入出金・送金といった操作に対して発生します。これは、ユーザーが取引所に対して支払うサービス利用料という位置づけです。
- スプレッド:「販売所」形式における、同一通貨の「購入価格」と「売却価格」の差額を指します。これは明確に「手数料」として請求されるものではありませんが、購入した瞬間に価格差分の含み損を抱えることになるため、ユーザーが実質的に負担している隠れたコストと言えます。スプレッドは取引所の利益となります。
簡単に言えば、手数料は「明示されたコスト」、スプレッドは「価格差に織り込まれた実質的なコスト」と理解すると良いでしょう。特に初心者が利用しがちな販売所では、このスプレッドが利益を大きく左右するため、注意が必要です。
「Taker」と「Maker」とは何ですか?
「Taker(テイカー)」と「Maker(メイカー)」は、「取引所」形式での注文者を区別するための用語で、市場の流動性に対する貢献度によって分けられます。
- Maker(メイカー):取引板に新しい注文を「作る(Make)」人のことです。例えば、まだ誰も注文を出していない価格で指値注文を出すと、その注文は板に並び、取引の選択肢を増やします。このように、市場に流動性を提供する(Provide)役割を担うため、取引所から優遇され、手数料が安く設定されたり、マイナス手数料(報酬)が支払われたりします。
- Taker(テイカー):取引板に既にある注文を「取る(Take)」人のことです。例えば、板に並んでいる売り注文に対して買い注文を出して即座に約定させたり、成行注文を出したりする場合がこれにあたります。市場から流動性を奪う(Remove)役割と見なされるため、一般的にMakerよりも高い手数料が課されます。
コストを抑えたいのであれば、すぐに約定しなくてもよい注文は指値で行い、Makerになることを意識するのが有効な戦略です。
手数料負けしないためにはどうすれば良いですか?
「手数料負け」とは、仮想通貨の価格が上昇して利益が出たとしても、取引手数料やその他のコストを差し引くと、結果的に元本割れしてしまう状態を指します。これを防ぐためには、コスト管理の意識を徹底することが不可欠です。
以下の5つのポイントを実践することをおすすめします。
- 「販売所」ではなく「取引所」を利用する:最も基本的で効果的な対策です。スプレッドという高額なコストを避け、手数料の安い取引所形式を主戦場にしましょう。
- 短期的な頻繁な売買を避ける:特に初心者のうちは、デイトレードやスキャルピングのような短期売買は避けるのが賢明です。取引回数が増えれば増えるほど、手数料はかさんでいきます。
- 入出金や送金はまとめて行う:固定額でかかる手数料を節約するため、資金移動は計画的に、ある程度まとまった金額で行いましょう。
- レバレッジ取引の長期保有に注意する:レバレッジ手数料(建玉管理手数料)は毎日発生します。ポジションを長期間持ち越すと、気づかぬうちに大きなコストになっていることがあるため注意が必要です。
- 自分の取引スタイルに合った手数料の安い取引所を選ぶ:本記事で紹介したように、取引所ごとに手数料体系は異なります。頻繁に取引するなら取引手数料が安いところ、頻繁に資金を動かすなら入出金・送金手数料が無料のところを選ぶなど、最適な取引所を見極めましょう。
海外の仮想通貨取引所は手数料が安いですか?
一般的に、Binance(バイナンス)などに代表される海外の仮想通貨取引所は、国内の取引所と比較して取引手数料が安い傾向にあります。また、取扱銘柄数が数百~数千種類と非常に豊富で、国内では取引できないアルトコインが購入できるという大きなメリットもあります。
しかし、これらのメリットの裏には、初心者が看過できない重大なリスクが存在します。
- 金融庁の認可を受けていない:海外取引所は日本の暗号資産交換業の登録を受けていません。そのため、日本の法律による利用者保護の対象外となります。万が一、取引所が破綻したり、ハッキング被害に遭って資産を失ったりしても、日本の規制当局からの救済は期待できません。
- 日本語サポートの欠如:公式サイトやサポートが日本語に完全対応していない場合が多く、トラブルが発生した際に円滑なコミュニケーションが取れないリスクがあります。
- 税金計算の複雑化:海外取引所での利益も、もちろん日本の税法に基づいて確定申告が必要です。しかし、取引履歴の取得方法が複雑であったり、日本円での損益計算が煩雑になったりする可能性があります。
- 法規制のリスク:過去には、日本の金融庁からの警告を受けて、一部の海外取引所が日本人向けのサービスを停止した事例もあります。突然、取引や出金ができなくなるリスクもゼロではありません。
これらのリスクを考慮すると、特に仮想通貨取引に慣れていない初心者の方は、まず金融庁に登録されている国内の取引所で安全に取引経験を積むことを強く推奨します。手数料の安さというメリット以上に、資産を守ることの重要性を優先すべきです。