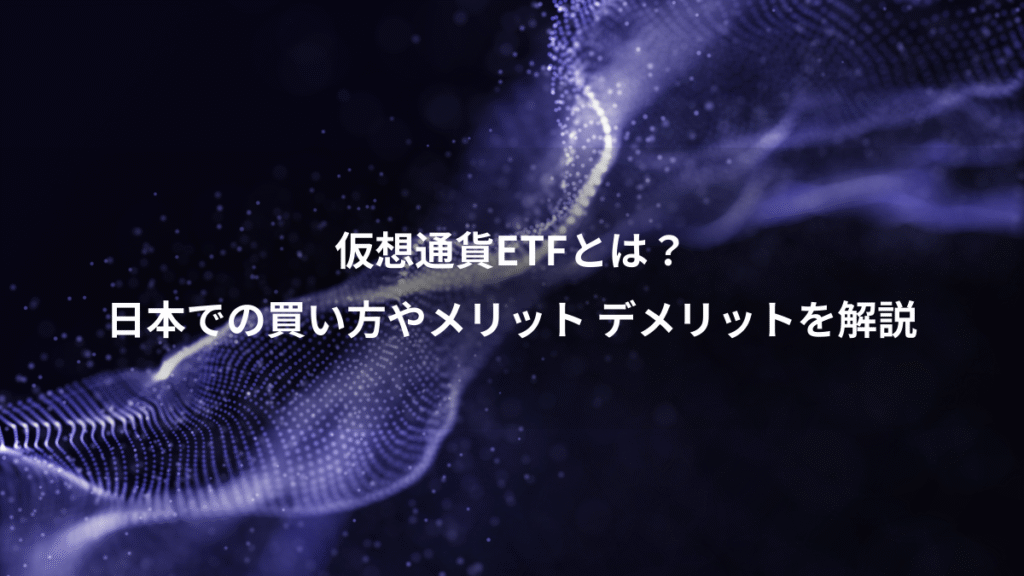近年、大きな注目を集めている仮想通貨(暗号資産)。その新しい投資の形として「仮想通貨ETF」が登場し、特に2024年1月に米国でビットコイン現物ETFが承認されたことは、金融市場に大きなインパクトを与えました。
「仮想通貨に興味はあるけれど、取引所の口座開設やセキュリティ管理が不安」「株式投資と同じように手軽に始めたい」と考えている方にとって、仮想通貨ETFは有力な選択肢となるかもしれません。
この記事では、仮想通貨ETFの基本的な仕組みから、他の金融商品との違い、米国での承認がもたらした影響、具体的な投資のメリット・デメリット、そして日本国内から投資する方法まで、網羅的に解説します。今後の将来性やよくある質問にも触れながら、仮想通貨ETFの全体像を深く理解できるよう、丁寧に掘り下げていきます。
目次
仮想通貨ETFとは?

仮想通貨ETFという言葉を理解するためには、まず「ETF」そのものがどのような金融商品なのかを知る必要があります。ここでは、ETFの基本から、それを仮想通貨に応用した仮想通貨ETFの仕組みまでを分かりやすく解説します。
ETF(上場投資信託)とは
ETFとは、「Exchange Traded Fund」の略称で、日本語では「上場投資信託」と訳されます。その名の通り、特定の指数(インデックス)に連動する成果を目指して運用される投資信託でありながら、証券取引所に上場しているため、株式のようにリアルタイムで売買できるという特徴を持っています。
もう少し具体的に見ていきましょう。
投資信託とは、多くの投資家から集めた資金を一つにまとめ、運用の専門家(ファンドマネージャー)が株式や債券、不動産など複数の資産に分散投資する金融商品です。個人では難しい多様な資産への分散投資を、少額から手軽に始められるのが魅力です。
一方、ETFはこの投資信託の性質を持ちながら、株式の利便性を兼ね備えています。
例えば、日本の代表的な株価指数である「日経平均株価」や「TOPIX(東証株価指数)」に連動するETFを考えてみましょう。これらのETFを1単位購入するだけで、指数を構成する多数の銘柄(日経平均株価なら225銘柄)に分散投資したのと同じ効果が得られます。個別に225社の株式を買い揃えるのは莫大な資金と手間がかかりますが、ETFならそれが一口数千円から数万円程度で実現可能です。
さらに、ETFは証券取引所に上場しているため、取引所の開いている時間内であれば、株式と同じようにリアルタイムの市場価格で、指値注文や成行注文といった方法で自由に売買できます。これは、1日に1回算出される基準価額でしか取引できない多くの非上場投資信託との大きな違いです。
このように、ETFは「投資信託の手軽さ・分散効果」と「株式のリアルタイム性・透明性」を併せ持つ、ハイブリッドな金融商品として、世界中の投資家に広く活用されています。
仮想通貨ETFは仮想通貨の価格に連動する投資信託
上記のETFの仕組みを、仮想通貨の世界に応用したものが「仮想通貨ETF」です。つまり、ビットコインやイーサリアムといった特定の仮想通貨、あるいは複数の仮想通貨で構成される指数の価格に連動するように設計された上場投資信託のことを指します。
投資家は、仮想通貨ETFを購入することで、仮想通貨そのものを直接保有することなく、その値上がり益を狙うことができます。仮想通貨の現物を購入する場合、自身で仮想通貨取引所に口座を開設し、ウォレットを用意して秘密鍵を厳重に管理する必要があります。ハッキングや盗難、紛失のリスクは常に付きまといます。
しかし、仮想通貨ETFの場合、ETFを発行・運用する資産運用会社が、投資家から集めた資金で実際に仮想通貨を購入し、専門のカストディアン(保管業者)を通じて安全に管理します。投資家が保有するのは、その仮想通貨の所有権を裏付けとした「受益証券」であり、仮想通貨の現物管理に伴う複雑さやセキュリティリスクから解放されます。
言い換えれば、投資家は信頼できる金融機関を通じて、間接的に仮想通貨市場へ参加できるのです。この手軽さと安全性の高さが、これまで仮想通貨投資に踏み出せなかった層、特に規制やコンプライアンスを重視する機関投資家や、セキュリティに不安を感じる個人投資家にとって大きな魅力となっています。
仮想通貨ETFには、裏付け資産として現物を保有する「現物ETF」と、価格に連動する先物契約に投資する「先物ETF」の2種類が存在します。特に、長らく承認されてこなかった「現物ETF」が米国で承認されたことは、仮想通貨が新たなアセットクラスとして認められた歴史的な出来事として、大きな意味を持っています。この違いや影響については、後の章で詳しく解説します。
仮想通貨ETFと他の金融商品との違い
仮想通貨ETFへの投資を検討する上で、既存の「仮想通貨の現物取引」や「一般的な投資信託」と何が違うのかを正確に理解しておくことが重要です。それぞれの特徴を比較し、メリット・デメリットを把握することで、自身の投資スタイルに合った選択ができます。
仮想通貨の現物取引との違い
仮想通貨投資と聞いて多くの人が真っ先に思い浮かべるのが、仮想通貨取引所でビットコインなどを直接売買する「現物取引」でしょう。仮想通貨ETFは、この現物取引とはいくつかの点で大きく異なります。
| 比較項目 | 仮想通貨ETF | 仮想通貨の現物取引 |
|---|---|---|
| 所有権 | ETFの受益証券を所有(間接保有) | 仮想通貨そのものを所有(直接保有) |
| 管理・保管 | 運用会社が専門業者に委託(自己管理不要) | 自己管理(ウォレット、秘密鍵の管理が必要) |
| セキュリティ | ハッキングや秘密鍵紛失のリスクが低い | ハッキングや秘密鍵紛失のリスクがある |
| 取引場所 | 証券取引所 | 仮想通貨取引所 |
| 取引口座 | 証券会社の口座 | 仮想通貨取引所の口座 |
| 取引時間 | 証券取引所の取引時間内(例:平日日中) | 24時間365日 |
| 税制(日本) | 申告分離課税(外国株として購入の場合) | 雑所得(総合課税) |
| レバレッジ | 基本的になし(一部例外あり) | 可能(国内取引所では最大2倍) |
最大の違いは、資産の所有形態とそれに伴う管理責任です。現物取引では、購入した仮想通貨は自分自身の資産となり、その保管責任もすべて自分にあります。秘密鍵を紛失すれば資産は永久に失われ、取引所や個人のウォレットがハッキングされれば資産が盗まれるリスクがあります。
一方、仮想通貨ETFでは、投資家は仮想通貨の現物を直接保有しません。実際の仮想通貨はETFの運用会社が購入し、高度なセキュリティ対策を施した専門の保管業者(カストディアン)が管理します。そのため、投資家個人がハッキングや秘密鍵の紛失といったリスクに直接晒されることはありません。この安全性の高さが、ETFの最も大きな利点の一つです。
また、取引の場も異なります。現物取引が仮想通貨取引所で行われるのに対し、ETFは証券取引所で売買されます。したがって、普段から株式投資をしている人であれば、使い慣れた証券会社の口座で、他の上場株式と同じ感覚で取引を始められます。新たに仮想通貨取引所の口座を開設し、操作方法を覚える手間が省けるのは大きなメリットです。
取引時間にも違いがあります。仮想通貨の現物市場は24時間365日動いていますが、ETFは上場している証券取引所が開いている時間帯しか取引できません。市場が閉まっている間に大きな価格変動が起きても即座に対応できない点は、ETFのデメリットと言えるでしょう。
さらに、日本国内における税制上の扱いも重要なポイントです。仮想通貨の現物取引で得た利益は「雑所得」として扱われ、給与所得など他の所得と合算して税率が決まる「総合課税」の対象となります。税率は最大で55%(所得税45%+住民税10%)に達する可能性があります。一方、米国の仮想通貨ETFを日本の証券会社を通じて購入した場合、その利益は「申告分離課税」の対象となり、所得額にかかわらず一律20.315%(所得税15.315%+住民税5%)の税率が適用されます。これは、特に所得が高い投資家にとって大きな税制上のメリットとなり得ます。
一般的な投資信託との違い
仮想通貨ETFは「上場している投資信託」ですが、多くの人が「投資信託」としてイメージする非上場の投資信託とは、取引方法や価格の決まり方などに違いがあります。
| 比較項目 | 仮想通貨ETF(上場投資信託) | 一般的な投資信託(非上場) |
|---|---|---|
| 上場の有無 | 上場している | 上場していない |
| 取引方法 | 株式と同様にリアルタイムで売買 | 1日1回の基準価額で取引 |
| 注文方法 | 成行注文、指値注文が可能 | 金額指定・口数指定のみ(価格は指定不可) |
| 価格の透明性 | 取引時間中は価格が常に変動し、透明性が高い | 1日1回算出される基準価額のみ |
| 主な手数料 | 売買委託手数料、信託報酬(経費率) | 購入時手数料、信託報酬、信託財産留保額 |
| コスト | 一般的に信託報酬が低い傾向にある | ETFに比べると信託報酬が高い傾向にある |
最も大きな違いは、取引のリアルタイム性です。ETFは証券取引所で株式と同じように扱われるため、市場が開いている間は常に価格が変動しており、投資家は「この値段で買いたい/売りたい」という指値注文を出すことができます。相場の動きを見ながら、自分の狙ったタイミングで売買できるのが強みです。
それに対して、一般的な非上場の投資信託は、1日に1回だけ算出される「基準価額」という値段で取引されます。注文を出した時点ではいくらで約定するかわからず、その日の取引終了後に発表される基準価額が適用されます。そのため、日中の価格変動に対応した機動的な売買はできません。
手数料の体系も異なります。ETFは株式と同様に、売買時に証券会社へ支払う「売買委託手数料」と、保有期間中に継続的にかかる「信託報酬(経費率)」が主なコストです。一方、非上場の投資信託は、購入時に「購入時手数料」、保有期間中に「信託報酬」、解約時に「信託財産留保額」がかかる場合があります(近年は購入時手数料が無料のノーロード投信も増えています)。一般的に、ETFは非上場の投資信託に比べて信託報酬が低く設定される傾向があり、長期保有におけるコストを抑えやすいというメリットがあります。
このように、仮想通貨ETFは、仮想通貨投資のハードルを下げつつ、伝統的な金融商品の利便性と安全性を兼ね備えた、新しい選択肢と言えるでしょう。
ビットコイン現物ETFが米国で承認!その影響とは
2024年1月10日(米国時間)、米国証券取引委員会(SEC)が11本のビットコイン現物ETFの上場申請を承認したことは、仮想通貨の歴史における画期的な出来事でした。この承認がなぜこれほど重要視されるのか、その背景と市場に与えた影響を深く掘り下げていきます。
ビットコイン現物ETF承認までの道のり
ビットコイン現物ETFの承認は、決して平坦な道のりではありませんでした。最初の申請は、遡ること2013年にウィンクルボス兄弟によって行われましたが、SECによって却下されました。以来、10年以上にわたり、数多くの資産運用会社が申請と却下を繰り返してきました。
SECが一貫して承認を拒否してきた主な理由は、以下の3点に集約されます。
- 市場操作への懸念: ビットコイン市場は規制が未整備で、価格が不正に操作されるリスク(相場操縦)が高い。
- 投資家保護の欠如: ハッキングや詐欺が横行しており、投資家の資産を保護する仕組みが不十分である。
- カストディ(保管)の問題: 仮想通貨を安全に保管する体制が確立されていない。
しかし、状況は少しずつ変化していきました。仮想通貨市場の成熟とともに、カストディサービスの技術は向上し、CME(シカゴ・マーカンタイル取引所)のような規制された市場でビットコイン先物が取引されるようになりました。
そして、承認への大きな転換点となったのが、2023年8月のグレイスケール・インベストメンツ社とSECの間の裁判です。グレイスケール社は、同社が運用する非上場のビットコイン投資信託「GBTC」を現物ETFに転換する申請をSECに却下されたことを不服として提訴しました。裁判所は、「SECが、類似のリスクを持つビットコイン先物ETFを承認しているにもかかわらず、現物ETFを拒否するのは『恣意的で気まぐれ』である」として、グレイスケール社の主張を全面的に認めました。
この司法判断が決定打となり、SECは方針転換を迫られました。そして、世界最大の資産運用会社であるブラックロック社をはじめとする大手金融機関が次々と申請に参入したことも後押しとなり、2024年1月10日、ついに歴史的な承認が下されたのです。
現物ETFと先物ETFの違い
この歴史的承認を理解する上で、既(2021年)に承認されていた「先物ETF」と、今回承認された「現物ETF」の違いを知ることが不可欠です。両者は同じビットコインの価格に連動することを目指しますが、その仕組みは根本的に異なります。
| 比較項目 | ビットコイン現物ETF (Spot ETF) | ビットコイン先物ETF (Futures ETF) |
|---|---|---|
| 裏付け資産 | 実際のビットコイン(現物) | ビットコインの先物契約 |
| 価格連動性 | 現物価格との連動性が高い | 現物価格と乖離する可能性がある |
| 仕組み | 運用会社が投資家から集めた資金でビットコイン現物を購入・保管する。 | ビットコインの将来の価格を予測する「先物契約」に投資する。現物は保有しない。 |
| 主なリスク | ビットコイン自体の価格変動リスク。 | 価格変動リスクに加え、ロールオーバーコスト(限月交代に伴うコスト)による価格乖離のリスク。 |
現物ETFは、その名の通り、運用会社が裏付け資産としてビットコインの「現物」を直接購入・保有します。ETFの価格は、この保有するビットコインの価値に直接連動するため、投資家はビットコインの価格動向をほぼそのまま享受できます。
一方、先物ETFは、ビットコインの現物ではなく、「先物契約」に投資します。先物契約とは、将来の特定の期日に、あらかじめ決められた価格で商品を売買することを約束する契約です。先物ETFは、この先物契約を売買することで、ビットコイン価格への連動を目指します。しかし、先物には限月(満期日)があり、満期が近づくと次の限月の契約に乗り換える「ロールオーバー」が必要になります。この際、期近の価格より期先の価格が高い状態(コンタンゴ)だとコストが発生し、ETFのパフォーマンスが現物価格を下回る原因となります。
つまり、現物ETFの方が、より直接的かつシンプルにビットコインの価値に投資できる商品であり、だからこそ市場関係者はその登場を長年待ち望んでいたのです。
米国で承認されたビットコイン現物ETF一覧
2024年1月10日に米国で承認・上場されたビットコイン現物ETFは11本です。ここでは、その中でも代表的なものをいくつか紹介します。
| ETF名称 | 運用会社 | ティッカー | 経費率(年率) |
|---|---|---|---|
| iShares Bitcoin Trust | BlackRock | IBIT | 0.25%(当初期間限定で割引あり) |
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | Fidelity | FBTC | 0.25%(当初期間限定で無料) |
| ARK 21Shares Bitcoin ETF | ARK Invest / 21Shares | ARKB | 0.21%(当初期間限定で無料) |
| Bitwise Bitcoin ETF | Bitwise | BITB | 0.20%(当初期間限定で無料) |
| Grayscale Bitcoin Trust | Grayscale | GBTC | 1.50% |
※経費率は2024年6月時点の情報であり、変更される可能性があります。参照:各運用会社公式サイト
特筆すべきは、世界最大の資産運用会社であるブラックロック(BlackRock)や、大手金融サービスのフィデリティ(Fidelity)といった、伝統的な金融業界の巨人が参入したことです。これにより、ビットコインETFへの信頼性が一気に高まりました。また、新規参入のETFは、投資家を呼び込むために軒並み低い経費率を設定し、さらに期間限定の無料キャンペーンを展開するなど、激しい競争が繰り広げられています。
承認による市場への影響
ビットコイン現物ETFの承認は、単に新しい金融商品が生まれたという以上の、大きな影響を市場にもたらしました。
機関投資家からの資金流入
最大のインパクトは、これまで仮想通貨市場への参入に障壁を感じていた年金基金、保険会社、政府系ファンドといった「機関投資家」の資金が流入する道が開かれたことです。
機関投資家は、顧客から預かった巨額の資金を運用する立場上、コンプライアンスや規制、資産の安全性を極めて重視します。従来の仮想通貨取引所を利用した直接投資は、規制の不確実性やカストディリスクから、彼らにとっては非常にハードルの高いものでした。
しかし、ETFという彼らが使い慣れた伝統的な金融商品の枠組みが提供されたことで、状況は一変しました。SECという規制当局のお墨付きを得たETFを通じてであれば、コンプライアンス上の懸念も払拭しやすくなります。実際に、承認後の数ヶ月間で、数十億ドル規模の資金がビットコイン現物ETFに流入し、ビットコイン価格を押し上げる大きな要因となりました。この資金流入は、市場の流動性を高め、価格の安定化にも寄与すると期待されています。
仮想通貨の信頼性向上
SECによる現物ETFの承認は、ビットコインが投機の対象から、一つの正規な「アセットクラス(資産クラス)」として公に認められたことを象徴する出来事です。これまで「怪しい」「危ない」といったイメージを持たれがちだった仮想通貨が、米国の金融規制のトップであるSECによって、株式や債券、コモディティ(商品)などと並ぶ投資対象として認知された意味は非常に大きいと言えます。
この「お墨付き」は、機関投資家だけでなく、一般の個人投資家にも大きな安心感を与えました。普段利用している証券会社で、株式と同じようにビットコインに投資できるようになったことで、投資の裾野が大きく広がりました。
結果として、仮想通貨市場全体の透明性や信頼性が向上し、より健全な市場へと発展していくための重要な一歩となったのです。この承認は、仮想通貨が金融のメインストリームに組み込まれていくプロセスにおける、歴史的なマイルストーンと言えるでしょう。
仮想通貨ETFに投資する4つのメリット
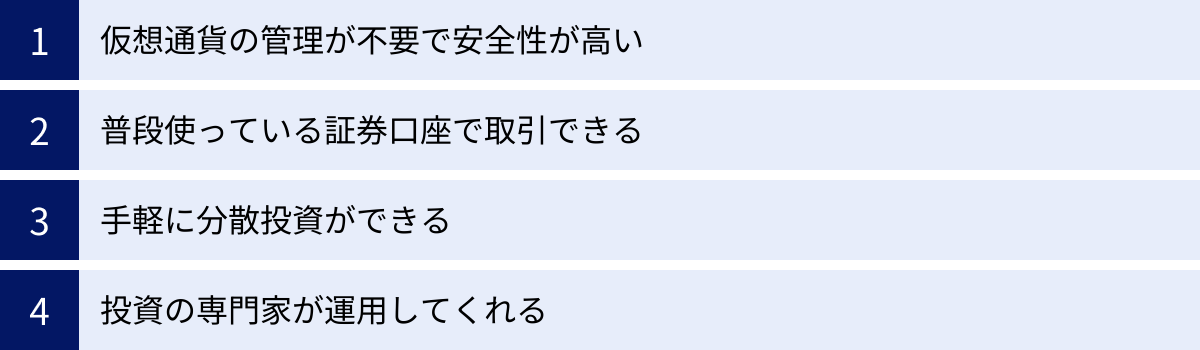
仮想通貨ETFがなぜこれほどまでに注目されるのか、その理由は投資家にとって多くのメリットがあるからです。特に、仮想通貨の現物取引に伴う課題を解決する点が大きな魅力となっています。ここでは、主な4つのメリットを具体的に解説します。
① 仮想通貨の管理が不要で安全性が高い
仮想通貨ETFに投資する最大のメリットは、ハッキングや秘密鍵の紛失といったセキュリティリスクを個人で負う必要がない点です。
仮想通貨の現物を自分で保有する場合、その管理はすべて自己責任となります。仮想通貨取引所に資産を預けっぱなしにすれば、取引所がハッキングされるリスクや、最悪の場合、倒産して資産が戻ってこないリスクがあります。実際に、過去には国内外で多くの取引所がハッキング被害に遭い、多額の顧客資産が流出する事件が発生しています。
かといって、個人のウォレット(ハードウェアウォレットなど)で管理するのも万全ではありません。ウォレットを復元するための秘密鍵やリカバリーフレーズを紛失・忘却してしまえば、その資産に二度とアクセスできなくなります。また、フィッシング詐欺などによって秘密鍵を盗まれてしまう危険性も常に存在します。
これに対し、仮想通貨ETFでは、実際の仮想通貨の管理と保管は、ETFを運用する資産運用会社が、専門の第三者機関である「カストディアン」に委託します。カストディアンは、銀行や信託会社など、資産保管を専門とする金融機関であり、オフライン環境で秘密鍵を管理する「コールドウォレット」や、複数の署名を必要とする「マルチシグ」など、極めて高度なセキュリティ体制を構築しています。
投資家はこれらの複雑なセキュリティ対策について一切気にする必要がなく、安心して資産を預けることができます。これは、テクノロジーに不慣れな方や、セキュリティ管理に不安を感じる方にとって、計り知れないメリットと言えるでしょう。
② 普段使っている証券口座で取引できる
2つ目のメリットは、その手軽さです。仮想通貨ETFは証券取引所に上場しているため、株式投資などで既に利用している証券会社の口座があれば、すぐに取引を始めることができます。
仮想通貨の現物取引を始めるには、まず数ある仮想通貨取引所の中から信頼できる業者を選び、新たに口座を開設し、本人確認手続きを行う必要があります。取引所のインターフェースや注文方法も、証券会社のそれとは異なる場合が多く、操作に慣れるまで時間がかかるかもしれません。
しかし、仮想通貨ETFであれば、これらの手間は一切不要です。いつも使っている証券会社のアプリやウェブサイトから、普段取引している国内株式や米国株式と同じ要領で、銘柄コード(ティッカー)を検索して注文を出すだけです。複数の金融資産を一つのプラットフォームで一元管理できるため、資産全体の状況を把握しやすく、ポートフォリオ管理も容易になります。
さらに、税金面の申告手続きが簡素化されるという利点もあります。日本の証券会社で「特定口座(源泉徴収あり)」を選択している場合、年間の利益が確定すると、証券会社が自動的に税金の計算と納税を行ってくれます。米国の仮想通貨ETFをこの口座で取引した場合も、他の株式などと損益を通算した上で処理されるため、原則として確定申告が不要になります(※年収2,000万円超の給与所得者など、確定申告が必要な場合もあります)。
これに対し、仮想通貨の現物取引で得た利益(雑所得)は、年末に自分で年間の損益を計算し、確定申告を行う必要があります。この手間が省ける点も、多忙な方や確定申告に不慣れな方にとっては大きな魅力です。
③ 手軽に分散投資ができる
3つ目のメリットは、一つの商品を購入するだけで、簡単に分散投資が実現できる点です。
これは特に、複数の仮想通貨で構成される指数に連動するタイプのETFにおいて顕著です。例えば、「主要な仮想通貨トップ10の時価総額加重平均指数」に連動するETFが登場したとします。このETFを1単位購入するだけで、ビットコインやイーサリアムをはじめとする10種類の仮想通貨に、それぞれの時価総額に応じた比率で投資したのと同じ効果が得られます。
もし個人で同じことをやろうとすれば、10種類の仮想通貨をそれぞれ適切な比率で購入し、価格変動に応じて定期的に資産配分を調整(リバランス)するという、非常に煩雑な作業が必要になります。
ビットコイン単体に連動するETFであっても、自身の投資ポートフォリオに仮想通貨という新しいアセットクラスを組み入れる、という意味での分散効果が期待できます。株式や債券といった伝統的な資産とは異なる値動きをすることが多いため、ポートフォリオ全体のリスクを低減させ、リターンの安定化に貢献する可能性があります。
このように、仮想通貨ETFは、少ない資金と手間で、効果的なリスク分散を実現するための優れたツールとなり得ます。
④ 投資の専門家が運用してくれる
4つ目のメリットとして、金融のプロフェッショナルである資産運用会社がETFの組成・運用を行ってくれる点が挙げられます。
ETFは、連動対象とする指数(インデックス)のパフォーマンスを正確に追随するように設計されています。運用会社は、指数の構成銘柄の変更や比率の調整に合わせて、実際に保有する仮想通貨の売買(リバランス)を適切に行います。
また、そもそもETFを組成する段階で、どの仮想通貨や指数を対象とするか、どのようなカストディアンを選定して資産を安全に保管するか、といった重要な判断も、すべて専門家が行っています。
投資家は、複雑な市場分析や銘柄選定、日々のポートフォリオ管理に頭を悩ませる必要がありません。信頼できる運用会社が提供するETFを選ぶだけで、プロが構築した投資戦略を手軽に活用できるのです。これは、特に投資経験の浅い初心者の方や、本業が忙しく投資に多くの時間を割けない方にとって、安心して投資を始められる大きな安心材料となります。
仮想通貨ETFに投資する3つのデメリット・注意点
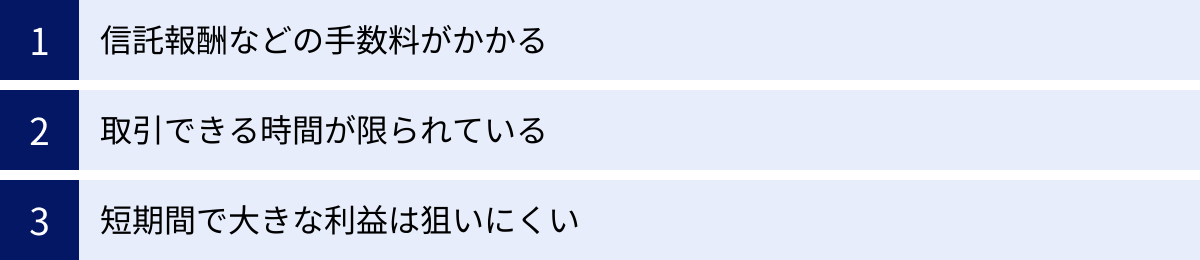
仮想通貨ETFは多くのメリットを持つ一方で、投資を始める前に知っておくべきデメリットや注意点も存在します。メリットとデメリットの両方を理解し、リスクを把握した上で判断することが重要です。
① 信託報酬などの手数料がかかる
仮想通貨ETFへの投資における最も基本的なデメリットは、保有している限りコストが発生し続けることです。主なコストは以下の2種類です。
- 信託報酬(経費率):
これはETFを運用・管理してもらうための経費として、運用会社に支払う手数料です。ETFの純資産総額に対して年率〇%という形で計算され、日割りで信託財産から差し引かれます。つまり、投資家は直接支払う感覚はありませんが、保有しているだけで毎日コストがかかっていることになります。米国のビットコイン現物ETFの経費率は、年率0.2%~1.5%程度と様々ですが、長期で保有すればするほど、このコストがリターンを押し下げる要因となります。仮想通貨の現物を自分で保有していれば、このような継続的なコストは発生しません。 - 売買委託手数料:
これはETFを売買する際に、利用する証券会社に支払う手数料です。株式の売買手数料と同じもので、取引金額に応じて手数料が決まります。近年は手数料の無料化が進んでいますが、証券会社や取引条件によっては手数料が発生する場合があります。
これらの手数料は、特に長期的なパフォーマンスに影響を与えます。例えば、年率0.5%の信託報酬がかかるETFを100万円分保有していると、年間で5,000円のコストがかかり続けます。わずかな差に見えても、複利効果で運用する期間が長くなればなるほど、その影響は無視できなくなります。ETFを選ぶ際には、リターンだけでなく、これらのコストもしっかりと比較検討することが不可欠です。
② 取引できる時間が限られている
仮想通貨ETFの利便性の裏返しとも言えるデメリットが、取引時間の制約です。
ビットコインをはじめとする仮想通貨の市場は、特定の取引所というものが存在せず、世界中の参加者によって24時間365日、常に取引が行われています。価格は土日や深夜でも絶えず変動しています。
一方で、仮想通貨ETFは証券取引所に上場している金融商品であるため、その取引所の取引時間内でしか売買できません。例えば、米国のETFであれば、日本時間の深夜から早朝にかけての米国市場が開いている時間帯に限られます。
これは、投資家にとって大きなリスクとなり得ます。もし、取引所のクローズ時間(例えば、日本の週末や米国の夜間)に、市場に大きな影響を与えるニュースが発表され、仮想通貨価格が急騰または急落したとします。現物取引であれば即座に売買して対応できますが、ETFの保有者は、翌営業日に取引所が開くまで、ただ価格の変動を見守るしかありません。その間に大きな損失を被ってしまう可能性や、利益を得る機会を逃してしまう可能性があります。
このように、市場の急変時にタイムリーな対応ができない「時間外リスク」は、仮想通貨ETFの構造的な弱点として認識しておく必要があります。
③ 短期間で大きな利益は狙いにくい
仮想通貨ETFは、比較的安全で手軽に投資できる反面、仮想通貨の現物取引で見られるような、短期間での爆発的なリターンは期待しにくいという側面があります。
その理由はいくつかあります。
- 分散効果の裏返し: 複数の仮想通貨に分散投資するタイプのETFの場合、ポートフォリオ全体の値動きはマイルドになります。一部の銘柄が10倍に高騰したとしても、他の銘柄のパフォーマンスが低調であれば、ETF全体のリターンは限定的になります。これはリスクを抑えるというメリットの裏返しです。
- レバレッジが効かない: 仮想通貨の現物取引では、証拠金を担保に自己資金の何倍もの取引ができるレバレッジ取引が可能です(国内では最大2倍)。レバレッジをかければ、少ない資金で大きな利益を狙える可能性がありますが、ETFは基本的に現物資産への投資であるため、レバレッジはかかりません。ハイリスク・ハイリターンを求める投資家には物足りなく感じるかもしれません。
- いわゆる「草コイン」は対象外: ETFの投資対象となるのは、基本的にビットコインやイーサリアムなど、時価総額が大きく、流動性や信頼性が高い主要な仮想通貨に限られます。時価総額が低く、将来的に価格が100倍、1000倍になる可能性を秘めた、いわゆる「草コイン」や「アルトコイン」に投資して一攫千金を狙うような戦略は、ETFでは取れません。
仮想通貨ETFは、あくまでも既存の金融システムの枠組みの中で、比較的安全に、長期的な視点で資産形成を目指すためのツールです。仮想通貨が持つボラティリティ(価格変動の大きさ)を活かした短期的な投機や、ハイリスクなリターンを追求する投資スタイルには向いていないことを理解しておくべきでしょう。
日本で仮想通貨ETFを買う方法
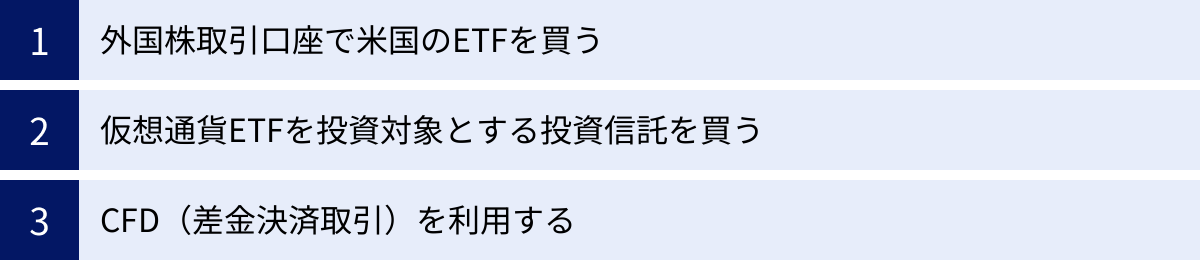
米国でビットコイン現物ETFが承認されたというニュースを聞いて、「日本でもすぐに買えるの?」と期待した方も多いかもしれません。しかし、現状はそう単純ではありません。ここでは、日本における仮想通貨ETFの現状と、日本在住の投資家が間接的に投資するための具体的な方法を解説します。
現状、日本の取引所で仮想通貨ETFは購入できない
まず、最も重要な事実として、2024年6月現在、日本の証券取引所では仮想通貨ETFは一切取り扱われていません。つまり、国内の証券会社を通じて、円建てで仮想通貨ETFを直接購入することはできません。
その理由は、日本の法律にあります。投資信託のルールを定めた「投資信託及び投資法人に関する法律(投信法)」において、投資信託が主要な投資対象とできる資産(有価証券、不動産など)に、仮想通貨が含まれていないためです。この法律が改正されない限り、日本の資産運用会社が仮想通貨ETFを組成・販売することは不可能です。
米国での承認を受け、日本でも解禁に向けた議論が始まりつつありますが、金融庁は投資家保護の観点から慎重な姿勢を崩しておらず、実現にはまだ時間がかかると見られています。したがって、現時点では海外の市場に上場しているETFにアクセスするという方法を取る必要があります。
日本から間接的に投資する3つの方法
日本国内での直接購入はできませんが、諦める必要はありません。日本の個人投資家が米国のビットコイン現物ETFなどに投資するための、現実的な方法が3つ存在します。
① 外国株取引口座で米国のETFを買う
これが、米国のビットコイン現物ETFに投資するための最も直接的で一般的な方法です。SBI証券、楽天証券、マネックス証券といった日本の主要なネット証券では、「外国株式取引口座」を開設することができます。この口座を通じて、ニューヨーク証券取引所(NYSE)やNASDAQに上場している米国の株式やETFを、日本から売買することが可能です。
具体的な手順は以下の通りです。
- 証券会社の総合口座と外国株式取引口座を開設する。(すでに総合口座があれば、追加で外国株口座の申し込みをするだけです)
- 証券口座に日本円を入金する。
- 入金した日本円を米ドルに両替(為替取引)する。
- 米国市場の取引時間内に、購入したいETFのティッカー(例:IBIT)を検索し、株式と同じように注文を出す。
この方法のメリットは、本物のビットコイン現物ETFそのものを購入できることです。一方で、注意点として以下の点が挙げられます。
- 為替リスク: 購入も売却も米ドル建てで行うため、為替レートの変動によって円換算での資産価値が変わります。円高が進むと、ETFの価格が上昇していても円ベースでは損失が出る可能性があります。
- 手数料: 日本円と米ドルを両替する際の「為替手数料」と、ETFを売買する際の「米国株取引手数料」がかかります。
- 取引時間: 米国市場の取引時間(日本時間の夜間)に取引する必要があります。
② 仮想通貨ETFを投資対象とする投資信託を買う
もう一つの方法として、日本国内で販売されている投資信託(非上場)の中に、ポートフォリオの一部として米国のビットコインETFを組み入れている商品を探すというアプローチがあります。
この方法のメリットは、円建てで、100円や1,000円といった少額から積立投資ができる手軽さにあります。外国株口座を開設したり、自分でドルに両替したりする手間もかかりません。
ただし、この方法はまだ一般的ではなく、該当する投資信託は非常に限られています。また、注意点として、その投資信託がビットコインETFに投資している比率はごく一部かもしれません。投資信託全体のパフォーマンスは、組み入れられている他の株式や債券の動向に大きく左右されます。
したがって、純粋にビットコインの値動きに投資したいという目的には、あまり適していない可能性があります。あくまでポートフォリオ全体の一部として、間接的に触れてみたいという方向けの選択肢と言えるでしょう。
③ CFD(差金決済取引)を利用する
より上級者向けの方法として、CFD(Contract for Difference:差金決済取引)を利用する方法があります。
CFDとは、現物の資産を直接保有することなく、その資産の価格を参照して、売買した時の差額だけを決済する金融商品です。多くのCFDブローカーでは、ビットコインやイーサリアムといった仮想通貨を参照する銘柄を取り扱っています。
CFDの最大の特徴はレバレッジです。少ない証拠金で大きな金額の取引ができるため、資金効率が高いというメリットがあります。また、「売り」から入ることもできるため、下落局面でも利益を狙うことが可能です。
しかし、レバレッジは諸刃の剣です。予想が外れた場合、損失も同样に大きくなり、預けた証拠金以上の損失が発生するリスク(追証)もあります。また、CFDはETFとは全く異なる、より複雑でハイリスクな金融デリバティブ商品です。その仕組みを十分に理解せずに手を出すのは非常に危険です。
CFDは、あくまで短期的な価格変動を狙ったトレーディングの手法であり、長期的な資産形成を目指すETF投資とは性質が大きく異なります。十分な知識と経験を持つ上級者向けの選択肢と位置づけるのが賢明です。
仮想通貨ETFの投資におすすめの証券会社
日本から米国の仮想通貨ETFに投資する場合、どの証券会社を選ぶかが重要になります。手数料の安さ、取扱銘柄の豊富さ、ツールの使いやすさなどを比較して、自分に合った証券会社を選びましょう。ここでは、米国株(ETF)取引に定評のある主要なネット証券3社を紹介します。
| 証券会社 | 米国ETF取扱銘柄数 | 米国株取引手数料(税込) | 為替手数料(片道) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| SBI証券 | 約6,000銘柄以上 | 約定代金の0.495%(上限22米ドル) | 25銭(住信SBIネット銀行経由で6銭) | 取扱銘柄数トップクラス。対象ETFの買付手数料が無料。為替コストが非常に安い。 |
| 楽天証券 | 約5,000銘柄以上 | 約定代金の0.495%(上限22米ドル) | 25銭 | 対象ETFの買付手数料が無料。楽天ポイントでの投資が可能。取引ツールが使いやすい。 |
| マネックス証券 | 約5,000銘柄以上 | 約定代金の0.495%(上限22米ドル) | 買付時0銭、売却時25銭 | 買付時の為替手数料が無料。米国株の分析ツール「銘柄スカウター」が非常に高機能。 |
※2024年6月時点の情報。手数料等は変更される可能性があるため、詳細は各社公式サイトでご確認ください。参照:SBI証券公式サイト、楽天証券公式サイト、マネックス証券公式サイト
SBI証券
SBI証券は、総合力で非常に評価の高いネット証券です。特に米国株・ETFの取扱銘柄数は業界トップクラスで、ビットコイン現物ETFも主要なものはすべて取り扱っています。
最大の強みの一つが為替手数料の安さです。グループ会社である住信SBIネット銀行の外貨預金口座を利用してドルを準備すれば、為替手数料はわずか1ドルあたり6銭(2024年6月時点)に抑えられます。これは他の証券会社と比較して圧倒的に有利な水準であり、取引コストを重視する投資家にとって大きなメリットです。
また、「SBI ETFセレクション」というプログラムがあり、対象となっている人気の米国ETF10銘柄の買付手数料が無料になります。将来的にはこのプログラムにビットコインETFが含まれる可能性も期待されます。豊富な商品ラインナップと低コストを両立させたい方におすすめです。
楽天証券
楽天証券は、楽天経済圏のユーザーにとって非常に魅力的な選択肢です。楽天市場などで貯めた楽天ポイントを使って米国ETFを購入できるため、現金を使わずに投資を始めることも可能です。
取引ツールにも定評があり、スマートフォンアプリ「iSPEED」は直感的で使いやすく、初心者でもスムーズに取引ができます。SBI証券と同様に、対象の米国ETF15銘柄の買付手数料が無料になるプログラムも提供しており、コストを抑えた投資が可能です。
取扱銘柄数も豊富で、主要なビットコイン現物ETFは問題なく取引できます。普段から楽天のサービスをよく利用する方や、使いやすいツールで手軽に始めたい方に適しています。
マネックス証券
マネックス証券は、特に米国株投資に力を入れている証券会社として知られています。その最大の特徴は、買付時の為替手数料が無料(0銭)であることです。日本円から直接米ドル建てのETFを購入する際に為替手数料がかからないため、コストを気にせず気軽に買い付けができます。(売却時には25銭かかります)
また、独自の投資分析ツール「銘柄スカウター米国株」が非常に強力です。企業の詳細な業績データやアナリストの評価などを視覚的に分かりやすく確認でき、ETF選びや市場分析に大いに役立ちます。
取扱銘柄数も豊富で、情報収集を重視し、本格的に米国株・ETF投資に取り組みたいと考えている投資家にとって、非常に頼りになる証券会社と言えるでしょう。
仮想通貨ETFの今後の見通しと将来性
ビットコイン現物ETFの承認は、ゴールではなく、新たな時代の始まりに過ぎません。今後、仮想通貨ETF市場はどのように発展していくのでしょうか。ここでは、その将来性を左右する2つの大きなテーマについて考察します。
イーサリアムなど他の仮想通貨ETFへの期待
ビットコインに次ぐ関心事として、時価総額第2位の仮想通貨であるイーサリアムの現物ETFが挙げられます。ブラックロック社をはじめ、ビットコインETFを申請した運用会社の多くが、イーサリアムの現物ETFについてもSECに申請を行っていました。
当初、SECはイーサリアムが「証券」に該当するかどうかという法的論点から慎重な姿勢を見せていましたが、市場の予想を覆し、2024年5月23日に主要な申請書類(フォーム19b-4)を承認しました。これは、イーサリアム現物ETFが実際に市場で取引されるための大きな一歩であり、市場にポジティブなサプライズをもたらしました。今後は、個別のETF商品に関する最終的な承認(フォームS-1の有効化)を経て、2024年内にも取引が開始されるとの見方が強まっています。(参照:米国証券取引委員会(SEC)ウェブサイト)
イーサリアムETFが実現すれば、その影響は計り知れません。イーサリアムは、単なる価値の保存手段としてのビットコインとは異なり、スマートコントラクトというプログラムを実行するプラットフォームとしての機能を持っています。DeFi(分散型金融)やNFT(非代替性トークン)といった、Web3.0時代の基盤技術です。イーサリアムETFの登場は、こうしたテクノロジーとしての側面も含めて、イーサリアムへの投資を加速させるでしょう。
さらに、ビットコイン、イーサリアムという市場の二大巨頭のETFが承認されれば、将来的にはソラナ(SOL)やリップル(XRP)といった他の有力なアルトコインのETFが登場する道も開かれる可能性があります。これにより、投資家はより多様な仮想通貨に、ETFという安全な形でアクセスできるようになり、仮想通貨市場全体へのさらなる資金流入と、市場の成熟が期待されます。
日本での取り扱い開始への期待
もう一つの大きなテーマは、日本国内での仮想通貨ETFの解禁です。前述の通り、現状では日本の法律が障壁となっていますが、米国での成功事例は、日本の規制当局や金融業界に大きな影響を与える可能性があります。
もし日本で仮想通貨ETFが解禁されれば、投資家にとって以下のような多大なメリットが生まれます。
- 円建てでの取引: 為替リスクや為替手数料を気にすることなく、日本円で直接投資できます。
- NISA(少額投資非課税制度)の活用: 成長投資枠などを利用して、非課税で仮想通貨に投資できる可能性が生まれます。これは個人投資家にとって極めて大きなメリットです。
- さらなる投資家層の拡大: 国内の証券会社で手軽に取引できるようになれば、これまで仮想通貨に縁のなかった層も投資を始めやすくなり、市場の裾野が一気に広がります。
すでに、一部の政治家や業界団体からは、国際的な競争力の観点からも早期の解禁を求める声が上がっています。金融庁も、海外の動向を注視しつつ、投資家保護を大前提とした上での検討を進めていくものと見られます。
ただし、法改正には慎重かつ時間を要する議論が必要です。すぐに実現する可能性は低いですが、中長期的には、日本でも仮想通貨ETFが当たり前に取引される時代が来る可能性は十分にあると言えるでしょう。その動向は、日本の金融市場と仮想通貨の未来を占う上で、引き続き注目していくべき重要なポイントです。
仮想通貨ETFに関するよくある質問
ここまで仮想通貨ETFについて詳しく解説してきましたが、まだ残る細かい疑問について、Q&A形式でお答えします。
なぜ今までビットコイン現物ETFは承認されなかったのですか?
ビットコイン現物ETFが10年以上にわたって承認されなかった主な理由は、米国の規制当局であるSEC(米国証券取引委員会)が、投資家保護の観点からいくつかの深刻な懸念を抱いていたためです。具体的には以下の3点が繰り返し指摘されてきました。
- 市場操作のリスク: ビットコインの現物市場は、株式市場のように統一された監視体制がなく、一部の取引所に取引が集中しているため、価格が不正に操作(相場操縦)される危険性が高いと判断されていました。
- カストディ(資産保管)体制の不備: 仮想通貨というデジタル資産を、ハッキングなどのリスクから安全に、かつ大規模に保管するための信頼できる仕組み(カストディ)が十分に確立されていないと見なされていました。
- 投資家保護の枠組みの欠如: 詐欺や盗難が多発する中で、投資家の資産を保護するための規制やルールが未整備であると考えられていました。
しかし、長年の間に、CME(シカゴ・マーカンタイル取引所)での先物取引の開始による市場監視の強化や、コインベース・カストディのような信頼性の高い保管サービスの登場など、状況は大きく改善しました。最終的には、裁判所が「先物ETFを認めておきながら現物ETFを認めないのは不合理」との判断を下したことが決定打となり、SECも承認せざるを得ない状況になった、というのが実情です。
イーサリアムの現物ETFは承認されますか?
市場では、承認はほぼ確実視されています。 2024年5月23日に、SECは複数のイーサリアム現物ETFの上場申請に関する重要書類を承認しました。これは上場に向けた手続きの大部分が完了したことを意味し、あとは最終的な事務手続きを残すのみとされています。市場関係者の間では、2024年の夏から秋にかけて取引が開始されるのではないかと予測されています。
ただし、ビットコインと異なり、イーサリアムには「証券性」をめぐる議論がありました。もしイーサリアムが法律上の「証券」と見なされると、より厳しい規制の対象となります。SECはこの点について長らく明確な態度を示してきませんでしたが、今回の承認は、少なくともETFの裏付け資産として問題ないという判断が下されたことを示唆しています。この承認は、イーサリアムがアセットクラスとしてさらに広く認知されるための重要な一歩となります。
日本でビットコインETFが承認される可能性はありますか?
中長期的には可能性はありますが、短期的には難しいというのが一般的な見方です。
日本で仮想通貨ETFを解禁するためには、主に「投資信託及び投資法人に関する法律(投信法)」の改正が必要です。この法律では、投資信託が投資できる資産が定められており、現状では仮想通貨はそこに含まれていません。
金融庁は、投資家保護を最優先する立場から、仮想通貨の価格変動の大きさや規制の不確実性に対して非常に慎重な姿勢を保っています。米国でのETFの運用実績や、そこで問題が発生しないかなどを十分に見極めた上で、国内での議論が本格化すると考えられます。
自民党のweb3プロジェクトチームなどが法改正に向けた提言を行っており、政治レベルでの動きは始まっていますが、実際に法案が国会で審議され、可決・施行されるまでには、数年単位の時間が必要になる可能性が高いでしょう。とはいえ、グローバルな金融競争の流れに取り残されないためにも、将来的には解禁に向けた動きが加速することが期待されています。
まとめ
本記事では、次世代の投資商品として注目される「仮想通貨ETF」について、その基本からメリット・デメリット、日本での購入方法、そして将来性までを包括的に解説しました。
最後に、重要なポイントを改めて整理します。
- 仮想通貨ETFとは、ビットコインなどの仮想通貨の価格に連動する上場投資信託(ETF)であり、投資家は仮想通貨を直接保有することなく、その値動きに投資できます。
- 最大のメリットは、ハッキングや秘密鍵紛失のリスクがなく安全性が高いこと、そして普段利用している証券会社の口座で株式と同じように手軽に取引できることです。
- 一方で、信託報酬という保有コストがかかり続けることや、24時間取引できないといったデメリットも存在します。
- 2024年1月、米国でビットコイン現物ETFが歴史的に承認され、機関投資家からの大規模な資金流入を促し、仮想通貨市場全体の信頼性を大きく向上させました。
- 現状、日本国内の取引所では仮想通貨ETFは購入できません。しかし、SBI証券や楽天証券などの外国株式取引口座を開設すれば、米国のETFに投資することが可能です。
- 今後は、イーサリアム現物ETFの登場や、日本国内での解禁に向けた議論が、市場のさらなる発展の鍵を握っています。
仮想通貨ETFは、仮想通貨投資のハードルを劇的に下げ、より多くの人々にとって身近なものに変えるポテンシャルを秘めています。それは、ハイリスク・ハイリターンな投機というイメージを払拭し、長期的な資産形成のポートフォリオに組み入れる一つの選択肢として、仮想通貨が成熟していく過程の象徴と言えるでしょう。
この記事が、仮想通貨ETFへの理解を深め、ご自身の投資戦略を考える上での一助となれば幸いです。まずは少額からでも始められる証券会社の口座を開設し、新しい投資の世界を覗いてみてはいかがでしょうか。