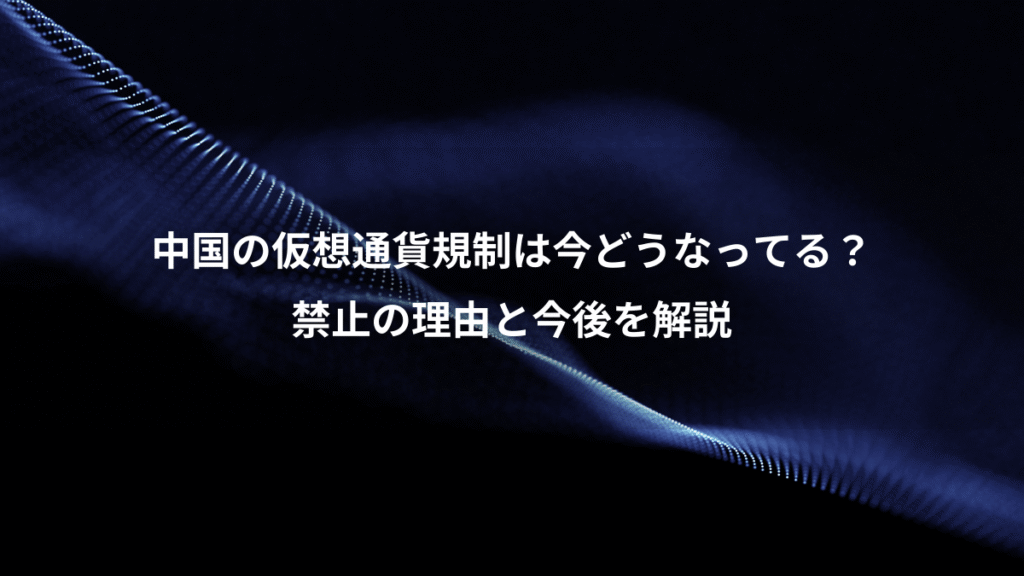かつて世界の仮想通貨市場を牽引するほどの存在感を示していた中国。しかし、度重なる厳しい規制強化により、その様相は一変しました。現在、中国本土では仮想通貨に関連する活動のほとんどが禁止されていますが、その一方で香港では仮想通貨ハブを目指す動きが活発化するなど、状況は複雑化しています。
この記事では、2024年最新の中国における仮想通貨規制の現状を徹底的に解説します。中国政府がなぜこれほどまでに仮想通貨を厳しく取り締まるのか、その背景にある4つの理由を深掘りし、これまでの規制の歴史を時系列で振り返ります。
さらに、中国の規制が世界の仮想通貨市場に与えた影響や、デジタル人民元との関係、そして今後の見通しについても多角的に分析します。中国の動向は、世界の仮想通貨市場の未来を占う上で欠かせない要素です。この記事を読めば、複雑な中国の仮想通貨事情の全体像を、初心者の方でも論理的に理解できるようになるでしょう。
目次
中国の仮想通貨に対する規制の現状【2024年最新版】
2024年現在、中国の仮想通貨に対する姿勢は「本土での全面禁止」と「香港での限定的な容認」という二つの側面を持っています。この極端な対比は、「一国二制度」という特殊な統治体制を背景に生まれています。ここでは、中国本土と香港、それぞれの現状を詳しく見ていきましょう。
中国本土では仮想通貨関連サービスを全面的に禁止
現在の中国本土における仮想通貨規制の結論から述べると、仮想通貨に関連する商業活動や金融サービスは、ほぼすべてが非合法的と見なされ、全面的に禁止されています。 これは、2021年9月に中国人民銀行(中央銀行)をはじめとする10の政府機関が連名で発表した「仮想通貨取引の投機リスクのさらなる防止と対処に関する通知」によって決定的なものとなりました。
この通知により、以下の行為が明確に違法と定義されています。
- 法定通貨と仮想通貨の交換業務
- 仮想通貨間の交換業務
- 仮想通貨の売買
- 仮想通貨取引の情報仲介や価格設定サービスの提供
- トークン発行による資金調達(ICOなど)
- 仮想通貨デリバティブ取引
- 仮想通貨のマイニング(採掘)活動
つまり、仮想通貨取引所の運営はもちろんのこと、個人が仮想通貨を売買したり、仮想通貨を決済手段として利用したりすることも固く禁じられています。さらに、海外の仮想通貨取引所がインターネットを通じて中国国内の居住者にサービスを提供することも違法とされ、関連するウェブサイトやアプリへのアクセスもブロックされています。
この規制の背景には、後述する資本流出の防止や金融システムの安定維持、そして国家が管理するデジタル通貨「デジタル人民元」の普及を促進したいという強力な国家の意思があります。違反した個人や組織には厳しい罰則が科される可能性があり、関連する金融口座が凍結されるなどの措置が取られます。
この徹底した規制により、かつては世界のビットコイン取引量やマイニングのハッシュレート(計算能力)の大部分を占めていた中国は、公式には仮想通貨市場から完全に姿を消したことになります。中国政府のスタンスは「仮想通貨そのものではなく、その基盤技術であるブロックチェーンは推進する」というものであり、この「幣鏈分離(通貨とチェーンの分離)」の原則が一貫して貫かれています。
個人による仮想通貨の保有はグレーゾーン
前述の通り、仮想通貨の取引や関連サービスは全面的に禁止されていますが、一方で個人が資産として仮想通貨を「保有」すること自体を直接的に禁止する法律は、現時点では存在しません。 この点が、中国の仮想通貨規制の最も複雑な部分であり、「グレーゾーン」とされています。
過去の民事裁判においては、ビットコインなどの仮想通貨が「仮想財産」として法的に認められ、所有権が保護されるべきであるとの判決が出た事例も存在します。これは、個人間で発生した窃盗や詐欺などのトラブルにおいて、被害者が法的救済を求める際の根拠となり得ます。
しかし、これはあくまで民事上の解釈に過ぎません。重要なのは、たとえ保有が黙認されているとしても、それを中国国内で合法的に売買したり、人民元に換金したりする手段が完全に断たれているという事実です。つまり、中国国内の個人が保有する仮想通貨は、実質的に「塩漬け」状態にあり、資産としての流動性は極めて低いと言わざるを得ません。
このグレーゾーンは、多くのリスクをはらんでいます。
- 法改正のリスク: 今後、政府の方針が変わり、個人の保有自体が違法と見なされる可能性はゼロではありません。
- 法的保護の欠如: 仮想通貨に関連する詐欺やハッキングの被害に遭った場合、取引自体が違法な活動と見なされるため、警察や司法による十分な保護を受けられない可能性があります。
- 換金の困難さ: 保有する仮想通貨を換金するには、海外のP2P(個人間)プラットフォームなどを利用するしかありませんが、これは当局の監視対象となりやすく、口座凍結などのリスクを伴います。
結論として、中国本土において個人が仮想通貨を保有することは直ちに違法とは言えないものの、それは極めて不安定でリスクの高い状態に置かれていると理解するのが適切です。事実上、資産としての価値を自由に実現する道は閉ざされているのが現状です。
香港では仮想通貨の取引が活発化
中国本土の厳しい規制とは対照的に、特別行政区である香港では、仮想通貨に対する規制緩和が進み、取引が活発化しています。これは「一国二制度」の下、香港が独自の法制度と金融システムを維持しているために可能なことです。
大きな転換点となったのは、2023年6月1日に施行された、証券先物委員会(SFC)による新たな仮想通貨サービスプロバイダー(VASP)向けのライセンス制度です。 この制度により、SFCから正式なライセンスを取得した取引所は、個人投資家(リテール投資家)に対しても仮想通貨の現物取引サービスを提供できるようになりました。
| 項目 | 中国本土 | 香港特別行政区 |
|---|---|---|
| 規制の基本方針 | 全面的な禁止 | 規制下での容認と促進 |
| 取引所の運営 | 違法 | ライセンス制(SFC認可が必要) |
| 個人投資家の取引 | 違法 | 認可取引所を通じて可能 |
| 対象資産 | – | SFCが認める主要な仮想通貨(BTC, ETHなど) |
| 政府の目標 | 金融安定、資本管理、デジタル人民元普及 | 国際的なWeb3・仮想通貨ハブの構築 |
| 法的根拠 | 中国人民銀行等の通知(2021年) | VASPライセンス制度(2023年) |
このライセンス制度は非常に厳格で、投資家保護の観点から、取り扱い可能な銘柄の選定、資産の分別管理、保険の付保、サイバーセキュリティ対策など、多岐にわたる要件が定められています。当初はビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)といった流動性の高い主要な銘柄に限定されていましたが、市場の発展とともにその範囲は拡大していく可能性があります。
さらに、2024年4月には、香港でアジア初となるビットコインとイーサリアムの現物ETF(上場投資信託)が承認され、取引が開始されました。 これは、機関投資家だけでなく、個人投資家も従来の証券口座を通じて、より手軽かつ安全に仮想通貨市場へアクセスできる道を開くものであり、香港が仮想通貨の金融ハブとしての地位を確立する上で極めて重要な一歩です。
香港政府がこのように仮想通貨に前向きな姿勢を示す背景には、シンガポールやドバイなど、他の都市との国際金融センターとしての競争があります。Web3.0時代の新たな金融イノベーションを取り込み、世界中の企業や才能、資本を引きつけることで、経済の新たな成長エンジンにしたいという狙いがあります。
このように、中国本土が仮想通貨を徹底的に排除する一方で、そのすぐ隣の香港が国際的な仮想通貨ハブを目指すという、ねじれとも言える状況が生まれています。この「本土の壁」と「香港の窓」という構造は、今後の中国と世界の仮想通貨市場の関係を読み解く上で最も重要な鍵となるでしょう。
中国が仮想通貨を厳しく規制・禁止する4つの理由
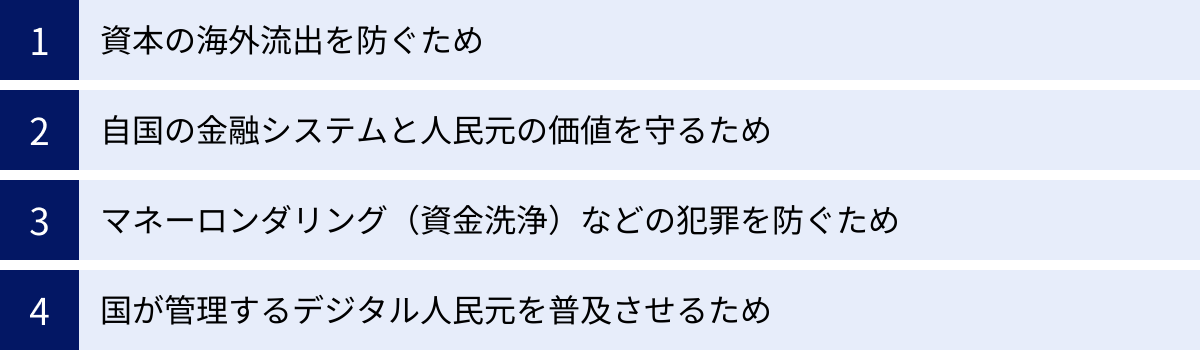
中国政府がなぜこれほどまでに仮想通貨に対して厳しい姿勢を取り続けるのか。その背景には、単一の理由ではなく、経済、金融、社会、そして政治的な思惑が複雑に絡み合った4つの主要な動機が存在します。これらの理由を理解することは、中国の規制の本質と今後の動向を予測する上で不可欠です。
① 資本の海外流出を防ぐため
中国が仮想通貨を厳しく規制する最も根源的な理由の一つが、資本の海外流出(キャピタルフライト)に対する強い警戒感です。
中国は長年にわたり、自国経済の安定と為替レートの管理を目的として、厳格な資本規制を実施してきました。例えば、中国の個人が海外に持ち出せる外貨の額は、年間5万米ドル相当に制限されています。これは、国内の資金が過度に海外へ流出し、人民元相場が急落したり、国内の投資が滞ったりする事態を防ぐための重要な防衛ラインです。
しかし、ビットコインをはじめとする仮想通貨は、この資本規制を容易にすり抜ける手段となり得ます。仮想通貨は、国境の概念がなく、銀行などの金融機関を介さずに、インターネットさえあれば瞬時に世界中のどこへでも送金が可能です。この特性は、政府の管理を逃れて資産を海外に移したいと考える富裕層や企業にとって、非常に魅力的な抜け穴となります。
具体的には、以下のようなシナリオが懸念されています。
- 中国国内で人民元を使って、P2P(個人間)取引などを通じて非合法に仮想通貨を購入する。
- 購入した仮想通貨を、海外の取引所や個人のウォレットに送金する。このプロセスは政府の監視が困難。
- 海外で仮想通貨を米ドルやユーロなどの法定通貨に換金し、現地の銀行口座に入金したり、不動産などの資産を購入したりする。
このような動きが大規模に行われれば、中国政府が築き上げてきた資本規制の壁は意味をなさなくなります。それは結果的に、人民元への売り圧力となって通貨価値を不安定にし、ひいては中国経済全体の安定を揺るがしかねません。
特に、経済の先行き不透明感が高まる時期や、政府の引き締めが強化される局面では、資産を安全な国外へ逃避させたいというインセンティブが強まります。中国政府にとって、国家による管理が及ばない仮想通貨は、統制経済の根幹を揺るがす潜在的な脅威であり、その抜け道を塞ぐことは国家の経済安全保障における最優先課題の一つなのです。
② 自国の金融システムと人民元の価値を守るため
第二の理由は、既存の金融システムの安定性を確保し、国家の基軸通貨である人民元の権威を守るためです。
仮想通貨は、その価格変動の激しさ(ボラティリティ)で知られています。もし、このような投機的な資産が金融システムの中に深く組み込まれてしまうと、価格の暴落が起きた際に金融機関の経営を揺るがし、システミックリスク(個別の金融機関の破綻が金融システム全体に連鎖的に広がるリスク)を引き起こす可能性があります。中国政府は、2008年の世界金融危機のような事態を自国で引き起こすことを極度に恐れており、リスクの芽は早期に摘み取るという方針を取っています。
さらに根源的な問題として、仮想通貨は国家による管理を受けない「超国家的な通貨」であるという点があります。現代の国家経済は、中央銀行がマネーサプライ(通貨供給量)を調整したり、金利を操作したりする金融政策を通じて成り立っています。これにより、インフレを抑制したり、景気を刺激したりすることが可能になります。
しかし、もし国民が人民元ではなく、ビットコインのような民間の仮想通貨を主要な決済手段や価値の保存手段として使い始めるとどうなるでしょうか。中央銀行の金融政策は、その影響力を失ってしまいます。国家の管理下にない通貨が社会に広く浸透することは、通貨発行権という国家主権の根幹を脅かす行為に他なりません。
中国共産党は、経済と社会に対する強力なコントロールを維持することを統治の基本としています。そのため、中央集権的な管理が不可能な非中央集権型(Decentralized)の仮想通貨は、その思想と真っ向から対立する存在です。人民元に対する国民の信頼を維持し、金融政策の有効性を確保するためにも、競合となりうる仮想通貨の普及を徹底的に抑え込む必要があるのです。
2017年のICOブームやその後の投機熱は、多くの一般市民を巻き込み、大きな損失を生む可能性がありました。こうした投機活動が社会不安につながることを防ぐという意味でも、政府は仮想通貨を「人民の財産を深刻に侵害する」存在と位置づけ、規制を強化する正当性を主張しています。
③ マネーロンダリング(資金洗浄)などの犯罪を防ぐため
第三の理由は、社会の安定と秩序を維持する観点から、仮想通貨が持つ匿名性がマネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与、その他の違法行為に悪用されることを防ぐためです。
仮想通貨取引は、特にP2P取引やプライバシーコイン(匿名性の高い仮想通貨)を利用した場合、送金者と受信者の身元を特定することが困難になる場合があります。この特性は、犯罪によって得た収益の出所を隠蔽し、合法的な資産であるかのように見せかけるマネーロンダリングにとって、非常に都合の良いツールとなります。
中国政府が特に懸念しているのは、以下のような犯罪への悪用です。
- 汚職・腐敗: 政府高官や企業幹部が受け取った賄賂を仮想通貨に換え、追跡を困難にする。
- 違法な資金調達: 詐欺的な投資スキームやネズミ講などで集めた資金を仮想通貨で持ち逃げする。
- 闇市場での決済: 違法薬物、武器、偽造品などの取引に、匿名性の高い決済手段として利用される。
- テロ資金供与: 国境を越えてテロ組織に資金を供給する手段として悪用される。
通常の銀行システムであれば、KYC(Know Your Customer:顧客確認)やAML(Anti-Money Laundering:アンチ・マネーロンダリング)といった規制が厳格に適用され、不審な取引は監視・報告されます。しかし、規制の及ばない海外の取引所や分散型金融(DeFi)プラットフォームを利用されると、当局による追跡は極めて困難になります。
中国は、社会の安定を最重要視する国であり、犯罪活動の温床となりうる要素は徹底的に排除しようとします。仮想通貨がもたらす金融イノベーションの可能性よりも、それが社会の秩序を乱し、犯罪を助長するリスクのほうを重く見ているのです。 2021年の全面禁止に関する通知の中でも、「仮想通貨は、賭博、違法な資金調達、詐欺、ねずみ講、マネーロンダリングなどの違法・犯罪活動の温床となっている」と厳しく断じており、規制の正当性を強く主張しています。この姿勢は、中国の強力な国家統制と治安維持への強い意志を反映したものと言えるでしょう。
④ 国が管理するデジタル人民元を普及させるため
そして第四に、そしておそらく将来を見据えた上で最も戦略的な理由が、中国政府が国家主導で開発を進める中央銀行デジタル通貨(CBDC)、すなわち「デジタル人民元(e-CNY)」の普及を促進するためです。
デジタル人民元は、ビットコインのような非中央集権型の仮想通貨とは全く異なる概念のデジタル通貨です。その本質は、中国人民銀行が発行・管理する、現金(紙幣や硬貨)をデジタル化したものに他なりません。つまり、管理者不在のビットコインとは対照的に、デジタル人民元は国家による強力な中央集権的管理の下に置かれます。
中国政府がデジタル人民元の開発と普及を急ぐ目的は多岐にわたります。
- 金融活動の完全な可視化: 国民や企業のすべての決済データをリアルタイムで把握し、脱税や汚職、資本流出などをより効果的に監視する。
- 金融政策の精度向上: 景気刺激策として、特定の期間や用途に限定したデジタル通貨を国民に直接給付するなど、より的を絞った機動的な金融政策を実施できるようになる。
- 決済システムの効率化: 既存の銀行システムを介さず、低コストで迅速な決済を実現する。また、AlipayやWeChat Payといった民間の決済プラットフォームへの依存を低下させる。
- 国際的な影響力の拡大: 将来的には、国際貿易の決済にデジタル人民元を利用してもらうことで、米ドルが支配する既存の国際金融システム(SWIFTなど)への挑戦を目指す。
この壮大な国家プロジェクトを成功させる上で、ビットコインなどの民間の仮想通貨は、いわば「競合相手」であり、その存在は邪魔になります。もし、国民が管理者のいない仮想通貨の利便性やプライバシー(匿名性)に慣れてしまうと、政府が管理するデジタル人民元への移行がスムーズに進まない可能性があります。
したがって、中国政府は、まず民間の仮想通貨という選択肢を市場から完全に排除し、国民が利用できるデジタル通貨をデジタル人民元に一本化しようとしているのです。 仮想通貨に対する厳しい規制は、デジタル人民元が普及するための「地ならし」という側面を色濃く持っています。この観点から見ると、中国の仮想通貨禁止は単なるネガティブな規制ではなく、自国のデジタル通貨覇権を確立するための極めて戦略的な布石であると理解できます。
中国における仮想通貨規制の歴史
中国の仮想通貨に対する規制は、ある日突然始まったわけではありません。約10年以上にわたり、市場の状況や政府の思惑に応じて、段階的に強化されてきた歴史があります。その変遷を時系列で追うことで、中国政府の一貫した姿勢と、規制強化の背景にある意図をより深く理解できます。
| 年代 | 主な出来事 | 内容と目的 | 市場への影響 |
|---|---|---|---|
| 2013年 | 金融機関によるビットコイン取り扱い禁止 | 投機熱の抑制と金融リスクの防止を目的とし、金融機関の関与を禁止。ただし、個人の取引は容認。 | 一時的な価格下落。しかし、個人取引は継続し、市場は拡大を続けた。 |
| 2017年 | ICOの全面禁止と国内取引所の閉鎖 | ICOによる詐欺や違法な資金調達の横行を受け、ICOを全面禁止。大手国内取引所も閉鎖命令。 | 中国国内での公式な取引が停止。投資家は海外取引所やP2P取引へ移行。「チャイナショック」として価格が暴落。 |
| 2019年 | ブロックチェーン技術の国家戦略化 | 習近平国家主席がブロックチェーン技術の重要性を強調。仮想通貨は否定しつつ、基盤技術は推進する方針が明確化。 | 「幣鏈分離(通貨とチェーンの分離)」が鮮明に。ブロックチェーン関連企業への投資が活発化。 |
| 2021年 | マイニング禁止と仮想通貨関連サービスの全面禁止 | 環境問題、金融リスク、デジタル人民元推進などを理由に、マイニングと全ての仮想通貨関連サービスを禁止。規制の総仕上げ。 | 世界最大のマイニング大国が消滅。ハッシュレートが国外に分散し、ネットワークの非中央集権化が促進。価格も一時急落。 |
2013年:金融機関によるビットコインの取り扱いを禁止
中国における仮想通貨規制の最初の大きな動きは、2013年12月に遡ります。当時、ビットコインの価格が初めて1,000ドルを突破するなど、世界的に価格が高騰し、中国国内でも急速に投機熱が高まっていました。大手IT企業がビットコイン決済の導入を検討するなど、社会的な関心も急上昇していました。
この状況を問題視した中国人民銀行(中央銀行)は、5つの中央省庁と連名で「ビットコインに関するリスク防止についての通知」を発表しました。この通知の要点は以下の通りです。
- ビットコインは本当の意味での通貨ではないと定義し、法定通貨と同等の法的地位を持たないと明言。
- すべての金融機関および決済機関に対し、ビットコインに関連する業務(売買、決済、保険など)を行うことを禁止。
- 一方で、一般の個人が自己の責任において、インターネット上で「商品」としてビットコインを自由に売買することは容認。
この規制は、金融システム全体をビットコインの価格変動リスクから切り離すことを目的としていました。政府としては、投機的なバブルが金融機関を巻き込んで崩壊し、システミックリスクに発展することを最も警戒していたのです。
この通知の発表後、ビットコイン価格は一時的に急落しましたが、個人間の取引は依然として合法であったため、市場はすぐに落ち着きを取り戻しました。むしろ、この規制によって政府のスタンスが(限定的ながらも)明確になったことで、かえって市場の透明性が増したと捉える向きもありました。この時点では、まだ後のような全面禁止には程遠く、中国は依然として世界の仮想通貨市場の中心地であり続けました。
2017年:ICOの全面禁止と国内取引所の閉鎖
2013年の規制からしばらく安定期が続きましたが、2017年に市場の状況は一変します。この年、世界中でICO(Initial Coin Offering:新規仮想通貨公開)がブームとなりました。ICOは、企業やプロジェクトが独自のトークン(仮想通貨)を発行・販売することで、迅速かつ容易に資金を調達できる画期的な手法として注目を集めました。
しかし、その手軽さゆえに、ずさんな計画や詐欺的なプロジェクトが後を絶たず、多くの投資家が被害に遭うという問題が深刻化しました。中国でもICOによる資金調達額が急増し、金融秩序を乱す大きな要因として政府に認識されるようになります。
これを受け、2017年9月4日、中国人民銀行をはじめとする7つの規制当局は、「トークン発行による資金調達のリスク防止に関する公告」を発表。ICOを「本質的に未承認の違法な公開資金調達行為」と断定し、即時全面禁止を命じました。すでに完了したICOについても、調達した資金を投資家に返還するよう求めるなど、極めて厳しい措置を取りました。
さらに、この動きに追い打ちをかけるように、同月中旬には、当時中国最大手であったBTCC、Huobi、OKCoinといった国内の仮想通貨取引所に対して、事業を停止するよう口頭で指導。これにより、中国国内における人民元を介した公式な仮想通貨取引の道が、事実上すべて閉ざされることになりました。
この一連の措置は「チャイナショック」として世界中の市場を揺るがし、ビットコイン価格は再び暴落しました。多くの中国人投資家は、VPN(仮想プライベートネットワーク)を使って海外の取引所にアクセスしたり、WeChatなどのSNSを介したP2P(個人間)取引に移行したりすることで、取引を継続しようとしましたが、人民元との換金は以前より格段に困難かつリスキーになりました。この2017年の規制は、中国が仮想通貨市場から本格的に距離を置き始める決定的な転換点となったのです。
2019年:ブロックチェーン技術の推進を国家戦略として発表
仮想通貨取引に対して厳しい姿勢を示す一方で、中国政府はその基盤技術であるブロックチェーンに対しては、全く異なるアプローチを取ります。その方針が最も明確に示されたのが、2019年10月の出来事です。
習近平国家主席は、中国共産党中央政治局の集団学習会において、ブロックチェーン技術を「コア技術の自主的イノベーションにおける重要な突破口」と位置づけ、その発展を加速させるよう国家戦略として推進する旨を表明しました。
この発言は、中国全土に大きなインパクトを与えました。それまで仮想通貨のイメージと結びつけて語られがちだったブロックチェーンが、国家の最高指導者からお墨付きを得たことで、一気にポジティブな技術として認知されるようになったのです。この発言後、中国の株式市場ではブロックチェーン関連銘柄が軒並み急騰しました。
この出来事により、中国政府のスタンスが明確になりました。それは、「投機的で管理不可能な仮想通貨(幣)は禁止するが、その基盤となり、データの透明性や改ざん耐性を保証するブロックチェーン技術(鏈)は積極的に活用・推進する」という、いわゆる「幣鏈分離(通貨とチェーンの分離)」の原則です。
政府は、ブロックチェーン技術が金融、サプライチェーン管理、公共サービス、知的財産保護など、様々な分野でイノベーションをもたらし、経済のデジタル化を加速させる重要な鍵になると考えています。この方針に基づき、以降、中国では政府機関や大手IT企業(アリババ、テンセントなど)主導によるコンソーシアム型ブロックチェーン(許可された参加者のみがネットワークを構成するタイプ)の開発プロジェクトが数多く立ち上がりました。この動きは、後のデジタル人民元の開発にも繋がっていきます。
2021年:マイニングの禁止と仮想通貨関連サービスの全面禁止
2017年の取引所閉鎖後も、中国は世界の仮想通貨市場において依然として大きな影響力を持ち続けていました。その最大の要因が、ビットコインのマイニング(採掘)です。安価な電力を背景に、中国、特に内モンゴル自治区、新疆ウイグル自治区、四川省などは世界のマイニング能力(ハッシュレート)の50%以上を占める一大拠点となっていました。
しかし、2021年、中国政府はこの最後の砦にもメスを入れます。同年5月、劉鶴副首相が主宰する金融安定発展委員会で、ビットコインのマイニングと取引行為への断固たる取り締まり方針が示されました。これには複数の理由がありました。
- 環境への配慮: マイニングは膨大な電力を消費します。特に石炭火力発電に依存する地域でのマイニングは、中国が国際社会に公約したカーボンニュートラル(炭素中立)目標の達成を妨げる要因と見なされました。
- 金融リスクの根絶: マイニング事業が非合法な資金調達や投機活動と結びついているとされ、金融リスクの根源を断つ必要がありました。
- デジタル人民元への布石: 前述の通り、競合となりうる仮想通貨のエコシステムを完全に排除する狙いもありました。
この方針を受け、各地方政府は管轄内のマイニング事業者に対して即時操業停止を命令。これにより、中国国内での大規模なマイニング活動は事実上不可能となりました。
そして、この規制の総仕上げとして、同年9月24日、中国人民銀行などが「仮想通貨取引の投機リスクのさらなる防止と対処に関する通知」を発表。これにより、取引、情報仲介、デリバティブ、海外取引所によるサービス提供など、およそ考えられるすべての仮想通貨関連の商業活動が「違法な金融活動」として明確に禁止されました。
この2021年の一連の措置は、2013年から続いた規制の集大成であり、中国が仮想通貨エコシステムを国内から完全に排除するという強い意志を世界に示しました。これにより、中国の仮想通貨の歴史は、一つの大きな区切りを迎えることになったのです。
中国の仮想通貨規制が市場に与えた影響

かつて世界の仮想通貨市場で圧倒的な存在感を誇っていた中国。その巨大市場での取引やマイニングが段階的に、そして最終的に全面的に禁止されたことは、世界の仮想通貨市場に計り知れない影響を及ぼしました。その影響は、短期的な価格変動に留まらず、市場の構造そのものを大きく変える結果となりました。
ビットコイン価格の一時的な下落
中国の規制強化に関するニュースは、その発表のたびに、世界の仮想通貨市場、特にビットコインの価格に大きな影響を与えてきました。これは「チャイナFUD(Fear, Uncertainty, and Doubt:恐怖、不確実性、疑念)」とも呼ばれ、投資家心理を冷え込ませる主要な要因の一つでした。
- 2017年9月の「チャイナショック」:
ICOの全面禁止と国内主要取引所の閉鎖が発表された際、ビットコイン価格は数日のうちに約40%も急落しました。当時、世界のビットコイン取引の大部分が中国の取引所で行われていたため、その閉鎖は市場に巨大な衝撃を与えました。多くの投資家は、最大の市場が失われることへの恐怖から、パニック売りを誘発しました。 - 2021年5月〜9月の全面禁止:
マイニングの取り締まりが開始された2021年5月、ビットコイン価格は当時の最高値から50%以上も下落しました。その後、9月に仮想通貨関連サービスを全面的に禁止する通知が発表された際にも、市場は再び下落しました。世界最大のマイニング大国であり、潜在的な巨大市場でもある中国が、仮想通貨エコシステムから完全に離脱するというニュースは、市場の将来に対する悲観的な見方を広げました。
なぜ中国の規制がこれほど価格に影響を与えるのでしょうか。その理由は主に3つあります。
- 市場規模の大きさ: 規制強化前、中国は世界最大のトレーダー人口とマイナー(採掘者)を抱えていました。この巨大な需要と供給が一気に市場から消える(あるいは非公式な市場に潜る)ことは、需給バランスを大きく崩し、価格下落圧力となります。
- 投資家心理への影響: 「中国が仮想通貨を禁止した」というニュースは、仮想通貨に詳しくない一般の人々にも強いインパクトを与えます。これにより、仮想通貨全体の将来性に対する不安が煽られ、世界中の投資家がリスク回避のために資産を売却する動きにつながります。
- FUDの拡散: 仮想通貨市場は、ニュースや噂に非常に敏感です。特にネガティブな情報(FUD)はSNSなどを通じて瞬時に拡散され、連鎖的な売りを呼び起こしやすい特性があります。
しかし、重要なのは、これらの価格下落はあくまで「一時的」なものであったという点です。 歴史を振り返ると、市場は中国の規制というショックを乗り越え、そのたびにより力強く回復し、価格の最高値を更新してきました。これは、仮想通貨市場がもはや一国の規制だけでコントロールできる規模ではなくなり、グローバルな広がりと回復力(レジリエンス)を持つようになったことを示しています。中国の規制は短期的には大きな打撃となりますが、長期的には市場がその影響を織り込み、新たな均衡点を見つけてきたのです。
マイニング事業者の国外移転とハッシュレートの分散
中国の規制が市場構造に与えた最も大きく、かつ長期的な影響は、ビットコインのマイニング地図を根本的に塗り替えたことです。
まず、ハッシュレートという言葉を簡単に説明すると、これはビットコインのネットワーク全体で1秒間に行われる計算(ハッシュ計算)の回数を示す指標です。ハッシュレートが高いほど、ネットワークのセキュリティは強固になります。マイニングとは、この膨大な計算競争に参加し、最初に成功した者が新たなビットコインを報酬として得る行為です。
2021年の規制以前、中国は安価な電気代(特に水力発電が豊富な四川省や、石炭火力発電が安い内モンゴル・新疆ウイグル自治区)を武器に、世界のビットコインハッシュレートの50%から、一時は70%近くを占めるほどの「マイニング大国」でした。これは、ビットコインネットワークの安定性を中国一国に大きく依存している状態であり、地政学的なリスクとして懸念されていました。もし中国政府がその気になれば、国内のマイナーを支配下に置き、ネットワークに対して悪意のある攻撃(51%攻撃など)を仕掛けることも理論上は可能だったからです。
しかし、2021年のマイニング全面禁止令は、この状況を一変させました。中国国内で事業を続けられなくなったマイニング事業者(マイナー)たちは、機材を抱えて一斉に国外への「大脱出(Great Mining Migration)」を開始しました。彼らが新たな拠点として選んだのは、主に以下のような国々です。
- アメリカ合衆国: 特にテキサス州やジョージア州など、安価な電力(再生可能エネルギーを含む)が豊富で、仮想通貨に対して友好的な規制を持つ州に多くのマイナーが移転しました。結果として、アメリカは中国に代わり、世界最大のマイニング大国へと躍り出ました。(参照:Cambridge Centre for Alternative Finance)
- カザフスタン: 中国と国境を接し、安価な石炭火力発電を背景に多くのマイナーを受け入れました。しかし、急激な電力需要の増加が国内の電力網を圧迫し、大規模な停電を引き起こすなど、新たな問題も発生しました。
- ロシア: シベリア地域の安価な電力が魅力となり、移転先の一つとなりました。
- カナダ、マレーシアなど
このマイナーの国際的な大移動は、ビットコインネットワークにとって非常に重要な結果をもたらしました。それは、ハッシュレートの地理的な分散化です。
- ポジティブな影響(ネットワークの堅牢性向上):
それまで中国一国に集中していたハッシュレートが、北米、中央アジア、ヨーロッパなど世界中に分散しました。これにより、特定の一国の政府や電力事情によってネットワーク全体が大きな影響を受けるリスクが大幅に低減され、ビットコインの非中央集権性という理念が、より強固なものになりました。多くの専門家は、中国のマイニング禁止が、長期的にはビットコインネットワークをより健全でたくましいものにしたと評価しています。 - ネガティブな影響(新たな課題):
一方で、移転先の国々で新たな問題も生じています。カザフスタンのように電力インフラが脆弱な国では社会問題化したり、移転先の国でも将来的に規制が強化されるリスクがあったりと、マイナーは常に新たな課題に直面しています。
結論として、中国の規制は短期的には市場に混乱をもたらしましたが、結果的にビットコインネットワークの脆弱性であった「地理的集中リスク」を解消し、その非中央集権性と安全性を高めるという、皮肉な結果を生み出したのです。
中国の仮想通貨に関する今後の見通しと将来性
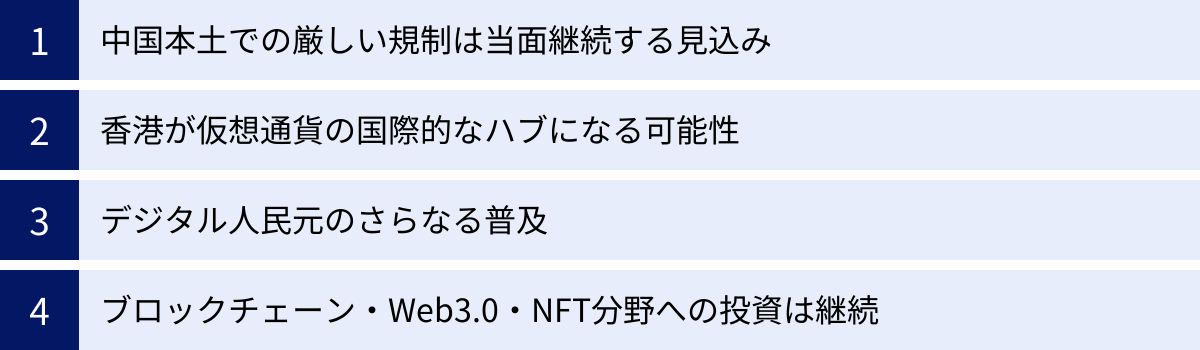
中国本土での厳しい規制、香港での活発化、そしてデジタル人民元の推進。これらの複雑な要素が絡み合う中、中国と仮想通貨の未来はどのようになっていくのでしょうか。現在の動向から、いくつかの重要な見通しを立てることができます。
中国本土での厳しい規制は当面継続する見込み
まず最も確実視されるのが、中国本土における仮想通貨への厳しい規制は、短中期的には緩和される可能性が極めて低いということです。その理由は、これまで述べてきた中国政府が仮想通貨を禁止する4つの根源的な動機が、今後も変わらないと考えられるからです。
- 資本流出の防止: 中国経済が安定成長を続ける限り、また国際情勢が不透明である限り、政府は資本のコントロールを緩めることは考えにくいでしょう。仮想通貨という抜け道は、引き続き厳しく塞がれるはずです。
- 金融システムの安定: 国家が管理できない投機的な資産を金融システムに組み込むリスクを、中国政府が許容するとは考えられません。金融の安定は、社会の安定に直結する最重要課題です。
- 犯罪行為の防止: マネーロンダリングなどへの悪用を防ぎ、社会秩序を維持するという名目は、規制を正当化する強力な理由であり続けます。
- デジタル人民元の推進: 国家プロジェクトであるデジタル人民元の普及を最優先する限り、競合相手となる民間の仮想通貨を容認することは、自己矛盾につながります。
これらの理由に加え、中国共産党による中央集権的な統治体制と、ビットコインに代表される非中央集権的な思想は、本質的に相容れません。したがって、現体制が続く限り、中国本土で再び仮想通貨取引所が合法化されたり、ビットコインが決済手段として認められたりする未来を想像するのは困難です。 投資家や事業者は、この現実を前提として戦略を立てる必要があります。
香港が仮想通貨の国際的なハブになる可能性
中国本土の扉が固く閉ざされる一方で、もう一つの扉が力強く開かれようとしています。それが香港です。「一国二制度」の下、香港は中国本土とは異なる規制の道を歩み、国際的な仮想通貨・Web3.0のハブとしての地位を確立しようとしています。
2023年の個人投資家への取引解禁や、2024年の現物ETFの承認は、その明確なシグナルです。香港政府は、シンガポールやドバイ、スイスといったライバル都市に対抗し、デジタルアセットという新たな成長分野で主導権を握りたいと考えています。
この香港の動きは、中国全体にとっていくつかの戦略的な意味合いを持つ可能性があります。
- 「実験区」としての役割: 中国政府は、管理の及ばない本土で仮想通貨を解禁するリスクを冒すことなく、香港という管理可能な「実験区」で、デジタルアセットが金融システムや経済にどのような影響を与えるかを観察できます。香港での成功や失敗の経験は、将来的に本土の規制を再考する際の貴重なデータとなり得ます。
- 国際社会との「窓口」: 本土の企業や資本が、完全にグローバルな仮想通貨市場から切り離されるのを防ぐための「窓口」の役割を果たす可能性があります。中国の技術者や投資家が、合法的な形で世界のWeb3.0エコシステムと関わるためのゲートウェイとして、香港の重要性は増していくでしょう。
- 中国資本の新たな投資先: 本土の投資家が直接海外の仮想通貨に投資することはできませんが、将来的に「ストックコネクト(滬港通・深港通)」のような仕組みを通じて、香港で上場された仮想通貨ETFなどに限定的に投資できるようになる可能性も、長期的には議論されるかもしれません。
ただし、楽観的な見方ばかりではありません。近年、香港国家安全維持法などにより、香港の自治に対する北京の影響力は強まっています。香港の仮想通貨政策が、いつまで本土の意向と独立して存在し続けられるのかという不確実性は、常に考慮しておくべきリスクです。しかし、当面の間は、香港が中国と世界の仮想通貨市場を繋ぐユニークで重要な役割を担っていくことは間違いないでしょう。
デジタル人民元のさらなる普及
仮想通貨の禁止と表裏一体で進むのが、デジタル人民元(e-CNY)の普及拡大です。 中国政府は、仮想通貨という選択肢を排除した上で、デジタル人民元の利用を強力に推進していくでしょう。
現在、デジタル人民元は、北京、上海、深圳など主要都市を含む多くの地域で大規模な実証実験が行われています。利用シーンも、当初の小売店での決済から、公共交通機関の運賃支払い、公共料金の納付、さらには一部の企業で給与の支払いにも利用されるなど、着実に拡大しています。
今後の展開として、以下の点が予測されます。
- 全国規模での展開: 現在の试点(試験運用)フェーズが完了すれば、全国民を対象とした本格的な導入が始まるでしょう。
- 利用シーンの多様化: 政府関連の支払いや補助金の給付など、公的な領域での利用が義務化されていく可能性があります。
- クロスボーダー決済への挑戦: 国内での普及がある程度進んだ次のステップとして、国際貿易の決済にデジタル人民元を利用する「mBridge」プロジェクトなどが推進されます。これは、米ドルを基軸とする現在の国際送金システム(SWIFT)への挑戦であり、人民元の国際的な地位向上を目指す壮大な戦略の一環です。
デジタル人民元の普及は、中国社会を大きく変える可能性を秘めています。 すべての取引が国家によって追跡可能になることによるプライバシーへの懸念や、社会信用システムとの連携による監視社会化のリスクも指摘されています。一方で、決済の効率化や金融包摂の促進といったメリットも期待されます。この国家主導のデジタル通貨の動向は、世界の金融システムの未来を占う上でも注目すべき重要なテーマです。
ブロックチェーン・Web3.0・NFT分野への投資は継続
最後に、仮想通貨は禁止されても、その根幹をなす技術への投資は止まらないという点を強調しておく必要があります。「幣鏈分離」の原則に基づき、中国は今後もブロックチェーン、Web3.0、そして中国独自の形に進化したNFT(非代替性トークン)分野への投資と開発を国策として継続していきます。
中国におけるブロックチェーンの活用は、金融、物流、行政サービス、知的財産管理など、実社会に根差した産業応用が中心です。特に、アリババグループのアントチェーンやテンセントのブロックチェーンなど、大手IT企業が主導するコンソーシアム型(許可型)ブロックチェーンが主流となっています。
また、NFTに関しても、中国市場は独特の発展を遂げています。仮想通貨による決済が禁止されているため、イーサリアムなどのパブリックブロックチェーン上で発行されるグローバルなNFTとは切り離されています。その代わり、「数字藏品(デジタルコレクティブル)」と呼ばれ、大手IT企業が運営するコンソーシアム型ブロックチェーン上で、人民元を使って売買されるものが主流です。これらは二次流通(転売)が厳しく制限されており、投機的な側面が抑えられ、あくまでアートや記念品としての「収集」が目的とされています。
このように、中国はグローバルなWeb3.0のトレンドとは一線を画しつつも、国家の管理下に置かれた「中国式Web3.0」とも呼べるエコシステムの構築を目指しています。この分野では、今後も政府の支援を受けた多くのプロジェクトが生まれ、独自のイノベーションが進んでいくことが予想されます。
中国の仮想通貨規制に関するよくある質問
中国の仮想通貨規制は複雑で、多くの人が疑問を持っています。ここでは、特によくある質問に対して、これまでの内容を基に分かりやすく回答します。
現在、中国人は仮想通貨を取引できますか?
結論から言うと、中国国内で、合法的に仮想通貨を取引することはできません。
2021年9月の中国人民銀行などによる通知により、仮想通貨に関連するあらゆる金融活動が「違法」と定められました。これには以下の行為が含まれます。
- 仮想通貨取引所を運営すること。
- 法定通貨(人民元)と仮想通貨を交換すること。
- 仮想通貨同士を交換すること。
- 個人として仮想通貨を売買すること。
- 海外の取引所が中国居住者にサービスを提供すること。
このため、かつて存在したHuobiやOKCoinのような中国系の取引所も、中国本土向けのサービスは完全に停止しています。
ただし、現実には一部の個人が、法律の網の目をかいくぐる形で取引を試みているケースも存在します。例えば、以下のような方法です。
- VPNの利用: VPN(仮想プライベートネットワーク)を使ってインターネット検閲を回避し、海外の仮想通貨取引所にアクセスする。
- P2P(個人間)取引: SNSや専用のプラットフォームを介して、個人間で直接売買する。
しかし、これらの方法は極めて高いリスクを伴います。まず、これらの行為自体が中国の法律に違反しており、発覚した場合には当局による処罰の対象となる可能性があります。 また、人民元との換金ルートも非常に限られており、非公式な両替商などを利用する過程で銀行口座が凍結されたり、資金を失ったりするリスクが常に付きまといます。さらに、相手の身元が不確かなP2P取引では、詐欺に遭う危険性も非常に高いです。
したがって、「取引できるか?」という問いに対しては、「物理的には可能かもしれないが、それは違法行為であり、極めて危険である」というのが正確な答えになります。
中国人が仮想通貨を保有することは違法ですか?
この質問に対する答えは、より複雑で、「グレーゾーン」と言えます。
現時点の中国の法律では、個人が資産として仮想通貨を「保有」すること自体を、明確に「違法」とする条文は存在しません。
過去には、仮想通貨の窃盗をめぐる民事裁判で、裁判所がビットコインを「仮想財産」として認め、所有者の財産権を保護すべきだという判断を下した事例があります。これは、個人がすでに所有している仮想通貨は、法的にその人の財産として扱われる余地があることを示唆しています。
しかし、この点を楽観視することはできません。重要なのは、以下の2つの現実です。
- 合法的な入手・換金手段がない: 保有が黙認されているとしても、中国国内で合法的に仮想通貨を新たに購入したり、保有する仮想通貨を売却して人民元に換えたりする手段がありません。つまり、資産としての流動性がなく、実質的に「使えない資産」となってしまいます。
- 法的な位置づけが不安定: 現在は保有が違法でなくても、将来的に政府の方針が変わり、保有自体が禁止される可能性は常にあります。また、保有する仮想通貨が何らかの犯罪に由来するものと疑われた場合、資産を没収されるリスクもあります。
まとめると、中国人が仮想通貨をただ持っているだけで直ちに逮捕される、ということにはなりませんが、その法的地位は非常に不安定です。 取引や換金ができない以上、実用的な意味はほとんどなく、常に法改正や資産凍結のリスクに晒されている状態であると理解すべきです。これは「合法」というよりは、単に「まだ明確に違法化されていない」だけの状態に近いと言えるでしょう。