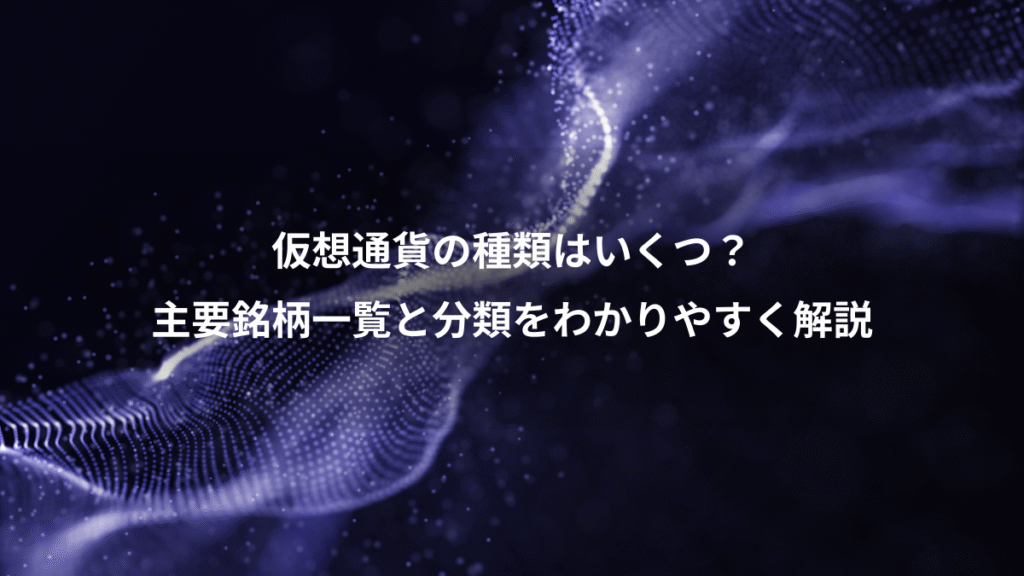仮想通貨(暗号資産)と聞いて、あなたは「ビットコイン」を思い浮かべるかもしれません。しかし、その世界はビットコインだけにとどまらず、数えきれないほどの種類の通貨が存在し、日々新しいプロジェクトが生まれています。2024年現在、その数は数万種類以上ともいわれ、それぞれが異なる技術、目的、そして可能性を秘めています。
この記事では、仮想通貨の広大で複雑な世界を解き明かすための羅針盤となることを目指します。まず、「仮想通貨とは何か」という基本的な定義から、その驚くべき種類の数、そしてそれらを理解するための分類方法までを丁寧に解説します。
さらに、時価総額ランキングで常に上位に位置する主要な15銘柄をピックアップし、それぞれの特徴や将来性を詳しくご紹介。また、「草コイン」と呼ばれるハイリスク・ハイリターンな銘柄の世界や、数ある仮想通貨の中から将来有望なものを見つけ出すための具体的な選び方についても深掘りしていきます。
仮想通貨投資をこれから始めたいと考えている初心者の方に向けて、口座開設から購入までの3ステップや、おすすめの国内取引所も具体的に解説します。この記事を最後まで読めば、仮想通貨の種類の全体像を掴み、自分に合った銘柄を見つけ、最初の一歩を踏み出すための知識と自信が得られるはずです。
目次
仮想通貨(暗号資産)とは

仮想通貨、または法律上の名称である「暗号資産」とは、インターネット上で取引される、特定の国家による価値の保証を持たないデジタルな資産のことです。この革新的な技術を理解するためには、その根幹をなす「ブロックチェーン」という技術と、従来の金融システムとの違いを把握することが不可欠です。
まず、なぜ「仮想通貨」と「暗号資産」という2つの呼び名が存在するのかについて触れておきましょう。もともと「仮想通貨」という呼称が一般的でしたが、2020年5月1日に施行された資金決済法の改正により、法令上は「暗号資産」という名称に統一されました。これは、「通貨」という言葉が、日本円や米ドルのような法定通貨との混同を招く恐れがあるためです。しかし、一般的には依然として「仮想通貨」という言葉も広く使われています。本記事では、読者の皆様の理解を助けるため、両方の名称を併記することがあります。
仮想通貨の最大の特徴は、「ブロックチェーン」と呼ばれる分散型台帳技術に基づいている点です。従来の銀行システムを想像してみてください。取引の記録は、銀行という中央の管理者が持つ巨大なデータベース(台帳)に一元的に記録・管理されています。これに対し、ブロックチェーンは、取引の記録(ブロック)を鎖(チェーン)のようにつなぎ、その情報をネットワークに参加する多数のコンピューター(ノード)で共有し、分散して管理します。
この仕組みには、いくつかの画期的な利点があります。
- 改ざんへの耐性(非改ざん性): 取引データは暗号化され、複数のブロックに連なって記録されます。もし誰かが一つのブロックの情報を改ざんしようとしても、それ以降のすべてのブロックの情報を整合性を保ちながら書き換える必要があり、さらにネットワーク上の多数のコンピューターの合意を得なければなりません。これは計算上、事実上不可能とされており、極めて高いセキュリティを実現しています。
- 透明性と可用性: ネットワークの参加者は、基本的に同じ取引台帳のコピーを共有しています。そのため、誰でも(プライバシーは保護された形で)取引の履歴を確認でき、透明性が確保されています。また、特定のサーバーがダウンしても、他の多数のコンピューターが稼働している限りシステム全体が停止することはありません。これを「ゼロダウンタイム」や「高い可用性」と呼びます。
- 非中央集権性(分散型): 特定の国や企業、銀行のような中央管理者が存在しません。ネットワーク参加者全員でシステムを維持・管理するため、一人の管理者の意向で取引が停止されたり、資産が凍結されたりするリスクがありません。このP2P(Peer-to-Peer)ネットワークによる運営が、仮想通貨の最も革新的な側面の一つです。
では、国や銀行が価値を保証していない仮想通貨に、なぜ価値が生まれるのでしょうか。その価値の源泉は多岐にわたります。
- 需要と供給: 最も基本的な要因は、買いたい人と売りたい人のバランスです。多くの人がその仮想通貨を欲しがれば価格は上がり、売りたがれば下がります。
- 技術的な優位性・実用性: その仮想通貨が持つ技術が、特定の課題(例えば、国際送金の速度や手数料)を解決できる場合、その実用性が価値の裏付けとなります。
- コミュニティの支持: プロジェクトを支持し、開発や普及に貢献するコミュニティの熱量も、価値を支える重要な要素です。
- 希少性: ビットコインのように、発行上限枚数がプログラムによって定められている場合、その希少性が金(ゴールド)のように価値の保存手段としての役割を期待させます。
これらの特性から、仮想通貨は従来の金融システムにはないメリットを提供します。例えば、銀行を介さない個人間の直接送金(P2P送金)により、特に国境を越える国際送金において、手数料を大幅に削減し、着金までの時間を劇的に短縮できます。銀行の営業時間に関わらず、24時間365日、世界中のどこへでも送金が可能です。
一方で、デメリットや注意点も存在します。最も顕著なのは価格変動(ボラティリティ)の大きさです。仮想通貨はまだ新しい市場であり、法規制の動向や著名人の発言、技術的なニュースなど、様々な要因で価格が短期間に大きく上下します。また、デジタル資産であるため、取引所のハッキングや自身の管理ミスによるパスワードの紛失などで、資産を失うリスクもあります。法規制も各国で整備が進められている段階であり、将来的な規制強化が市場に影響を与える可能性も念頭に置く必要があります。
総じて、仮想通貨(暗号資産)とは、ブロックチェーン技術を基盤とした、非中央集権的でグローバルな新しい形の資産であり、単なる投機対象としてだけでなく、金融や社会のあり方を変える可能性を秘めた技術革新であると理解することが重要です。
仮想通貨の種類は全部でいくつある?
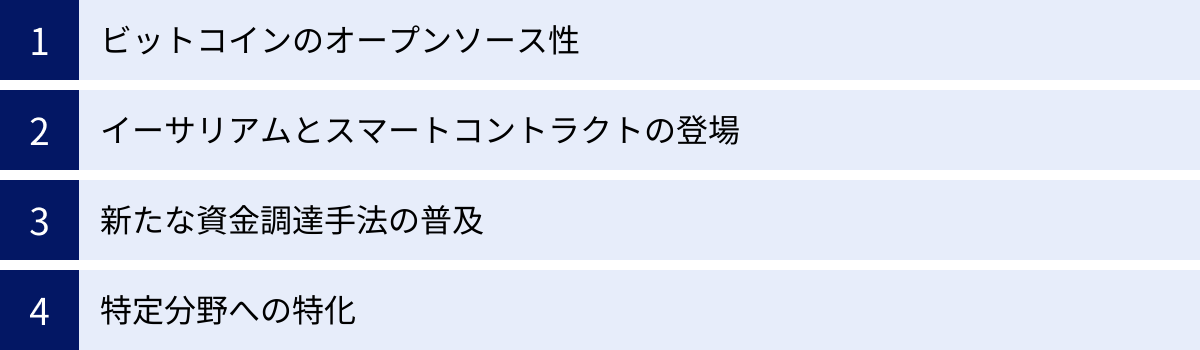
仮想通貨の世界に足を踏み入れた多くの人が最初に抱く疑問の一つが、「一体、何種類の仮想通貨が存在するのか?」ということでしょう。結論から言うと、その正確な数を把握することは極めて困難であり、その数は今この瞬間も増え続けています。
世界中の仮想通貨の価格や時価総額などのデータを集約している主要なウェブサイト、例えばCoinMarketCapやCoinGeckoを参照すると、その膨大さを垣間見ることができます。2024年6月時点で、CoinMarketCapには240万種類以上、CoinGeckoには1万5千種類以上の仮想通貨がリストアップされています。この数字の違いは、各サイトがどの仮想通貨をリストに掲載するかの基準が異なるためです。特にCoinMarketCapは、分散型取引所(DEX)で取引される非常にマイナーなトークンも自動的にリストアップする傾向があるため、数が膨大になっています。いずれにせよ、少なくとも1万種類を超える独自の仮想通貨プロジェクトが存在し、その数は日々増加していると考えるのが現実的です。
参照:CoinMarketCap、CoinGecko 公式サイト
では、なぜこれほどまでに多くの仮想通貨が次々と生まれるのでしょうか。その背景には、いくつかの重要な技術的・経済的な要因があります。
- ビットコインのオープンソース性: 2009年に登場した最初の仮想通貨であるビットコインは、その設計図であるソースコードが公開されています(オープンソース)。これにより、誰でもそのコードをコピーし、改変して新しい仮想通貨(いわゆる「フォークコイン」)を作ることが可能になりました。ライトコイン(LTC)やビットコインキャッシュ(BCH)などは、この代表例です。
- イーサリアムとスマートコントラクトの登場: 2015年にイーサリアム(ETH)が登場したことで、仮想通貨の世界は劇的に変化しました。イーサリアムは、単なる通貨機能だけでなく、「スマートコントラクト」という、あらかじめ設定されたルールに従って契約を自動的に実行するプログラムをブロックチェーン上で動かすことを可能にしました。これにより、専門的なプログラミング知識がなくても、「ERC-20」などの統一規格に則って、誰でも比較的簡単に独自のトークン(仮想通貨)を発行できるようになったのです。これが、仮想通貨の種類が爆発的に増加した最大の要因と言えるでしょう。
- 新たな資金調達手法の普及: スマートコントラクトの普及は、新しい資金調達の方法を生み出しました。プロジェクトが独自のトークンを発行し、それを投資家に販売して開発資金を集めるICO(Initial Coin Offering)が一時期ブームになりました。その後、取引所がプロジェクトを審査してトークン販売を行うIEO(Initial Exchange Offering)や、分散型取引所(DEX)で販売を行うIDO(Initial DEX Offering)など、様々な手法が登場し、スタートアップ企業が容易にグローバルな市場から資金を調達できる環境が整いました。これが新しいプロジェクトと仮想通貨の誕生を後押ししています。
- 特定分野への特化: ブロックチェーン技術の応用範囲が広がるにつれて、様々な分野に特化した仮想通貨が登場しています。例えば、従来の金融をブロックチェーン上で再現しようとするDeFi(分散型金融)、デジタルアートやゲーム内アイテムの所有権を証明するNFT(非代替性トークン)、ゲームをプレイすることで収益を得られるGameFi(ゲームファイ)、現実世界のデータをブロックチェーンに取り込むオラクルなど、特定の目的を達成するために設計された専門的な仮想通貨が数多く存在します。
しかし、この「種類の多さ」には注意が必要です。数万という仮想通貨の中には、明確なビジョンや技術的裏付けを持たないプロジェクトや、残念ながら投資家から資金を騙し取ることを目的とした詐欺的なプロジェクト(スキャムコイン)も数多く含まれています。特に、過剰な宣伝文句で投資を煽り、開発者が資金を持ち逃げする「ラグプル」と呼ばれる手口は後を絶ちません。
したがって、仮想通貨の種類が多いことは、技術革新の活発さを示すポジティブな側面と、投資家が慎重になるべきリスクの側面を併せ持っています。初心者がこの膨大な数の中から価値あるプロジェクトを見つけ出すのは容易ではありません。だからこそ、次のセクションで解説する「分類方法」を理解し、市場の全体像を把握することが、賢明な判断を下すための第一歩となるのです。
仮想通貨の基本的な分類方法
数万種類も存在する仮想通貨を一つ一つ見ていくのは不可能です。そこで、市場の全体像を理解するために、いくつかの基本的な分類方法を知っておくことが非常に役立ちます。最も大きな分類は「ビットコイン」とそれ以外の「アルトコイン」に分ける方法です。さらに、アルトコインはその目的や機能によって、いくつかのカテゴリーに細分化できます。
ビットコインとアルトコイン
仮想通貨の世界は、まずこの2つの大きなグループに分けることから始まります。
ビットコイン(BTC)
ビットコイン(BTC)は、2009年にサトシ・ナカモトと名乗る謎の人物(またはグループ)によって生み出された、世界で最初の仮想通貨です。すべての仮想通貨の原点であり、その存在なくして現在の市場は語れません。
ビットコインの主な目的は、特定の国や銀行といった中央管理者を介さずに、個人間で価値を直接やり取りできるP2P(ピアツーピア)の電子キャッシュシステムを実現することでした。その最大の特徴は、発行上限枚数が2,100万枚とプログラムによって厳密に定められている点です。この希少性から、インフレーションによって価値が下落しやすい法定通貨とは対照的に、その価値を長期的に保存する手段として注目されるようになりました。この性質から、しばしば「デジタルゴールド」と形容されます。
現在では、決済手段としてよりも、この価値の保存手段としての側面が強く認識されており、仮想通貨市場全体の健全性を示す指標としても機能しています。ビットコインの価格動向は、他の多くの仮想通貨の価格にも大きな影響を与えます。
アルトコイン
アルトコインとは、「Alternative Coin(代替のコイン)」の略で、ビットコイン以外のすべての仮想通貨の総称です。イーサリアム、リップル、ソラナなど、ビットコイン以外の有名な通貨はすべてアルトコインに含まれます。
アルトコインが作られる目的は様々ですが、主に以下のような動機が挙げられます。
- ビットコインの課題解決: ビットコインには、取引の処理速度が遅い(スケーラビリティ問題)、取引手数料が高騰することがある、といった課題があります。これらの課題を解決するために、より高速で安価な決済を目指すアルトコインが数多く開発されました(例:ライトコイン)。
- 新たな機能の追加: ビットコインが主に価値の移転に特化しているのに対し、アルトコインは独自の機能を追加して差別化を図っています。その代表例が、契約の自動執行を可能にする「スマートコントラクト」機能です。
- 特定の用途への特化: 金融(DeFi)、ゲーム(GameFi)、アート(NFT)、サプライチェーン管理など、特定の産業や用途に特化して設計されたアルトコインも多数存在します。
アルトコインはビットコインに比べて価格変動が激しい傾向にありますが、その分、革新的な技術やユースケースを持つプロジェクトが成功すれば、大きなリターンをもたらす可能性も秘めています。
アルトコインの主な種類
アルトコインは、その目的や機能によってさらに細かく分類できます。ここでは、代表的な6つのカテゴリーを紹介します。
| カテゴリー | 主な目的・特徴 | 代表的な銘柄 |
|---|---|---|
| プラットフォーム型 | dApps(分散型アプリケーション)やスマートコントラクトを構築・実行するための基盤(OS)となる。 | イーサリアム (ETH), ソラナ (SOL), カルダノ (ADA) |
| 決済・送金特化型 | より速く、より安く、効率的な決済や送金を実現することを目的とする。 | リップル (XRP), ライトコイン (LTC), ビットコインキャッシュ (BCH) |
| ステーブルコイン | 法定通貨(米ドルなど)や他の資産に価格が連動するように設計され、価格の安定を目指す。 | テザー (USDT), USDコイン (USDC), ダイ (DAI) |
| DeFi関連銘柄 | 銀行などを介さずに金融サービス(貸付、取引など)を提供する分散型金融プロジェクトに関連する。 | ユニスワップ (UNI), アーベ (AAVE), メーカー (MKR) |
| NFT・GameFi関連銘柄 | NFTマーケットプレイスや、遊んで稼ぐ(Play-to-Earn)ブロックチェーンゲーム内で使用される。 | アクシ―インフィニティ (AXS), ザ・サンドボックス (SAND), ディセントラランド (MANA) |
| ミームコイン | インターネット上のジョーク(ミーム)を元に作られ、明確な実用性よりもコミュニティの熱量で価値が決まる。 | ドージコイン (DOGE), 柴犬コイン (SHIB) |
プラットフォーム型
プラットフォーム型コインは、他の開発者がそのブロックチェーン上で独自のアプリケーション(dApps)やトークンを作成するための基盤(インフラ)を提供するプロジェクトのネイティブトークンです。コンピューターのOS(WindowsやmacOS)に例えられることが多く、ブロックチェーン生態系の土台となる非常に重要な役割を担っています。このカテゴリーのコインは、dAppsを動かす際の取引手数料(ガス代)の支払いや、ネットワークのセキュリティを維持するためのステーキングなどに使用されます。代表格はイーサリアム(ETH)であり、その他にもソラナ(SOL)、カルダノ(ADA)、アバランチ(AVAX)などが「イーサリアムキラー」としてシェアを争っています。
決済・送金に特化したコイン
このカテゴリーのコインは、ビットコインが抱えるスケーラビリティ問題(取引の遅延や手数料の高騰)を解決し、日常的な支払いや国際送金などを、より速く、安く、効率的に行うことを主な目的としています。リップル(XRP)は特に金融機関との連携による国際送金の革新を目指しており、ライトコイン(LTC)はビットコインよりも高速な決済ネットワークを提供することを目指して開発されました。
ステーブルコイン
ステーブルコインは、その名の通り価格の安定(Stable)を目指して設計された仮想通貨です。その価値を米ドルなどの法定通貨や、金などのコモディティに1対1などで連動(ペッグ)させます。ビットコインや多くのアルトコインが激しい価格変動に晒されるのに対し、ステーブルコインは価値の尺度や交換媒体、安全な価値の退避先として機能します。DeFi(分散型金融)の世界では、取引の基軸通貨として広く利用されています。テザー(USDT)やUSDコイン(USDC)のように、発行額と同等のドル資産を準備金として保有する「法定通貨担保型」が主流です。
DeFi(分散型金融)関連銘柄
DeFi(Decentralized Finance)とは、ブロックチェーン上で銀行や証券会社といった仲介者なしに金融サービスを提供する仕組みのことです。貸し借り(レンディング)、資産の交換(DEX)、保険など、様々なサービスが存在します。DeFi関連銘柄は、これらのDeFiプロトコル(サービス)の運営に関わるトークンで、主にガバナンストークンとしての役割を持ちます。トークンの保有者は、プロトコルの手数料率の変更や新しい機能の追加など、運営に関する意思決定に投票で参加する権利を得られます。ユニスワップ(UNI)やアーベ(AAVE)がその代表例です。
NFT・GameFi関連銘柄
NFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)は、デジタルデータに唯一無二の価値を与え、所有権を証明できる技術です。このNFTを活用したデジタルアートの売買や、ブロックチェーンゲームが近年大きな注目を集めています。NFT・GameFi関連銘柄は、これらのNFTマーケットプレイスや、GameFi(ゲームをプレイすることで仮想通貨を稼げる仕組み)プロジェクト内で利用される通貨です。ゲーム内アイテムの購入や、キャラクターの育成、プロジェクトの運営方針を決めるガバナンス投票などに使われます。アクシーインフィニティ(AXS)やザ・サンドボックス(SAND)などが有名です。
ミームコイン
ミームコインは、インターネット上のジョークや流行(ミーム)を元に作られた仮想通貨です。もともとは特定の技術的な目的や実用性を持たずに、面白半分で生み出されたものがほとんどです。その価値は、プロジェクトのビジョンや技術力よりも、コミュニティの熱狂的な支持や、著名人の発言、SNSでの話題性によって大きく左右される傾向があります。代表格であるドージコイン(DOGE)は、日本の柴犬のミームから生まれました。非常に高い価格変動リスクを伴う一方で、コミュニティの力によって驚異的な価格上昇を見せることもある、極めて投機的な側面の強いカテゴリーです。
【2024年最新】主要な仮想通貨の種類15選
ここでは、2024年現在の仮想通貨市場において、時価総額や知名度、影響力の観点から特に重要とされる主要な15銘柄をピックアップしてご紹介します。それぞれのコインがどのような目的を持ち、どのような特徴を持っているのかを理解することで、仮想通貨市場のトレンドや技術の方向性が見えてくるでしょう。
(※時価総額ランキングは2024年6月時点の情報を参考にしていますが、常に変動する点にご留意ください。)
① ビットコイン(BTC)
- 概要: 2009年に誕生した世界初の仮想通貨であり、すべての仮想通貨の原点。中央管理者を必要としないP2Pの電子決済システムとして考案されました。
- 主な特徴: 発行上限が2,100万枚と定められており、その希少性から「デジタルゴールド」として価値の保存手段と見なされています。時価総額は常に1位であり、その価格動向は仮想通貨市場全体に大きな影響を与えます。最も分散化され、堅牢なネットワークを持つと評価されています。
- 時価総額ランキング: 1位
② イーサリアム(ETH)
- 概要: 2015年に公開された、スマートコントラクト機能を実装したプラットフォーム型の仮想通貨。
- 主な特徴: dApps(分散型アプリケーション)やNFT、DeFiの基盤として圧倒的なシェアを誇り、巨大なエコシステムを形成しています。開発者コミュニティが非常に活発で、数多くのプロジェクトがイーサリアム上で構築されています。コンセンサスアルゴリズムをPoWからPoS(プルーフ・オブ・ステーク)へ移行した「The Merge」により、エネルギー消費量を大幅に削減しました。
- 時価総額ランキング: 2位
③ リップル(XRP)
- 概要: 米国のリップル社が開発を主導する、国際送金に特化した仮想通貨。
- 主な特徴: 数秒で完了する高速な決済速度と、非常に低い送金手数料が最大の特徴です。世界中の金融機関と提携し、従来の国際送金システム(SWIFTなど)が抱える時間とコストの問題を解決することを目指しています。ブリッジ通貨としての役割が期待されています。
- 時価総額ランキング: 7位前後
④ ソラナ(SOL)
- 概要: イーサリアムの強力な対抗馬と目される、高性能なプラットフォーム型ブロックチェーン。
- 主な特徴: 「Proof of History (PoH)」という独自のコンセンサスアルゴリズムにより、1秒間に数万件のトランザクションを処理できる圧倒的なスケーラビリティを実現しています。取引手数料も非常に安価なため、DeFiやNFT、GameFi分野で急速に採用が拡大しています。
- 時価総額ランキング: 5位前後
⑤ カルダノ(ADA)
- 概要: イーサリアムの共同創設者の一人であるチャールズ・ホスキンソン氏が中心となって開発を進めるプラットフォーム型ブロックチェーン。
- 主な特徴: 科学的な哲学と学術的な査読(ピアレビュー)に基づいた、厳密で慎重な開発アプローチが特徴です。高いセキュリティと持続可能性、相互運用性を目標に掲げており、堅牢なブロックチェーンの構築を目指しています。PoSの一種である「Ouroboros(ウロボロス)」を採用しています。
- 時価総額ランキング: 10位前後
⑥ ドージコイン(DOGE)
- 概要: 2013年に日本の柴犬をモチーフにしたインターネットミーム(ジョーク)から生まれた、ミームコインの代表格。
- 主な特徴: 当初は明確な目的を持たないコインでしたが、熱狂的なコミュニティと、イーロン・マスク氏などの著名人の支持によって世界的な知名度を獲得しました。実用性よりも話題性やコミュニティの力によって価格が大きく変動する点が特徴です。一部では決済手段としても導入されています。
- 時価総額ランキング: 8位前後
⑦ ポルカドット(DOT)
- 概要: イーサリアムの共同創設者であるギャビン・ウッド氏が考案した、異なるブロックチェーン同士を繋ぐためのプロジェクト。
- 主な特徴: ビットコインやイーサリアムなど、独立したブロックチェーン間の相互運用性(インターオペラビリティ)を実現することを目指しています。「リレーチェーン」という中心的なチェーンに、「パラチェーン」という複数の独自のブロックチェーンを接続する構造で、高いスケーラビリティとセキュリティを両立させます。
- 時価総額ランキング: 15位前後
⑧ アバランチ(AVAX)
- 概要: DeFiやカスタムブロックチェーンの展開に最適化された、高速なプラットフォーム型ブロックチェーン。
- 主な特徴: 「サブネット」と呼ばれる独自のブロックチェーンを誰でも作成できるアーキテクチャが特徴です。これにより、特定のアプリケーション専用のチェーンを構築でき、ネットワーク全体の負荷を分散して高い処理能力を維持します。トランザクションの最終確定が1秒未満と非常に高速です。
- 時価総額ランキング: 12位前後
⑨ チェーンリンク(LINK)
- 概要: ブロックチェーン(オンチェーン)と現実世界(オフチェーン)のデータを安全に接続する「分散型オラクルネットワーク」を提供するプロジェクト。
- 主な特徴: スマートコントラクトは、それ自体では外部のデータ(例:株価、天気、スポーツの結果)を取得できません。チェーンリンクは、この外部データを信頼性の高い形でブロックチェーン上に提供するという、極めて重要な役割を担います。多くのDeFiプロジェクトで利用されています。
- 時価総額ランキング: 15位前後
⑩ ライトコイン(LTC)
- 概要: 2011年に元Googleのエンジニアであるチャーリー・リー氏によって開発された、ビットコインから派生した仮想通貨。
- 主な特徴: ビットコインが「金」ならばライトコインは「銀」と位置付けられています。ビットコインよりもブロックの生成時間が4分の1(約2.5分)と短く、日常的な少額決済において、より高速で安価な取引を実現することを目指しています。
- 時価総額ランキング: 20位前後
⑪ ビットコインキャッシュ(BCH)
- 概要: 2017年にビットコインからハードフォーク(分裂)して誕生した仮想通貨。
- 主な特徴: ビットコインのスケーラビリティ問題を解決するため、ブロックサイズの上限を拡大し、より多くの取引を一度に処理できるように設計されました。サトシ・ナカモトの論文にある「P2P電子キャッシュシステム」としての役割、つまり日常的な決済手段としての利用を重視しています。
- 時価総額ランキング: 15位前後
⑫ 柴犬コイン(SHIB)
- 概要: 「ドージコインキラー」を自称して2020年に登場した、日本の柴犬をモチーフにしたミームコイン。
- 主な特徴: 当初はミームコインとしてスタートしましたが、その後、独自の分散型取引所(ShibaSwap)やNFT、メタバース構想など、多岐にわたるエコシステムの構築を進めています。強力なコミュニティ「ShibArmy」に支えられており、その動向が価格に大きな影響を与えます。
- 時価総額ランキング: 11位前後
⑬ ユニスワップ(UNI)
- 概要: イーサリアム上で稼働する世界最大級のDEX(分散型取引所)であるUniswapのガバナンストークン。
- 主な特徴: Uniswapは、特定の管理者を介さずにユーザー同士が直接トークンを交換できるサービスです。UNIトークンの保有者は、Uniswapの将来的な開発方針や手数料の分配など、運営に関する重要事項の投票に参加する権利を持ちます。DeFiの象徴的なプロジェクトの一つです。
- 時価総額ランキング: 20位前後
⑭ コスモス(ATOM)
- 概要: ポルカドットと同様に、異なるブロックチェーン間の相互運用を目指すプロジェクト。「ブロックチェーンのインターネット」を構想しています。
- 主な特徴: 「Cosmos SDK」という開発キットを提供し、開発者が比較的容易に独自のブロックチェーンを構築できる環境を整えています。これらの独立したブロックチェーンは、「IBC(Inter-Blockchain Communication)」というプロトコルを通じて相互に通信・連携できます。
- 時価総額ランキング: 25位前後
⑮ ニアプロトコル(NEAR)
- 概要: 開発者とユーザーの双方にとっての使いやすさ(ユーザビリティ)を重視した、プラットフォーム型ブロックチェーン。
- 主な特徴: 「シャーディング」という技術を用いてネットワークを分割処理することで、高いスケーラビリティを実現しています。また、一般的なプログラミング言語で開発が可能であったり、人間が読めるアカウント名(例:yourname.near)を使えたりと、ブロックチェーンの普及を妨げる障壁を取り除くことに注力しています。
- 時価総額ランキング: 20位前後
一攫千金も?将来性が期待される「草コイン」とは
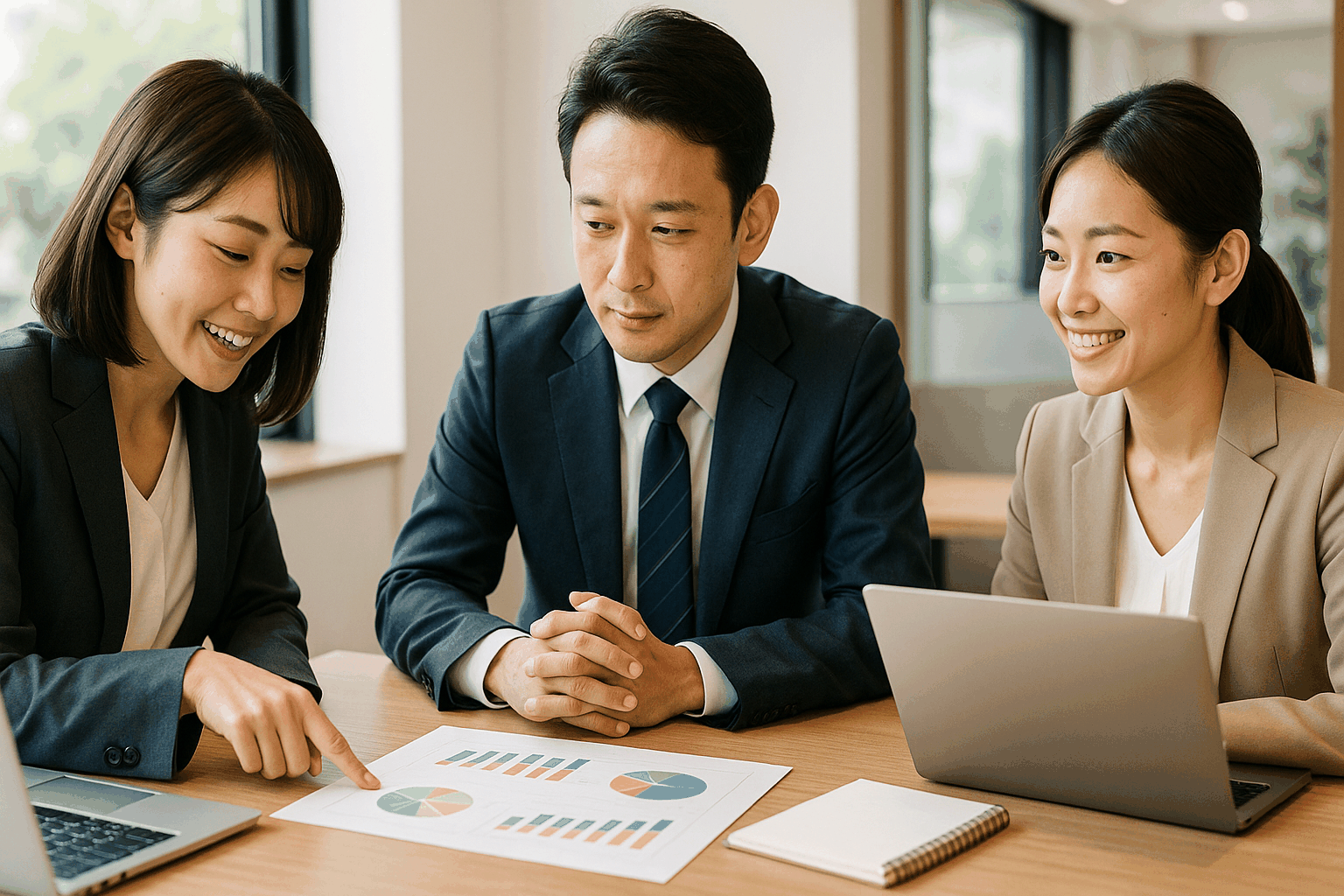
仮想通貨の世界には、ビットコインやイーサリアムのような有名銘柄だけでなく、まだほとんど知られていない無数のコインが存在します。その中でも、時価総額が非常に小さく、価格も安いものを俗に「草コイン」と呼びます。これらは一攫千金の夢を抱かせる一方で、非常に高いリスクを伴う諸刃の剣です。ここでは草コインの定義、リスクとリターン、そしてその探し方について解説します。
草コインの定義
草コインに明確な学術的・法的な定義はありません。これは、仮想通貨コミュニティから自然発生的に生まれたスラング(俗語)です。一般的には、以下のような特徴を持つ仮想通貨を指すことが多いです。
- 時価総額が非常に小さい: 数億円〜数十億円程度、あるいはそれ以下。CoinMarketCapなどのランキングでは数百位以下、時には数千位以下に位置します。
- 価格が極端に安い: 1枚あたりの価格が1円未満、中には0.001円以下といった銘柄も珍しくありません。
- 知名度が低い: ほとんどの人がその名前を聞いたことがなく、情報も限られています。
- 流動性が低い: 取引量が少なく、大手の中央集権型取引所(CEX)には上場しておらず、主に分散型取引所(DEX)で取引されています。
なぜ「草」と呼ばれるのかについては諸説ありますが、「(まだ誰も見つけていない)草原に生えているコイン」「(価値が低すぎて)笑ってしまう(ネットスラングの”草”)」といった意味合いで使われることが多いようです。
草コインのリスクとリターン
草コイン投資の最大の魅力は、その爆発的なリターンへの期待です。時価総額が小さいため、わずかな資金が流入するだけで価格が急騰しやすく、価値が10倍(テンバガー)、100倍、時には1,000倍以上になる可能性もゼロではありません。過去には、無名だった草コインが大手取引所に上場したり、有名人が言及したりしたことをきっかけに、一夜にして億り人(資産が1億円を超えた投資家)を生み出した事例も存在します。
しかし、その輝かしいリターンの裏には、比較にならないほど大きなリスクが潜んでいます。草コイン投資は、「宝くじ」や「ギャンブル」に近いと認識しておく必要があります。
- 価値がゼロになるリスク: プロジェクトが失敗したり、開発が頓挫したりして、コインの価値が完全にゼロになることは日常茶飯事です。
- 詐欺(スキャム)のリスク: 投資家を騙す目的で作られたプロジェクトも多数存在します。特に、開発チームが投資家から集めた資金を持ち逃げする「ラグプル(Rug Pull)」は、DEXで取引される草コインに頻発する手口です。
- 流動性リスク: 取引量が少ないため、いざ売却しようと思っても買い手がつかず、売れない可能性があります。また、少額の取引でも価格が大きく変動(スリッページ)してしまい、意図した価格で売買できないこともあります。
- ハッキングリスク: 新興プロジェクトはセキュリティが脆弱な場合が多く、ハッキングの標的になりやすい傾向があります。
- 情報の非対称性: プロジェクトに関する情報が少なく、真偽の判断が非常に困難です。意図的に誇大な情報や虚偽の情報を流して価格を吊り上げようとする動き(パンプ・アンド・ダンプ)も横行しています。
草コインへの投資は、失っても生活に影響のない余剰資金の、さらにごく一部で行うべきです。大きなリターンを夢見る前に、投資した資金がすべて無くなる可能性の方がはるかに高いことを強く認識してください。
草コインの探し方
高いリスクを承知の上で、将来性のある草コインを探したいという場合、以下のような方法が一般的です。ただし、どの方法を用いるにしても、DYOR(Do Your Own Research – 自分で調べる)という鉄則を絶対に忘れないでください。他人の情報を鵜呑みにせず、必ず自分自身でプロジェクトを精査することが重要です。
- データアグリゲーターサイトを活用する:
- CoinMarketCapやCoinGeckoには、「新規上場(Recently Added)」や「急上昇(Top Gainers)」といったセクションがあります。ここをチェックすることで、新しく生まれたコインや、直近で注目を集めているコインを見つけることができます。時価総額や取引量でフィルタリングし、低位のコインをリストアップするのも有効です。
- 分散型取引所(DEX)を探索する:
- 多くの草コインは、まずUniswap(イーサリアム系)やPancakeSwap(BNBチェーン系)といったDEXに上場します。これらのDEXでは、誰でも自由にトークンペアを作成して流動性を提供できるため、無数の草コインが取引されています。DEXToolsやDexScreenerといった分析ツールを使えば、DEX上のリアルタイムな取引状況や新規ペアの情報を追跡できます。
- SNSやコミュニティをリサーチする:
- X (旧Twitter)は、仮想通貨の最新情報が最も早く流れるプラットフォームの一つです。影響力のあるインフルエンサーや、特定のプロジェクトの動向を追うことで、初期の情報を得られる可能性があります。
- TelegramやDiscordでは、各プロジェクトが公式のコミュニティチャンネルを運営しています。コミュニティに参加し、開発者の発言やロードマップの進捗、コミュニティの熱量を肌で感じることは、プロジェクトの将来性を見極める上で非常に重要です。
- ローンチパッド(Launchpads)をチェックする:
- ローンチパッドは、新しい仮想通貨プロジェクトが資金調達(IDO)を行うためのプラットフォームです。有望なプロジェクトを初期段階で発掘し、上場前の価格でトークンを購入できる可能性があります。ただし、参加するにはプラットフォーム独自のトークンを保有する必要があるなど、一定の条件が課せられることがほとんどです。
草コインを探す際は、ホワイトペーパーを読み込み、開発チームの経歴や過去の実績を調べ、コミュニティが健全に機能しているかなど、多角的な視点から徹底的にリサーチすることが、詐欺を避け、将来の宝を発見するための唯一の道となります。
将来性が期待できる仮想通貨の選び方
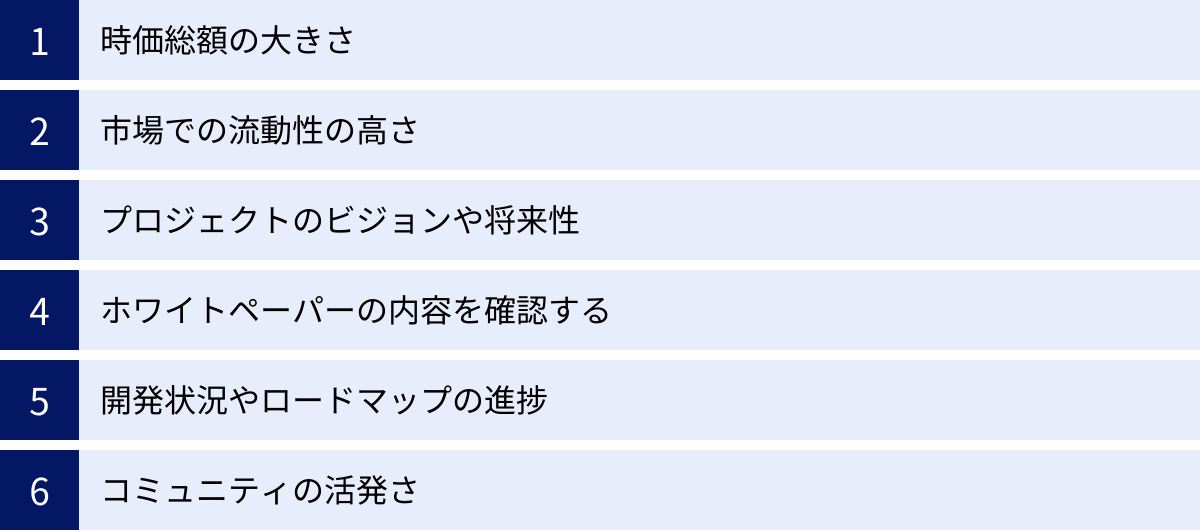
数万種類もの仮想通貨の中から、将来的に価値が上がる可能性を秘めた銘柄を見つけ出すことは、多くの投資家にとっての目標です。しかし、運や勘だけで選ぶのは非常に危険です。ここでは、初心者でも実践できる、将来性が期待できる仮想通貨を選ぶための具体的な6つのチェックポイントを解説します。これらの要素を総合的に評価することで、より根拠のある投資判断が可能になります。
時価総額の大きさ
時価総額は、その仮想通貨の現在の市場における評価と信頼性を測る最も基本的な指標です。計算式は「時価総額 = 現在の価格 × 発行済み(流通)枚数」で表されます。
時価総額が大きいということは、それだけ多くの資金が投じられ、多くの投資家から支持されていることを意味します。一般的に、時価総額が大きい銘柄(例:ビットコイン、イーサリアム)は、価格の安定性が比較的高く、情報も豊富で、市場からの信頼も厚い傾向にあります。そのため、仮想通貨投資の初心者は、まず時価総額ランキング上位の銘柄から検討を始めるのが最も安全なアプローチと言えるでしょう。
一方で、時価総額が小さい銘柄(草コインなど)は、将来的に価格が何十倍にもなる可能性を秘めていますが、その分リスクも非常に高くなります。自分のリスク許容度に合わせて、どの時価総額レベルの銘柄に投資するかを考えることが重要です。
市場での流動性の高さ
流動性とは、その仮想通貨がどれだけ活発に取引されているかを示す指標であり、主に取引高(ボリューム)で測られます。流動性が高い銘柄は、市場に多くの買い手と売り手が存在するため、以下のようなメリットがあります。
- 取引のしやすさ: 自分が「買いたい」と思った時にすぐに買え、「売りたい」と思った時にすぐに売ることができます。
- 価格の安定性: 大口の取引があったとしても、価格への影響が比較的小さく抑えられます。
- スリッページの抑制: 注文価格と実際に約定した価格の差(スリッページ)が発生しにくくなります。
逆に、流動性が低い銘柄は、少しの売買で価格が乱高下しやすく、最悪の場合、売りたい時に買い手が見つからず売却できない「塩漬け」状態になるリスクがあります。CoinMarketCapやCoinGeckoなどで、興味のある銘柄の日々の取引高を確認する習慣をつけましょう。
プロジェクトのビジョンや将来性
テクニカルな指標だけでなく、その仮想通貨が「どのような社会課題や技術的課題を解決しようとしているのか」というプロジェクトの根本的なビジョンを理解することが、長期的な投資において最も重要です。
- 課題解決能力: そのプロジェクトは、既存のシステム(金融、物流、エンターテイメントなど)の非効率性を改善するものか? ブロックチェーン技術でなければ実現できない、独自の価値を提供しているか?
- 実用性(ユースケース): 理論上は素晴らしくても、実際に企業や個人に使われる見込みはあるか? すでに提携している企業や、具体的な導入事例はあるか?
- 独自性と競合優位性: 同じような目的を持つ他のプロジェクトと比較して、技術的、戦略的にどのような優位性があるか?
これらの問いに自分なりの答えを見つけることで、単なる投機ではなく、プロジェクトの成長を応援する「投資」としての視点を持つことができます。
ホワイトペーパーの内容を確認する
ホワイトペーパーは、その仮想通貨プロジェクトの「設計図」や「事業計画書」に相当する重要な文書です。プロジェクトの創設者が、その目的、技術的な仕組み、解決しようとする課題、将来のロードマップ、そしてトークンの経済圏(トークノミクス)などについて詳細に記述しています。
専門的な内容が多く、すべてを完璧に理解するのは難しいかもしれません。しかし、少なくとも以下の点を確認するために、一度は目を通すべきです。
- プロジェクトが目指すゴールは明確か?
- そのゴールを達成するための技術的なアプローチは論理的か?
- ロードマップは具体的で、現実的なスケジュールが示されているか?
- トークンの発行枚数、配布計画、用途(トークノミクス)は、プロジェクトの持続的な成長に貢献するように設計されているか?
ホワイトペーパーが存在しない、あるいは内容が抽象的で具体性に欠けるプロジェクトは、非常に危険な兆候と捉えるべきです。
開発状況やロードマップの進捗
壮大なビジョンや立派なホワイトペーパーを掲げていても、開発が実際に進んでいなければ意味がありません。プロジェクトの開発がアクティブであるかを確認することは、その将来性を見極める上で不可欠です。
- GitHubの活動: 多くのオープンソースプロジェクトは、GitHubというプラットフォームでソースコードを管理しています。開発者のコミット(コードの更新)履歴を見ることで、開発が活発に行われているかを確認できます。
- 公式ブログやSNSでの発表: プロジェクトチームが公式ブログやX (旧Twitter)などで、ロードマップの進捗状況や、テストネットの公開、新機能の実装などを定期的に報告しているかを確認しましょう。約束した計画通りに開発が進んでいるプロジェクトは信頼性が高いと言えます。
開発が長期間にわたって停滞しているプロジェクトは、将来性が低いと判断できる有力な材料になります。
コミュニティの活発さ
非中央集権的な性質を持つ仮想通貨プロジェクトにとって、それを支えるコミュニティの存在は生命線です。活発で健全なコミュニティは、以下のような点でプロジェクトの成功に大きく貢献します。
- 情報の拡散と新規ユーザーの獲得: コミュニティメンバーが自発的にプロジェクトの魅力を広めてくれます。
- フィードバックと改善: ユーザーからのフィードバックが、プロジェクトの改善に繋がります。
- ネットワークの分散化とセキュリティ: 多くの人々がノードを運営したり、ステーキングに参加したりすることで、ネットワークの安定性と安全性が向上します。
X (旧Twitter)のフォロワー数やエンゲージメント率、DiscordやTelegramの参加者数と議論の質などをチェックして、コミュニティがどれだけ熱量を持ち、建設的な活動を行っているかを確認しましょう。
初心者でも簡単!仮想通貨の始め方・買い方の3ステップ
仮想通貨の世界に興味を持ったものの、「何から始めればいいのか分からない」と感じる方も多いでしょう。しかし、心配は無用です。現在、日本国内のサービスを利用すれば、初心者でも驚くほど簡単に、そして安全に仮想通貨の取引を始めることができます。ここでは、口座開設から購入までの流れを、分かりやすい3つのステップに分けて解説します。
① 仮想通貨取引所で口座を開設する
仮想通貨を購入するためには、まず専用の財布であり取引所でもある「仮想通貨取引所」に自分の口座を開設する必要があります。日本円で仮想通貨を売買する場合、金融庁に暗号資産交換業者として登録されている国内の取引所を利用するのが最も安全で確実です。
【口座開設に必要なもの】
一般的に、以下の3点があればスムーズに手続きを進められます。
- メールアドレス: 登録や各種通知の受け取りに使用します。
- 本人確認書類: 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、顔写真付きの身分証明書。
- 銀行口座: 仮想通貨を購入するための日本円の入金や、利益を出金する際に使用する、自分名義の銀行口座。
【口座開設の基本的な流れ】
ほとんどの取引所で、以下の手順で口座を開設できます。
- 公式サイトにアクセスし、メールアドレスを登録: 利用したい取引所の公式サイトへ行き、メールアドレスとパスワードを設定します。登録したアドレスに届く確認メールのリンクをクリックして、基本情報の入力に進みます。
- 基本情報(氏名、住所など)の入力: 画面の指示に従い、氏名、住所、生年月日、職業、投資経験などの必要事項を入力します。
- 本人確認手続き: 次に、本人確認を行います。以前は書類を郵送する方法が主流でしたが、現在では「スマホでかんたん本人確認」(e-KYC)が一般的です。スマートフォンのカメラで本人確認書類と自分の顔を撮影してアップロードするだけで、オンライン上で手続きが完結します。この方法なら、最短で即日〜翌営業日には審査が完了します。
- 審査と口座開設完了: 取引所側で入力情報と提出書類の審査が行われます。審査に通過すると、口座開設完了の通知がメールなどで届き、取引を開始できるようになります。
② 口座に日本円を入金する
口座が無事に開設されたら、次に仮想通貨を購入するための資金(日本円)をその口座に入金します。主な入金方法は以下の通りで、取引所によって対応している方法や手数料が異なります。
| 入金方法 | メリット | デメリット・注意点 |
|---|---|---|
| 銀行振込 | ほとんどの取引所で対応。一度に大きな金額を入金できる。 | 銀行の振込手数料が自己負担になる場合が多い。銀行の営業時間外だと、入金の反映が翌営業日になることがある。 |
| クイック入金 | 提携しているネットバンクから24時間365日ほぼリアルタイムで入金可能。手数料が無料の取引所が多い。 | 入金した資産の移動が一定期間制限されることがある。取引所ごとに提携金融機関が異なる。 |
| コンビニ入金 | 全国の提携コンビニの端末やレジで簡単に入金できる。 | 1回あたりの入金上限額が比較的低い。所定の手数料がかかる場合がある。 |
自分のライフスタイルや利用している銀行に合わせて、最適な入金方法を選びましょう。初心者のうちは、まず失っても問題のない少額の資金から始めることを強くお勧めします。
③ 購入したい仮想通貨を選ぶ
日本円の入金が口座に反映されたら、いよいよ仮想通貨を購入します。取引所のアプリやウェブサイトにログインし、購入画面に進みましょう。仮想通貨の購入方法には、主に「販売所」と「取引所」の2つの形式があります。
- 販売所形式:
- 相手: 仮想通貨取引所
- 特徴: 提示された価格で、簡単・確実に売買できるのが最大のメリットです。操作画面がシンプルで分かりやすいため、初心者に適しています。
- 注意点: 買値と売値の差である「スプレッド」が実質的な手数料となり、次に説明する取引所形式に比べて割高になる傾向があります。
- 取引所形式:
- 相手: 他のユーザー
- 特徴: ユーザー同士が「板」と呼ばれる掲示板で、希望の価格と数量を提示して売買します。手数料が販売所に比べて非常に安いのがメリットです。
- 注意点: 操作がやや複雑で、希望の価格で注文が成立しない(約定しない)可能性もあります。
【購入の具体的な手順(販売所の場合)】
- 取引所のメニューから「販売所」を選択します。
- 購入したい仮想通貨の銘柄(例:ビットコイン)を選びます。
- 「購入」ボタンをタップ(クリック)します。
- 購入したい金額(例:10,000円分)または数量(例:0.001 BTC)を入力します。
- 内容を確認し、購入を確定するボタンを押せば、取引は完了です。
これで、あなたの資産の一部として仮想通貨がポートフォリオに加わります。最初のうちは、操作が簡単な「販売所」で少額から購入し、取引に慣れてきたらコストの安い「取引所」形式に挑戦してみるのが良いでしょう。
仮想通貨の購入におすすめの国内取引所3選
日本国内で仮想通貨取引を始めるにあたり、どの取引所を選ぶかは非常に重要です。ここでは、金融庁の認可を受けており、初心者にも人気が高く、それぞれに異なる強みを持つ3つの主要な取引所を厳選してご紹介します。各取引所の特徴を比較し、ご自身の投資スタイルに合った場所を見つける参考にしてください。
| 項目 | Coincheck(コインチェック) | DMM Bitcoin | GMOコイン |
|---|---|---|---|
| 取扱銘柄数(現物) | 29種類 | 38種類 | 26種類 |
| 取引形式 | 販売所・取引所 | 販売所・BitMatch | 販売所・取引所 |
| 各種手数料 | 入出金手数料は有料、取引所手数料は一部無料 | 入出金・送金手数料が無料(※BitMatch取引手数料などは除く) | 入出金・送金手数料が無料 |
| 最低取引金額 | 販売所:500円相当額、取引所:0.005BTC以上など | 0.0001 BTCなど | 0.00001 BTCなど |
| 特徴 | ダウンロード数No.1の使いやすいアプリ、NFTマーケットプレイス | レバレッジ取引の銘柄数が国内最多、手数料の安さ | オリコン顧客満足度調査で高評価、総合力の高さ |
| 公式サイト情報 | 参照:コインチェック株式会社 公式サイト | 参照:株式会社DMM Bitcoin 公式サイト | 参照:GMOコイン株式会社 公式サイト |
| (注:取扱銘柄数や各種情報は2024年6月時点のものです。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。) |
① Coincheck(コインチェック)
Coincheckは、特に仮想通貨取引が初めての方に絶大な人気を誇る取引所です。その最大の理由は、スマートフォンアプリの圧倒的な使いやすさにあります。シンプルで直感的なデザインのインターフェースは、誰でも迷うことなく操作できるように設計されており、「仮想通貨アプリ、ダウンロード数No.1」の実績がその支持の高さを物語っています。(※対象:国内の暗号資産取引アプリ、期間:2019年〜2023年、データ協力:App Tweak)
500円という少額から仮想通貨を購入できるため、お試しで始めてみたいというニーズにもぴったりです。また、国内では珍しい「Coincheck NFT」というNFTマーケットプレイスを運営しており、イーサリアムだけでなくCoincheckで取り扱っている仮想通貨で直接NFTを売買できる点も大きな特徴です。仮想通貨投資だけでなく、NFTの世界にも興味がある方には最適な選択肢となるでしょう。
② DMM Bitcoin
DMM.comグループが運営するDMM Bitcoinは、特に手数料の安さとレバレッジ取引に強みを持つ取引所です。最大の魅力は、日本円のクイック入金・出金手数料や、仮想通貨の送金手数料が無料である点です。取引コストをできるだけ抑えたいと考えるユーザーにとっては、非常に大きなメリットとなります。
(※一部、BitMatch取引手数料などの例外はあります。)
また、現物取引だけでなく、レバレッジ取引の取扱銘柄数が国内最多クラスであることも特筆すべき点です。少ない資金で大きなリターンを狙うアクティブなトレードを志向するユーザーから高い支持を得ています。DMM独自の注文方法である「BitMatch」を利用すれば、販売所形式でありながらスプレッドを抑えた取引が可能になるなど、中級者以上にとっても満足度の高いサービスを提供しています。
③ GMOコイン
GMOインターネットグループが運営するGMOコインは、総合力が高く、幅広いニーズに対応できる優良な取引所です。オリコン顧客満足度調査の「暗号資産取引所 現物取引」において、2年連続で総合No.1を獲得している実績(※2023年・2024年)が、その信頼性とサービスの質の高さを証明しています。
DMM Bitcoinと同様に日本円の入出金手数料や仮想通貨の預入・送付手数料が無料であることに加え、現物取引の取扱銘柄数が26種類と国内トップクラスの豊富さを誇ります。主要銘柄はもちろん、アルトコインの取引にも力を入れたい方に適しています。さらに、仮想通貨を貸し出して金利を得る「貸暗号資産」や、保有しているだけで報酬が得られる「ステーキング」など、売買以外のサービスも充実しており、長期的な資産運用を考えているユーザーにもおすすめです。
仮想通貨の種類に関するよくある質問
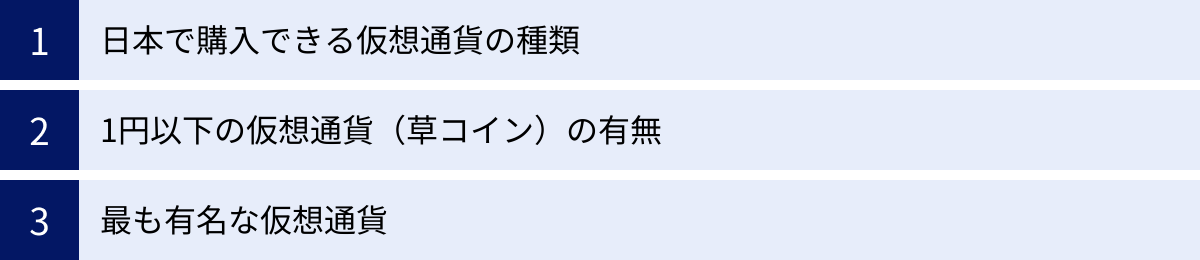
仮想通貨の種類について学ぶ中で、多くの人が抱く共通の疑問があります。ここでは、特に頻繁に寄せられる3つの質問に、分かりやすくお答えします。
日本で買える仮想通貨は何種類くらいありますか?
世界には数万種類の仮想通貨が存在しますが、日本の金融庁に登録された暗号資産交換業者(取引所)で購入できる仮想通貨の種類は、それに比べると限定的です。これは、日本の規制当局が投資家保護を重視し、各取引所が新しい仮想通貨を取り扱う際には厳格な審査を行っているためです。この審査を通過した、いわば「ホワイトリスト」に掲載された銘柄のみが国内で取引可能となります。
一般社団法人日本暗号資産取引業協会(JVCEA)のデータを参照すると、2024年5月末時点で、国内の全取引所でのべ106種類の暗号資産が取り扱われています。ただし、これは全取引所での合計数であり、一つの取引所ですべての銘柄が買えるわけではありません。各取引所は独自の基準で取扱銘柄を選定しているため、A取引所では買えるがB取引所では買えない、ということが普通です。例えば、Coincheckでは29種類、DMM Bitcoinでは38種類、GMOコインでは26種類(2024年6月時点)と、取引所ごとにラインナップは異なります。自分が購入したい特定の銘柄がある場合は、それを取り扱っている取引所を選ぶ必要があります。
参照:一般社団法人日本暗号資産取引業協会(JVCEA) 暗号資産種類別取り扱い状況
1円以下の仮想通貨(草コイン)はありますか?
はい、あります。 1枚あたりの価格が1円に満たない仮想通貨は「草コイン」や「ペニー株」ならぬ「ペニークリプト」などと呼ばれ、数多く存在します。この記事でも紹介したミームコインの代表格であるドージコイン(DOGE)や柴犬コイン(SHIB)も、かつては1円以下の価格帯で取引されていました。
国内の取引所でも、1円以下で購入できる銘柄は存在します。しかし、ここで非常に重要な注意点があります。それは、「価格が安い ≠ 割安」ではないということです。仮想通貨の価値を正しく評価するためには、1枚あたりの価格だけでなく、「時価総額(=価格 × 発行枚数)」を見る必要があります。例えば、価格が0.1円でも発行枚数が1兆枚のコインと、価格が100円で発行枚数が100万枚のコインでは、前者の時価総額(1000億円)の方がはるかに大きくなります。
1円以下のコインは少額から大量に購入できるため、価格が少し上昇しただけで大きな利益が出るように感じられるかもしれませんが、その分、プロジェクト自体の信頼性が低かったり、価格がゼロに近くなったりするリスクも極めて高いことを忘れてはなりません。
最も有名な仮想通貨は何ですか?
これは間違いなく、ビットコイン(BTC)です。
ビットコインは、世界で最初に誕生した仮想通貨であり、その知名度、歴史、時価総額、メディアでの報道量など、あらゆる面で他の仮想通貨を圧倒しています。仮想通貨という言葉を知っている人のほとんどが、同時にビットコインの名前も知っていると言っても過言ではありません。
その理由はいくつかあります。
- 歴史と先行者利益: 2009年から存在する最も歴史の長い仮想通貨であり、「仮想通貨=ビットコイン」というイメージを確立しました。
- 圧倒的な時価総額: 常に時価総額ランキング1位に君臨しており、市場全体の価値の大部分を占めています。
- 市場の指標: ビットコインの価格動向は、アルトコイン市場全体に大きな影響を与えるベンチマークとして機能しています。
- 価値の保存手段: 発行上限が定められていることから「デジタルゴールド」と呼ばれ、機関投資家などからも資産の一部として見なされるようになっています。
イーサリアムもdAppsのプラットフォームとして非常に有名ですが、一般的な知名度や市場における象徴的な意味合いにおいては、依然としてビットコインが最も有名な仮想通貨であると言えるでしょう。
まとめ
本記事では、仮想通貨の広大な世界を探求するために、その種類や分類、選び方から具体的な始め方までを包括的に解説してきました。最後に、この記事の重要なポイントを振り返りましょう。
- 仮想通貨の種類は数万以上: 2024年現在、仮想通貨の種類は数万以上存在し、その数は日々増え続けています。この背景には、イーサリアムの登場によるトークン発行の容易化や、DeFi、NFTといった新分野の発展があります。
- 基本は「ビットコイン」と「アルトコイン」: すべての仮想通貨は、最初の仮想通貨である「ビットコイン」と、それ以外の「アルトコイン」に大別されます。この基本的な分類を理解することが、市場全体を把握する第一歩です。
- アルトコインは目的別に多様な種類が存在: アルトコインは、dAppsの基盤となる「プラットフォーム型」、高速・低コストな決済を目指す「決済・送金特化型」、価格の安定を目指す「ステーブルコイン」、分散型金融サービスに関連する「DeFi関連銘柄」、そしてジョークから生まれた「ミームコイン」など、その目的や機能によって細かく分類されます。
- 銘柄選びは多角的な視点が重要: 将来性が期待できる仮想通貨を選ぶためには、時価総額や流動性といった市場データだけでなく、プロジェクトが何を解決しようとしているのか(ビジョン)、その計画書であるホワイトペーパーの内容、開発は実際に進んでいるか(進捗)、そしてコミュニティは活発かといった、より本質的な要素を自分自身で調査(DYOR)する姿勢が不可欠です。
- 初心者は国内取引所で少額から: 仮想通貨取引を始めるのは、決して難しくありません。金融庁に認可された国内の仮想通貨取引所で口座を開設し、まずは失っても生活に影響のない少額の資金から始めてみましょう。Coincheck、DMM Bitcoin、GMOコインなど、それぞれに特徴のある取引所の中から、自分のスタイルに合った場所を選ぶことが大切です。
仮想通貨の世界は、技術の進歩が非常に速く、市場の状況も刻一刻と変化します。しかし、その根底にあるブロックチェーンという技術は、金融のみならず、社会の様々な分野に変革をもたらす大きな可能性を秘めています。この記事が、あなたが仮想通貨という新しい資産クラスへの理解を深め、自信を持ってその第一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。常に最新の情報を学び続ける好奇心を持ち、賢明な判断でこのエキサイティングな世界に関わっていきましょう。