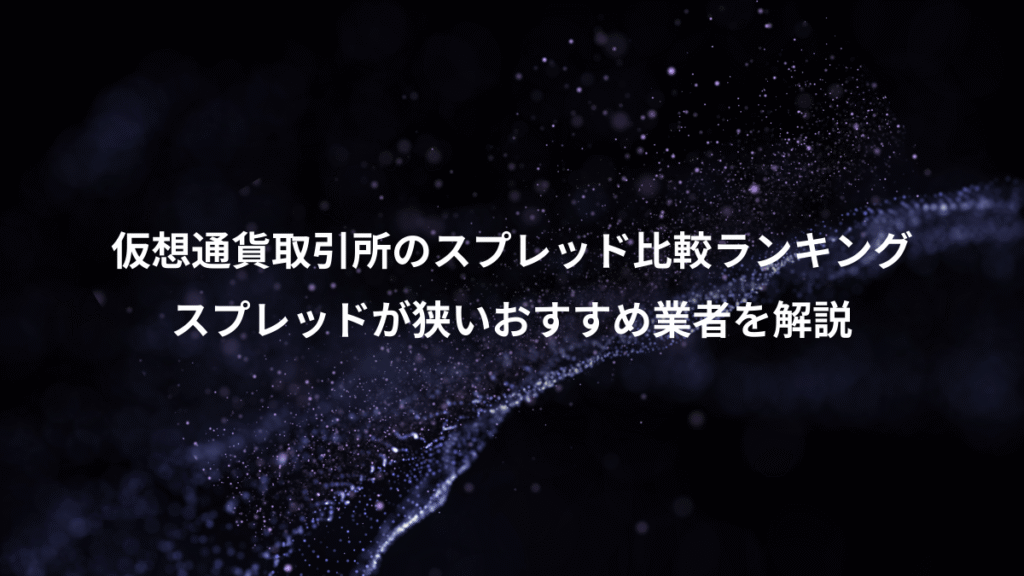仮想通貨(暗号資産)取引を始めるにあたり、多くの人が手数料の安さに注目しますが、実はそれと同じくらい、あるいはそれ以上に重要なのが「スプレッド」です。スプレッドは、仮想通貨を「買うときの価格」と「売るときの価格」の差額であり、実質的な取引コストとして利益に直結します。
特に、短期的な売買を繰り返すトレーダーにとって、スプレッドの広さは収益を圧迫する大きな要因となります。逆に、スプレッドが狭い取引所を選ぶことは、取引のたびに発生するコストを最小限に抑え、より有利な条件で資産運用を行うための第一歩と言えるでしょう。
しかし、スプレッドは常に変動しており、どの取引所が本当に「狭い」のかを判断するのは簡単ではありません。また、スプレッドの仕組みや、なぜ広くなったり狭くなったりするのかを理解しないまま取引を始めると、思わぬ損失につながる可能性もあります。
この記事では、仮想通貨取引におけるスプレッドの基本から、コストを抑えるための具体的なコツまでを網羅的に解説します。さらに、数ある国内の仮想通貨取引所の中から、スプレッドが狭いと評判のおすすめ業者を7社厳選し、それぞれの特徴を徹底比較します。
この記事を最後まで読めば、あなたに最適な取引所を見つけ、賢くコストを管理しながら仮想通貨取引をスタートできるようになるでしょう。
目次
スプレッドが狭い仮想通貨取引所おすすめランキング7選
ここでは、数ある国内の仮想通貨取引所の中から、特にスプレッドが狭いことで定評のあるおすすめの業者を7社紹介します。各社の特徴や手数料、取り扱い銘柄などを総合的に比較し、自分に合った取引所選びの参考にしてください。
① GMOコイン
GMOコインは、東証プライム上場企業であるGMOインターネットグループが運営する仮想通貨取引所です。金融サービスのノウハウを活かした堅牢なセキュリティと、コストパフォーマンスの高さが大きな魅力です。
■ スプレッドと手数料
GMOコインの最大の特徴は、「販売所」と「取引所(現物・レバレッジ)」の両方を提供しており、特にレバレッジ取引におけるスプレッドの狭さには定評があります。販売所のスプレッドは他の取引所と同様に広めに設定されていますが、取引所形式を利用することでコストを大幅に抑えることが可能です。
さらに、日本円の即時入金手数料や出金手数料、仮想通貨の送金(預入・送付)手数料が無料である点も特筆すべきポイントです。取引コストだけでなく、資金管理にかかる費用も最小限に抑えられるため、総合的なコストパフォーマンスが非常に高いと言えます。(参照:GMOコイン公式サイト)
■ 取引形式と取り扱い銘柄
GMOコインは、初心者でも簡単に売買できる「販売所」、ユーザー間で直接取引を行う「取引所(現物)」、そして少ない資金で大きな取引が可能な「取引所(レバレッジ)」を提供しています。特に取引所(現物)では、ビットコイン(BTC)だけでなく、イーサリアム(ETH)やリップル(XRP)など複数の人気アルトコインを扱っており、板取引に慣れたい中級者以上のユーザーにも適しています。
取り扱い銘柄数も国内トップクラスであり、主要なコインから注目度の高いアルトコインまで幅広く取引できる環境が整っています。
■ その他の特徴
GMOコインは、取引以外にも「つみたて暗号資産」や「ステーキング」、「貸暗号資産」といったサービスが充実しています。特にステーキングサービスは、対象の仮想通貨を保有しているだけで報酬が得られる仕組みであり、長期的な資産形成を目指すユーザーから人気を集めています。
また、高性能な取引ツールやスマホアプリも提供されており、初心者から上級者まで、あらゆるレベルのトレーダーが満足できる取引環境を提供しています。
■ まとめ:GMOコインはこんな人におすすめ
- 取引コストを徹底的に抑えたい人
- 取引所形式でアルトコインを売買したい人
- レバレッジ取引をメインに考えている人
- ステーキングや貸暗号資産など、長期的な運用も視野に入れている人
② DMM Bitcoin
DMM Bitcoinは、DMM.comグループが運営する仮想通貨取引所です。特にレバレッジ取引に力を入れており、豊富なアルトコインをレバレッジ取引できる点で他の取引所と一線を画しています。
■ スプレッドと手数料
DMM Bitcoinは、取引手数料や日本円の入出金手数料、仮想通貨の送金手数料が無料となっているのが大きな特徴です。(※BitMatch取引手数料を除く)。そのため、取引コストは実質的にスプレッドのみとなります。
スプレッドは、同社独自の注文方法である「BitMatch注文」を利用することで、通常のスプレッドよりも狭くなる可能性があります。BitMatch注文とは、DMM Bitcoinが提示するミッド(仲値)価格を参考に、ユーザー同士の注文をマッチングさせる仕組みです。一定時間内にマッチングが成立すれば、通常よりも有利なレートで取引が成立するため、コストを意識するトレーダーにとって非常に魅力的な機能です。(参照:DMM Bitcoin公式サイト)
■ 取引形式と取り扱い銘柄
DMM Bitcoinの取引形式は、現物取引とレバレッジ取引に対応しています。特筆すべきはレバレッジ取引の取り扱い銘柄数で、国内最多クラスを誇ります。ビットコインやイーサリアムといった主要銘柄はもちろん、他の取引所では現物取引しかできないようなアルトコインもレバレッジをかけて取引できるため、多彩な戦略を立てることが可能です。
ただし、現物取引ができる銘柄数はレバレッジ取引に比べて少ない点には注意が必要です。
■ その他の特徴
初心者でも直感的に操作できる使いやすいスマホアプリが好評で、PC版の取引ツールも高機能です。また、カスタマーサポートが充実しており、LINEでの問い合わせにも365日対応しているため、仮想通貨取引が初めての方でも安心して利用できます。セキュリティ面でも、DMMグループが培ってきたノウハウを活かし、コールドウォレットでの資産管理や二段階認証など、万全の対策を講じています。
■ まとめ:DMM Bitcoinはこんな人におすすめ
- アルトコインのレバレッジ取引をしたい人
- 「BitMatch注文」で取引コストを抑えたい人
- 手数料を気にせず、頻繁に日本円の入出金をしたい人
- LINEでの手厚いサポートを受けたい初心者
③ bitbank(ビットバンク)
bitbankは、国内最大級の取引量を誇る仮想通貨取引所であり、特に「取引所」形式での取引に強みを持っています。
■ スプレッドと手数料
bitbankの最大の特徴は、「取引所」の流動性が非常に高く、その結果としてスプレッドが安定して狭い傾向にあることです。多くの国内取引所では、アルトコインはスプレッドの広い「販売所」でしか扱っていないケースが多いですが、bitbankでは数多くのアルトコインを「取引所」で売買できます。これにより、ビットコインだけでなく、アルトコインの取引においてもコストを大幅に削減できます。
取引手数料は、Maker(指値注文)が-0.02%、Taker(成行注文)が0.12%と設定されています。Maker手数料がマイナスということは、指値注文が約定すると、逆に手数料を受け取れることを意味します。これは、板に流動性を提供してくれたことへのインセンティブであり、頻繁に取引を行うトレーダーにとっては大きなメリットです。(参照:bitbank公式サイト)
■ 取引形式と取り扱い銘柄
bitbankは「販売所」も提供していますが、メインはあくまで「取引所」です。取り扱い銘柄数は国内トップクラスで、そのほとんどを取引所形式で売買できます。この豊富な選択肢と狭いスプレッドが、多くのアクティブトレーダーを惹きつけています。
また、チャートツールとして世界中のトレーダーに利用されている「TradingView」を標準搭載しており、高度なテクニカル分析が可能です。
■ その他の特徴
セキュリティ対策にも力を入れており、第三者機関による評価でも高い評価を獲得しています。コールドウォレットやマルチシグ(複数人の承認を必要とする署名方式)といった技術を採用し、ユーザーの資産を安全に保護しています。
また、「貸して増やす(レンディング)」サービスも提供しており、保有している仮想通貨を貸し出すことで、最大年率5%の利用料を受け取ることが可能です。
■ まとめ:bitbankはこんな人におすすめ
- アルトコインを「取引所」形式で売買し、コストを抑えたい人
- 指値注文(Maker)を活用して、手数料を受け取りながら取引したい人
- 高度なチャート分析(TradingView)を行いたい中級者以上のトレーダー
- 取引量の多さによる安定した取引環境を求める人
④ SBI VCトレード
SBI VCトレードは、ネット証券大手のSBIグループが運営する仮想通貨取引所です。金融業界で培った信頼性と、各種手数料の安さ、スプレッドの狭さを両立させているのが特徴です。
■ スプレッドと手数料
SBI VCトレードは、スプレッドが業界最狭水準であることを強みとして打ち出しています。特に販売所のスプレッドは、他の多くの取引所と比較して狭めに設定されている傾向があり、初心者でもコストを意識しながら取引を始めやすい環境です。
さらに、取引手数料、日本円の入出金手数料、仮想通貨の入出庫手数料がすべて無料となっており、取引のたびに発生するコストを最小限に抑えられます。この手数料体系は、少額から始めたい初心者や、頻繁に資金を移動させるユーザーにとって非常に魅力的です。(参照:SBI VCトレード公式サイト)
■ 取引形式と取り扱い銘柄
簡単な操作で売買できる「販売所」と、ユーザー間で取引する「取引所」の両方を提供しています。取り扱い銘柄数も順次拡大しており、主要な仮想通貨は一通り取引可能です。
また、SBIグループの強みを活かし、外貨や株式など他の金融商品と同じような感覚で利用できるプラットフォームを目指しており、初心者にも親しみやすいインターフェースが特徴です。
■ その他の特徴
「ステーキング」や「レンディング」といった、仮想通貨を保有しているだけで収益を得られるサービスも充実しています。特にステーキングサービスは、特別な申し込み手続きが不要で、対象銘柄を保有しているだけで自動的に報酬が分配されるため、手間なく長期的な資産運用が可能です。
セキュリティ面では、SBIグループの高い基準に準拠した管理体制を敷いており、安心して取引に集中できます。
■ まとめ:SBI VCトレードはこんな人におすすめ
- 信頼性の高い大手金融グループの取引所を利用したい人
- スプレッドだけでなく、入出金手数料などを含めたトータルコストを重視する人
- ステーキングなど、手間のかからない長期運用に興味がある人
- シンプルな操作で取引を始めたい初心者
⑤ BITPOINT(ビットポイント)
BITPOINTは、東証プライム上場企業の株式会社リミックスポイントの子会社が運営する仮想通貨取引所です。新規銘柄への上場が早く、各種手数料が無料である点が大きな魅力です。
■ スプレッドと手数料
BITPOINTの最大の特徴は、取引手数料、日本円の即時入金手数料、入出金手数料(銀行振込手数料は自己負担)、仮想通貨の送金手数料がすべて無料であることです。これにより、取引コストは実質的にスプレッドのみとなり、非常に分かりやすい料金体系となっています。
スプレッドは他の取引所と比較して標準的ですが、頻繁に開催されるキャンペーンなどを利用することで、お得に取引を始めることができます。(参照:BITPOINT公式サイト)
■ 取引形式と取り扱い銘柄
取引形式は、シンプルな「販売所」と、より高度な取引が可能な「BITPOINT PRO(取引所)」を提供しています。BITPOINTの特筆すべき点は、他の国内取引所ではまだ扱っていないような、新しいアルトコインの取り扱いに積極的なことです。ジャスミー(JMY)やディープコイン(DEP)、シバイヌ(SHIB)といった注目銘柄をいち早く上場させてきた実績があり、新しいプロジェクトに早期から投資したいユーザーにとって魅力的な選択肢となります。
■ その他の特徴
「貸して増やす(レンディング)」や「ステーキング」サービスも提供しており、取引以外の収益機会も豊富です。特にステーキングは、対象銘柄を保有しているだけで報酬が得られるため、長期保有を考えているユーザーに適しています。
また、取引ツールはシンプルで分かりやすく、初心者でも直感的に操作できる設計になっています。
■ まとめ:BITPOINTはこんな人におすすめ
- 新しいアルトコインや珍しい銘柄に投資したい人
- 手数料を気にせず、シンプルに取引したい人
- キャンペーンなどを活用してお得に取引を始めたい人
- 長期保有とステーキングを組み合わせたい人
⑥ Coincheck(コインチェック)
Coincheckは、アプリダウンロード数国内No.1を誇る、非常に知名度の高い仮想通貨取引所です。圧倒的に使いやすいスマホアプリと、豊富な取り扱い銘柄数で、多くの初心者ユーザーから支持されています。
■ スプレッドと手数料
Coincheckのメインである「販売所」のスプレッドは、正直なところ他の取引所と比較して広めに設定されています。これは、初心者でも迷わず購入できるシンプルな操作性を提供するためのトレードオフと言えるでしょう。
一方で、ビットコイン(BTC)に限っては「取引所」形式での売買が可能です。取引所のスプレッドは販売所に比べて格段に狭いため、ビットコインを取引する際は必ず取引所を利用することで、コストを大幅に抑えられます。取引手数料は、Taker/Makerともに無料です(キャンペーン期間中などの条件あり)。(参照:Coincheck公式サイト)
■ 取引形式と取り扱い銘柄
「販売所」では国内最大級の銘柄数を取り扱っており、ビットコインからアルトコイン、NFT関連銘柄まで幅広く購入できます。この手軽さと銘柄の豊富さが、Coincheckが多くのユーザーに選ばれる理由です。
「Coincheckつみたて」や「Coincheck IEO」、「Coincheck NFT」といったユニークなサービスも展開しており、単なる売買だけでなく、多様な形で仮想通貨やNFTに関わることができます。
■ その他の特徴
何と言っても、その洗練されたUI/UXが最大の強みです。スマホアプリはチャート画面も見やすく、資産管理も一目でわかるため、仮想通貨取引が全く初めての人でも、迷うことなく操作を始められます。
過去の流出事件を教訓に、現在はマネックスグループの傘下で強固なセキュリティ体制を構築しており、安心して利用できます。
■ まとめ:Coincheckはこんな人におすすめ
- とにかく簡単な操作で仮想通貨を始めたい完全初心者
- ビットコインを「取引所」形式で低コストに取引したい人
- 色々な種類のアルトコインを少額から購入してみたい人
- NFTの取引やIEOにも興味がある人
⑦ bitFlyer(ビットフライヤー)
bitFlyerは、国内で最も歴史のある仮想通貨取引所の一つであり、長年にわたる運営実績と高い流動性、強固なセキュリティで知られています。
■ スプレッドと手数料
bitFlyerの「販売所」のスプレッドは、他の取引所と同様に広めです。しかし、bitFlyerの真価は、プロ向けの取引ツールである「bitFlyer Lightning」にあります。「bitFlyer Lightning」は現物取引、FX、先物取引に対応した取引所で、国内トップクラスのビットコイン取引量を背景とした高い流動性により、スプレッドが非常に狭く安定しています。
取引手数料は、銘柄や取引量によって変動しますが、直近30日の取引量に応じて割引が適用される仕組みがあります。(参照:bitFlyer公式サイト)
■ 取引形式と取り扱い銘柄
初心者向けの「販売所」、ビットコインの板取引ができる「取引所」、そしてプロ向けの「bitFlyer Lightning」と、ユーザーのレベルに応じた取引環境が用意されています。取り扱い銘柄も豊富で、特にビットコインの取引においては、その流動性の高さから多くのトレーダーに選ばれています。
■ その他の特徴
bitFlyerは、業界をリードする存在としてセキュリティ対策に最も力を入れている取引所の一つです。創業以来ハッキングによる資産流出を一度も起こしておらず、その安全性は高く評価されています。
また、Tポイントをビットコインに交換できるサービスや、クレジットカードの利用でビットコインが貯まる「bitFlyerクレカ」など、日常生活の中で気軽に仮想通貨に触れられるユニークなサービスも展開しています。
■ まとめ:bitFlyerはこんな人におすすめ
- ビットコインをメインに、安定した環境で取引したい人
- 「bitFlyer Lightning」を使って本格的なトレードを行いたい中上級者
- セキュリティの高さを最優先に考えたい人
- Tポイントやクレジットカードでビットコインを貯めたい人
【一覧表】おすすめ取引所のスプレッド・手数料比較
ここまで紹介した7社の特徴を一覧表にまとめました。スプレッドは常に変動するためあくまで参考値ですが、各社の手数料体系やサービス内容を比較検討する際にご活用ください。
| 仮想通貨取引所 | 主要銘柄の取引形式 | 取引手数料(取引所) | 日本円入金手数料 | 日本円出金手数料 | 仮想通貨送金手数料 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMOコイン | 販売所 / 取引所 | Maker: -0.01% Taker: 0.05% |
無料 | 無料 | 無料 | 総合的なコストが安い。レバレッジ取引に強み。 |
| DMM Bitcoin | 販売所 / レバレッジ取引 | 無料(BitMatch手数料は別途) | 無料 | 無料 | 無料(マイナーへの手数料は自己負担) | レバレッジ取引の銘柄が豊富。BitMatch注文が特徴。 |
| bitbank | 販売所 / 取引所 | Maker: -0.02% Taker: 0.12% |
無料 | 550円/770円 | 銘柄による | 取引所の流動性が高く、アルトコインのスプレッドが狭い。 |
| SBI VCトレード | 販売所 / 取引所 | Maker: -0.01% Taker: 0.05% |
無料 | 無料 | 無料 | 各種手数料が無料。大手金融グループの安心感。 |
| BITPOINT | 販売所 / 取引所 | 無料 | 無料 | 銀行振込手数料は自己負担 | 無料 | 新規銘柄の上場が早い。各種手数料が無料。 |
| Coincheck | 販売所 / 取引所(BTCのみ) | 無料 | 銀行振込は無料 | 407円 | 銘柄による | アプリが使いやすく初心者向け。販売所の銘柄が豊富。 |
| bitFlyer | 販売所 / 取引所 | 直近30日の取引量による | 銀行振込は無料 | 220円~770円 | 銘柄による | ビットコインの取引量が多く、流動性が高い。 |
※上記の情報は2024年5月時点のものです。最新の情報は必ず各取引所の公式サイトでご確認ください。
※スプレッドは市場の状況により常に変動します。
※参照:GMOコイン公式サイト、DMM Bitcoin公式サイト、bitbank公式サイト、SBI VCトレード公式サイト、BITPOINT公式サイト、Coincheck公式サイト、bitFlyer公式サイト
仮想通貨のスプレッドとは?

仮想通貨取引における「スプレッド」は、利益に直結する非常に重要な概念です。ここでは、スプレッドの基本的な意味と、なぜそれが取引コストになるのかを分かりやすく解説します。
売値と買値の価格差のこと
スプレッドとは、同一の仮想通貨における「購入価格(Ask/アスク)」と「売却価格(Bid/ビッド)」の差額のことです。
仮想通貨取引所のアプリやウェブサイトを見ると、同じ銘柄でも「購入価格」と「売却価格」の2つの価格が表示されていることに気づくでしょう。そして、購入価格は常に売却価格よりも高く設定されています。この価格差がスプレッドです。
- 購入価格(Ask): ユーザーが仮想通貨を買うときの価格
- 売却価格(Bid): ユーザーが仮想通貨を売るときの価格
例えば、ビットコインの価格表示が以下のようになっているとします。
- 購入価格(Ask):10,010,000円
- 売却価格(Bid):10,000,000円
この場合、スプレッドは「10,010,000円 – 10,000,000円 = 10,000円」となります。あなたがこの瞬間に1BTCを購入し、直後に売却すると、理論上はこの10,000円分の損失が発生することになります。
実質的な取引コストになる
スプレッドは、取引手数料のように「手数料」という名目で明示的に請求されるものではありません。しかし、その性質上、ユーザーが負担する「見えない手数料」や「実質的な取引コスト」として機能します。
仮想通貨を購入した瞬間、その資産の評価額は購入価格ではなく、その時点での売却価格で計算されます。上記の例で1BTCを10,010,000円で購入した場合、その瞬間に資産価値は売却価格である10,000,000円として表示されます。つまり、購入した瞬間にスプレッド分のマイナスからスタートするのです。
利益を出すためには、売却価格が自分の購入価格を上回るまで価格が上昇するのを待たなければなりません。
- 利益が出る条件: 将来の売却価格(Bid) > 自分が購入した時の購入価格(Ask)
この仕組みから、スプレッドは狭ければ狭いほど、利益を出しやすくなることがわかります。特に、1日に何度も売買を繰り返すデイトレードやスキャルピングといった短期的な取引スタイルでは、スプレッドの広さが収益性を大きく左右します。わずかな価格差に見えても、取引回数が増えれば増えるほど、その影響は雪だるま式に大きくなっていくのです。
したがって、仮想通貨取引所を選ぶ際には、取引手数料だけでなく、このスプレッドがどれくらい狭いかを比較検討することが極めて重要になります。
スプレッドと手数料の違い
仮想通貨取引で発生するコストには、主に「スプレッド」と「取引手数料」の2種類があります。この2つは混同されがちですが、その性質は大きく異なります。トータルコストを正確に把握するためにも、両者の違いをしっかり理解しておきましょう。
| 項目 | スプレッド | 取引手数料 |
|---|---|---|
| 性質 | 売値と買値の価格差。実質的なコスト(隠れコスト) | 取引ごとに発生する明示的な費用 |
| 発生タイミング | 仮想通貨の売買が成立した瞬間に常に発生 | 取引所形式での取引時や、一部の販売所で発生 |
| 表示方法 | 2つの価格(購入価格/売却価格)の差として間接的に表示 | 「手数料〇%」のように直接的に表示 |
| 変動要因 | 市場の流動性、価格変動、時間帯、銘柄などにより常に変動 | 取引所ごとに固定または段階的に設定されている |
| 主な発生場所 | 販売所で特に広く、取引所でも発生 | 取引所で発生することが多い |
■ スプレッド:見えないコスト
前述の通り、スプレッドは購入価格と売却価格の差額であり、取引所の利益やリスクヘッジのための費用が含まれています。これは「手数料」という名目では表示されず、価格差に織り込まれているため「隠れコスト」とも呼ばれます。
「手数料無料」を謳っている取引所でも、このスプレッドは必ず存在します。特に、操作が簡単な「販売所」形式では、このスプレッドが広く設定されていることが多く、実質的な収益源となっています。
■ 取引手数料:見えるコスト
一方、取引手数料は「取引金額の〇%」といった形で明確に提示されるコストです。主に、ユーザー同士が直接売買を行う「取引所」形式で発生します。
取引手数料は、取引所によって料率が異なり、「無料」のところもあれば、「Maker手数料(指値注文)」と「Taker手数料(成行注文)」で料率を変えているところもあります。例えば、bitbankのようにMaker手数料をマイナスに設定している取引所では、指値注文が約定すると手数料を逆に受け取ることができます。これは、市場に流動性を提供したことへの報酬(インセンティブ)と考えることができます。
■ トータルコストで考える重要性
重要なのは、スプレッドと取引手数料を合算した「トータルコスト」で判断することです。
例えば、以下のような2つの取引所があったとします。
- A社(販売所): 取引手数料無料、スプレッドが3%
- B社(取引所): 取引手数料0.1%、スプレッドが0.2%
一見すると、A社は「手数料無料」で魅力的に見えるかもしれません。しかし、実質的なコストであるスプレッドが3%と非常に広いため、トータルコストは高くなります。一方で、B社は0.1%の取引手数料がかかりますが、スプレッドが0.2%と狭いため、トータルコストは0.3%(0.1% + 0.2%)となり、A社よりもはるかに有利な条件で取引できます。
このように、表面的な「手数料無料」という言葉だけに惑わされず、スプレッドという実質的なコストを含めて、どちらが本当に有利なのかを見極めることが、賢い取引所選びの鍵となります。
「販売所」と「取引所」のスプレッドの違い
多くの仮想通貨取引所では、「販売所」と「取引所」という2つの取引形式が提供されています。この2つは、取引の相手方や仕組みが根本的に異なり、それがスプレッドの広さに大きく影響しています。
販売所:スプレッドは広いが操作が簡単
■ 販売所の仕組み
販売所は、ユーザーと仮想通貨取引所(業者)が直接、仮想通貨を売買する形式です。スーパーマーケットで商品を買うのと同じような感覚で、取引所が提示する価格で、欲しい量を確実に購入・売却できます。
■ スプレッドが広い理由
販売所の価格は、取引所が市場価格(取引所形式での価格など)を参考にしつつ、自社の利益や在庫リスク、価格変動リスクなどを上乗せ(スプレッドとして)して決定します。このスプレッドが、販売所を運営する業者の主な収益源となります。そのため、一般的に販売所のスプレッドは、次に説明する取引所形式よりも広く設定されています。
- メリット
- 操作が非常に簡単: 金額や数量を入力するだけで、誰でも直感的に売買できる。
- 確実に約定する: 提示された価格で、希望する数量をすぐに取引できる。
- デメリット
- スプレッドが広い(取引コストが高い): 実質的な手数料が高く、短期売買には不向き。
販売所は、その手軽さから仮想通貨取引が初めての初心者には非常に魅力的ですが、コスト面では不利になることを理解しておく必要があります。
取引所:スプレッドは狭いが操作が少し複雑
■ 取引所の仕組み
取引所は、仮想通貨を売買したいユーザー同士が直接取引を行うプラットフォームです。仮想通貨取引所は、その取引の「場」を提供しているに過ぎません。株式取引のように、「売りたい人」と「買いたい人」の注文が一致(マッチング)することで取引が成立します。
この取引の場には、「板(いた)」と呼ばれる注文一覧が表示されます。板には、各価格帯にどれくらいの売り注文(売り板)と買い注文(買い板)が出されているかがリアルタイムで表示されており、トレーダーはこの板情報を見ながら取引を行います。
■ スプレッドが狭い理由
取引所の価格は、ユーザー同士の需要と供給によって決まります。最も安い売り注文(Ask)と最も高い買い注文(Bid)の価格差が、そのままスプレッドとなります。業者の中間マージンが含まれないため、原理的に販売所よりもスプレッドは格段に狭くなります。
- メリット
- スプレッドが狭い(取引コストが低い): 販売所に比べて有利な価格で取引できる。
- 指値注文・成行注文が使える: 自分の希望する価格で注文を出したり(指値)、現在の市場価格で即座に売買したり(成行)できる。
- デメリット
- 操作がやや複雑: 板情報の見方や注文方法に慣れが必要。
- 必ずしも約定しない: 指値注文の場合、希望価格に達しなければ取引は成立しない。また、流動性が低いと、成行注文でも希望通りの数量を取引できないことがある。
コストを最優先に考えるのであれば、多少操作が複雑であっても「取引所」形式を利用するのが鉄則です。特に、頻繁に取引を行う予定がある方は、早い段階で取引所の使い方に慣れておくことを強くおすすめします。
スプレッドが広くなる3つのタイミング
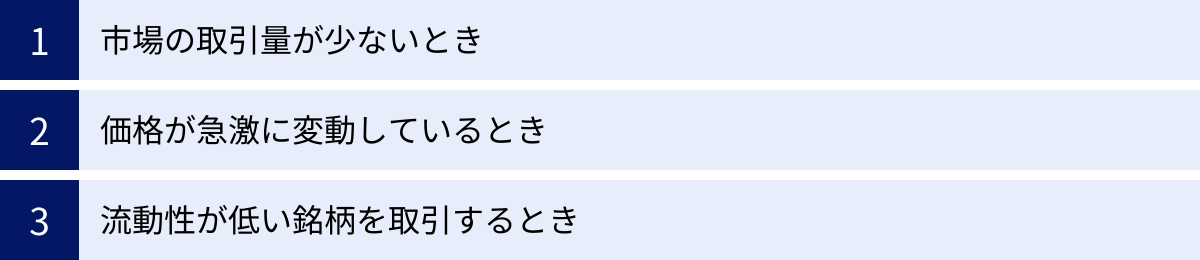
仮想通貨のスプレッドは常に一定ではなく、市場の状況によって大きく変動します。特に、スプレッドが急激に広がりやすい特定のタイミングを知っておくことは、意図しない高コストな取引を避けるために非常に重要です。
① 市場の取引量が少ないとき
スプレッドは、市場の流動性(取引の活発さ)に大きく左右されます。市場に参加しているトレーダーが少なく、取引量(出来高)が減少すると、板情報が「薄く」なります。板が薄いとは、売り注文と買い注文の数が少なく、それぞれの価格差が大きくなっている状態を指します。
このとき、最も安い売り注文と最も高い買い注文の価格差が必然的に開いてしまうため、スプレッドは広がります。
■ 具体的な時間帯
- 早朝や深夜: 日本時間の平日の日中と比べて、世界の主要な市場(ニューヨーク、ロンドンなど)が閉まっている時間帯は、全体の取引参加者が減少します。
- 土日・祝日: 機関投資家や多くの個人トレーダーが市場から離れるため、平日よりも取引量が少なくなる傾向があります。
- 年末年始などの大型連休: 市場参加者がさらに減少し、流動性が著しく低下することがあります。
このような時間帯に無理に取引を行うと、通常よりも広いスプレッドで約定してしまい、不利な取引になる可能性が高まります。
② 価格が急激に変動しているとき
市場に大きな影響を与えるニュースやイベントが発生し、価格が短時間で大きく上下する(ボラティリティが高まる)と、スプレッドは広がる傾向にあります。
■ 具体的な状況
- 重要な経済指標の発表時: 米国の雇用統計や消費者物価指数(CPI)、連邦公開市場委員会(FOMC)の政策金利発表など、世界経済の動向を示す指標が発表される前後。
- 業界に関する重大なニュース: 大手企業の仮想通貨決済導入、特定の国での規制強化・緩和、取引所のハッキング事件など。
- 著名人やインフルエンサーの発言: 特定の人物の発言によって、特定の銘柄の価格が急騰・急落するケース。
このような状況では、価格の先行きが不透明になり、リスクが高まります。仮想通貨交換業者は、この価格変動リスクをヘッジするために、意図的にスプレッドを広げて自己防衛を図ります。また、市場の混乱により、多くのトレーダーが注文を取り下げたり、様子見に回ったりするため、板が薄くなりスプレッドが広がるという側面もあります。
価格が大きく動いているときは一見すると利益を出すチャンスに見えますが、同時にスプレッドというコストも増大していることを忘れてはいけません。
③ 流動性が低い銘柄を取引するとき
スプレッドの広さは、取引する仮想通貨の銘柄によっても大きく異なります。一般的に、知名度が高く、時価総額が大きく、多くの取引所で扱われている銘柄ほど流動性が高く、スプレッドは狭くなる傾向があります。
■ 流動性が高い銘柄(スプレッドが狭い傾向)
- ビットコイン(BTC)
- イーサリアム(ETH)
これらの銘柄は世界中で取引されており、常に膨大な数の売り注文と買い注文が存在するため、スプレッドは比較的安定して狭く保たれます。
■ 流動性が低い銘柄(スプレッドが広い傾向)
- アルトコイン(草コイン): 時価総額が小さく、取引参加者が少ない、いわゆるマイナーなコイン。
- 上場したばかりの新しい銘柄: まだ市場での認知度が低く、取引が活発でない銘柄。
これらの流動性が低い銘柄は、もともとの取引参加者が少ないため、常に板が薄い状態にあります。少し大きな注文が入っただけで価格が大きく変動しやすく、売り注文と買い注文の価格差も開きがちです。そのため、ビットコインなどと比較して、スプレッドが数パーセント、場合によっては10%以上に達することも珍しくありません。
マイナーなアルトコインで大きなリターンを狙う戦略もありますが、その裏には高いスプレッドというコストが潜んでいることを十分に理解しておく必要があります。
仮想通貨取引のスプレッドを抑える4つのコツ
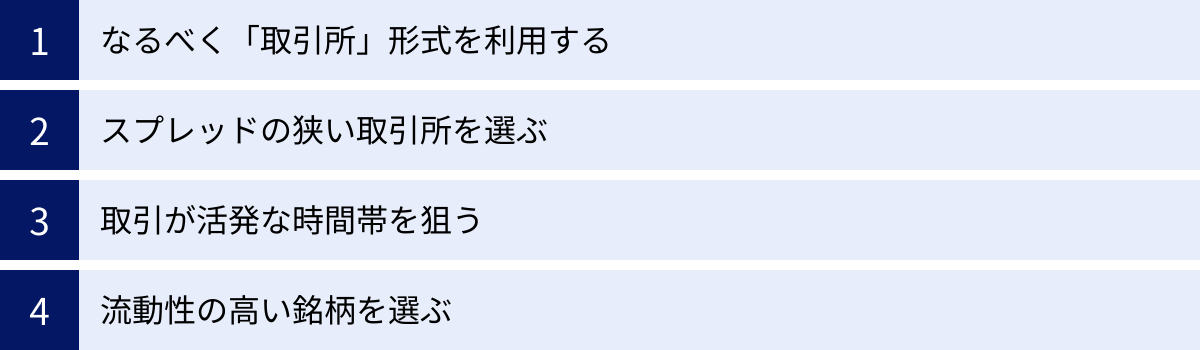
スプレッドは実質的な取引コストであり、これをいかに抑えるかが収益性を高める鍵となります。ここでは、スプレッドを意識して有利に取引を進めるための具体的な4つのコツを紹介します。
① なるべく「取引所」形式を利用する
これはスプレッドを抑える上で最も基本的かつ効果的な方法です。前述の通り、「販売所」は操作が簡単な代わりに、業者の利益が上乗せされているためスプレッドが広く設定されています。一方で、「取引所」はユーザー同士で直接売買するため、スプレッドが格段に狭くなります。
特に、ビットコインやイーサリアムといった主要な銘柄を取引する場合は、ほとんどの国内業者で「取引所」形式が提供されています。たとえ少額の取引であっても、毎回「取引所」を利用する習慣をつけるだけで、長期的には大きなコスト削減につながります。
アルトコインについては、業者によって「取引所」で扱っているかどうかが異なります。自分が取引したいアルトコインを「取引所」形式で、かつ狭いスプレッドで提供している業者(例えばbitbankなど)を選ぶことが重要です。最初は板取引の画面に戸惑うかもしれませんが、少し慣れればすぐに使いこなせるようになります。コスト削減のメリットは非常に大きいため、ぜひ挑戦してみましょう。
② スプレッドの狭い取引所を選ぶ
すべての取引所が同じスプレッドを提供しているわけではありません。業者ごとにスプレッドの広さには差があります。そのため、口座を開設する前に、複数の取引所を比較し、全体的にスプレッドが狭い傾向にある業者を選ぶことが重要です。
この記事の冒頭で紹介した「スプレッドが狭い仮想通貨取引所おすすめランキング7選」も参考に、各社の特徴を比較検討してみてください。
- レバレッジ取引がメインならGMOコインやDMM Bitcoin
- アルトコインの現物取引ならbitbank
- 各種手数料を含めたトータルコストを重視するならSBI VCトレード
上記のように、自分の取引スタイルに合った、スプレッド面で有利な業者を選ぶことが賢明です。一つの取引所に固執せず、複数の口座を開設しておき、取引する銘柄やタイミングによって最も有利な業者を使い分けるのも有効な戦略です。
③ 取引が活発な時間帯を狙う
スプレッドは市場の流動性に大きく影響されるため、取引が活発な時間帯を狙って取引することで、より狭いスプレッドで約定できる可能性が高まります。
一般的に、市場の取引量が多くなるのは、世界の主要な金融市場が開いている時間帯です。日本時間で言えば、以下の時間帯が狙い目となります。
- 東京時間(午前9時〜午後3時頃): アジア市場が活発になる時間帯。
- ロンドン時間(午後4時〜深夜2時頃): 欧州市場が活発になる時間帯。
- ニューヨーク時間(午後9時〜午前6時頃): 米国市場が活発になる時間帯。
特に、ロンドン市場とニューヨーク市場が重なる日本時間の午後9時〜深夜2時頃は、世界で最も取引が活発になるゴールデンタイムと言われています。この時間帯は流動性が非常に高まるため、スプレッドが最も狭くなる傾向があります。
逆に、市場参加者が少ない早朝や深夜、週末などは流動性が低下し、スプレッドが広がりやすいため、特別な理由がない限り取引を避けるのが賢明です。
④ 流動性の高い銘柄を選ぶ
スプレッドを抑えるという観点からは、取引する銘柄選びも重要です。前述の通り、流動性が低いマイナーなアルトコイン(草コイン)は、スプレッドが非常に広く設定されていることがほとんどです。
一攫千金を夢見て草コインに手を出すのも一つの投資戦略ですが、取引コストが非常に高いというリスクを伴います。もし、安定してコストを抑えた取引をしたいのであれば、まずは流動性が最も高いビットコイン(BTC)や、それに次ぐイーサリアム(ETH)といった主要銘柄から始めるのがおすすめです。
これらの銘柄は世界中で膨大な量が取引されており、常に厚い板が形成されているため、スプレッドが安定して狭い水準に保たれています。取引に慣れてきて、他のアルトコインにも興味が出てきたら、その銘柄の流動性やスプレッドを事前にしっかりと確認してから取引するようにしましょう。
スプレッドを比較するときの3つの注意点
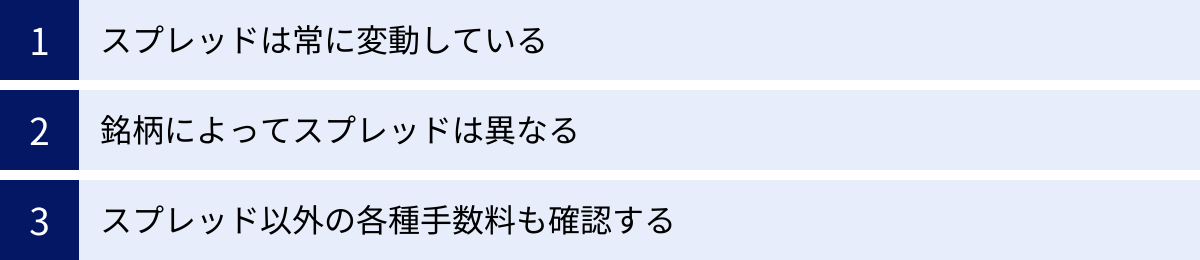
スプレッドの狭い取引所を選ぶことは重要ですが、単純に特定の瞬間のスプレッドだけを見て判断するのは危険です。ここでは、スプレッドを比較検討する際に押さえておくべき3つの注意点を解説します。
① スプレッドは常に変動している
最も重要な注意点は、スプレッドは固定された数値ではなく、常にリアルタイムで変動しているということです。市場の流動性や価格のボラティリティに応じて、秒単位でスプレッドは広がったり狭まったりします。
そのため、ある瞬間にA社のスプレッドがB社より狭かったとしても、数分後には逆転しているということも日常的に起こります。広告などで「業界最狭水準!」と謳われていても、それはあくまで特定の条件下での話である可能性があります。
■ 対策
- 特定の瞬間の数値だけで判断しない: 口座開設を検討している複数の取引所の取引画面を、異なる時間帯(例えば、平日の日中、夜間、早朝など)に何度かチェックし、平常時のスプレッドがどの程度の水準で推移しているのか、その傾向を把握することが重要です。
- 急変時の広がり方を比較する: 重要な経済指標の発表時など、価格が急変した際にどれくらいスプレッドが広がるのかも、取引所の安定性を見極める良い指標になります。急変時でも比較的スプレッドの広がりが穏やかな業者は、リスク管理能力が高いと言えるかもしれません。
② 銘柄によってスプレッドは異なる
ある取引所が、ビットコインのスプレッドは業界最狭水準であっても、他のアルトコインのスプレッドは他社より広い、というケースは珍しくありません。取引所によって、力を入れている銘柄や得意な銘柄が異なるためです。
例えば、ビットコインの取引だけをしたい人にとってはA社が最適でも、リップル(XRP)やソラナ(SOL)といった特定のアルトコインを取引したい人にとっては、B社の方が有利な場合があります。
■ 対策
- 自分が取引したい銘柄で比較する: 仮想通貨取引所を比較する際は、漠然と「スプレッドが狭いか」を見るのではなく、「自分が主に取引したいと考えている銘柄のスプレッドが狭いか」という視点でチェックすることが不可欠です。
- 複数の取引所を使い分ける: この銘柄はA社、あの銘柄はB社、というように、取引する銘柄に応じて最も有利なスプレッドを提供する取引所を使い分けるのも、コストを最小化するための高度なテクニックです。
③ スプレッド以外の各種手数料も確認する
スプレッドは実質的な取引コストですが、取引にかかる費用はそれだけではありません。スプレッドの狭さだけに目を奪われず、トータルコストで判断することが非常に重要です。
確認すべき主な手数料には、以下のようなものがあります。
- 取引手数料: 特に「取引所」形式で発生。無料のところもあれば、有料のところもある。
- 日本円の入金手数料: 即時入金や銀行振込など、入金方法によって異なる場合がある。
- 日本円の出金手数料: 利益を確定して自分の銀行口座に戻す際に発生。
- 仮想通貨の送金(出庫)手数料: 自分のウォレットや他の取引所に仮想通貨を送る際に発生。
例えば、スプレッドは非常に狭いものの、取引手数料が高かったり、日本円の出金手数料が高額だったりする取引所もあります。逆に、スプレッドはそこそこでも、これらの各種手数料がすべて無料であるため、結果的にトータルコストが安く済むというケースもあります。
■ 対策
- コストシミュレーションをしてみる: 自分の投資スタイル(取引頻度、入出金の回数など)を想定し、スプレッドと各種手数料を含めたトータルコストがどれくらいになるかをシミュレーションしてみることをおすすめします。目先の利益だけでなく、最終的に手元に残る金額を最大化するという視点で取引所を選びましょう。
仮想通貨のスプレッドに関するよくある質問
最後に、仮想通貨のスプレッドに関して初心者が抱きがちな疑問について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。
スプレッドの計算方法は?
スプレッドの絶対額(円やドル)だけでなく、その価格に対する割合(スプレッド率)を計算することで、異なる価格帯の銘柄同士のコストを比較しやすくなります。
スプレッド率の計算式は以下の通りです。
スプレッド率(%) = (購入価格 – 売却価格) ÷ 購入価格 × 100
例えば、ある仮想通貨の価格が以下のようになっているとします。
- 購入価格(Ask): 101円
- 売却価格(Bid): 100円
この場合のスプレッド額は 101円 - 100円 = 1円 です。
スプレッド率は、(101円 - 100円) ÷ 101円 × 100 ≒ 0.99% となります。
この計算式を使えば、価格が1,000万円のビットコインと100円のアルトコインのスプレッドのどちらが実質的に広い(コストが高い)のかを客観的に比較できます。
なぜ販売所のスプレッドは広いのですか?
販売所のスプレッドが取引所に比べて広く設定されているのには、主に2つの理由があります。
① 取引所の収益源であるため
販売所は、ユーザーと仮想通貨取引所(業者)が直接取引する形態です。業者は、ユーザーに安定して仮想通貨を供給するために、あらかじめ市場から仮想通貨を仕入れて在庫として保有しています。そして、仕入れ価格に自社の利益(手数料)を上乗せして販売価格を設定します。この業者の利益分がスプレッドの大部分を占めています。簡単な操作でいつでも確実に売買できるという利便性を提供する対価として、ユーザーは広いスプレッドを支払っている、と考えることができます。
② 価格変動リスクをヘッジするため
仮想通貨は価格変動が非常に激しい資産です。業者は在庫として大量の仮想通貨を保有しているため、価格が急落すると大きな損失を被るリスクを常に抱えています。この在庫リスクや急な価格変動に対する保険(リスクプレミアム)として、スプレッドを広めに設定しています。特に、価格のボラティリティが高まっているときや、流動性が低い銘柄ほど、このリスクヘッジのためのスプレッドは広くなる傾向にあります。
スプレッドがマイナスになることはありますか?
通常の取引環境において、ユーザーが目にするスプレッドがマイナスになることは基本的にありません。
スプレッドがマイナスになるということは、「売却価格(Bid) > 購入価格(Ask)」の状態を意味します。もしこのような状況が発生すれば、その瞬間に買ってすぐに売るだけで差額分の利益が確定します。これは「裁定取引(アービトラージ)」と呼ばれる機会であり、世界中のトレーダーやボット(自動売買プログラム)が常に市場を監視しているため、もし発生したとしても、瞬時に取引が行われて価格差は解消されてしまいます。
そのため、一般のユーザーが取引所の画面でマイナススプレッドを目にすることは、まずないと考えてよいでしょう。ごく稀に、システムのバグや取引所の流動性が極端に枯渇するような異常事態で瞬間的に発生する可能性はゼロではありませんが、それは極めて例外的なケースです。スプレッドは常にプラス(購入価格 > 売却価格)であり、取引におけるコストとして認識しておくのが正しい理解です。