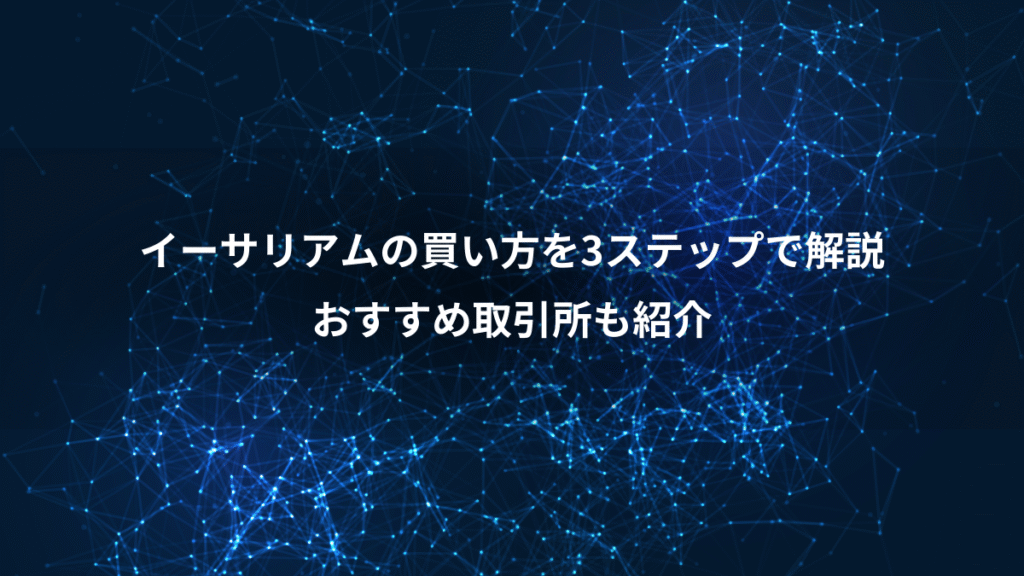近年、ビットコインと並び大きな注目を集めている仮想通貨(暗号資産)が「イーサリアム(Ethereum)」です。単なるデジタル通貨としてだけでなく、スマートコントラクトという革新的な技術を基盤に持ち、NFTやDeFi(分散型金融)といった新しいWeb3の世界を支える中心的な役割を担っています。
この記事では、これからイーサリアム投資を始めたいと考えている初心者の方に向けて、イーサリアムの基本的な知識から、具体的な買い方を3つのステップで分かりやすく解説します。さらに、安心して利用できるおすすめの国内仮想通貨取引所や、取引所選びのポイント、投資する上での注意点まで、網羅的にご紹介します。
この記事を最後まで読めば、イーサリアムの購入方法を完全に理解し、自信を持って仮想通貨投資の第一歩を踏み出せるようになるでしょう。
目次
イーサリアム(ETH)とは

イーサリアム(Ethereum)は、2015年にヴィタリック・ブテリン氏らによって開発・公開された、分散型アプリケーション(DApps)やスマートコントラクトを構築・実行するためのプラットフォームです。このプラットフォーム上で使用されるネイティブ通貨が「イーサ(Ether)」であり、一般的にティッカーシンボル「ETH」で表されます。しばしば「イーサリアム」という言葉が通貨そのものを指して使われることもありますが、厳密にはプラットフォームの名称です。
イーサリアムの最大の特徴は、「スマートコントラクト」という機能にあります。これは、あらかじめ設定されたルールや条件に従って、契約や取引を自動的に実行するプログラムのことです。この機能により、開発者は金融、ゲーム、アート、不動産など、さまざまな分野で中央管理者(銀行や企業など)を介さない新しいアプリケーション(DApps)を構築できます。
例えば、自動販売機はスマートコントラクトの簡単な例えとしてよく用いられます。「お金を入れる」という条件が満たされると、「ジュースを出す」という契約が自動的に実行されます。このプロセスに、店員のような第三者の介入は不要です。イーサリアムは、この仕組みをブロックチェーン上で、より複雑かつ安全に実現します。
このスマートコントラクト技術を応用して生まれたのが、近年大きな話題となっているNFT(非代替性トークン)やDeFi(分散型金融)です。NFTは、デジタルデータに唯一無二の価値を持たせる技術であり、その所有権の記録や移転にイーサリアムのスマートコントラクトが利用されています。また、DeFiは、銀行や証券会社といった仲介者なしに、貸し借り(レンディング)や交換(DEX)などの金融サービスを提供する仕組みで、これもイーサリアム上で数多く構築されています。
このように、イーサリアムは単に価値を保存したり送金したりするための通貨ではなく、新しいインターネットの形(Web3)を実現するための基盤となるプラットフォームとしての役割が期待されており、その将来性に多くの注目が集まっています。
ビットコインとの主な違い
イーサリアムはしばしば「ビットコインに次ぐ仮想通貨」と紹介されますが、その目的や技術的な特徴は大きく異なります。両者の違いを理解することは、イーサリアムの本質的な価値を把握する上で非常に重要です。
| 比較項目 | イーサリアム(ETH) | ビットコイン(BTC) |
|---|---|---|
| 主な目的 | スマートコントラクトの実行、DAppsのプラットフォーム | P2Pの電子決済システム、価値の保存手段(デジタルゴールド) |
| スマートコントラクト | あり(核心的な機能) | なし(限定的なスクリプト機能のみ) |
| 発行上限 | なし(ただし、バーンにより供給量が減少する仕組みがある) | 2,100万枚 |
| コンセンサスアルゴリズム | PoS (Proof of Stake) | PoW (Proof of Work) |
| ブロック生成時間 | 約12秒 | 約10分 |
| 開発者 | ヴィタリック・ブテリン氏ら | サトシ・ナカモト(正体不明の個人または団体) |
1. 目的とスマートコントラクトの有無
最大の違いは、その開発目的にあります。ビットコインが「P2P(Peer-to-Peer)の電子決済システム」、つまり中央銀行などを介さずに個人間で価値を直接やり取りすることを目指して作られたのに対し、イーサリアムは前述の通り「スマートコントラクトを実行するためのプラットフォーム」として設計されました。
この目的の違いから、イーサリアムにはスマートコントラクト機能が備わっていますが、ビットコインにはありません。これにより、イーサリアムは「プログラム可能なブロックチェーン」と呼ばれ、開発者が自由な発想で様々なアプリケーションを構築できる柔軟性を持っています。
2. 発行上限
ビットコインには2,100万枚という厳格な発行上限が定められており、その希少性から「デジタルゴールド」とも呼ばれます。一方、イーサリアムには現時点で発行上限が設定されていません。
しかし、2021年の大型アップデート「ロンドン」で、取引手数料の一部を焼却(バーン)する仕組み(EIP-1559)が導入されました。これにより、イーサリアムの利用が活発になるほど供給量が減少し、将来的にはインフレ率がマイナスになる(デフレ資産になる)可能性も指摘されています。
3. コンセンサスアルゴリズム
ブロックチェーンの取引を承認し、安全性を保つための仕組みをコンセンサスアルゴリズムと呼びます。ビットコインは「PoW(Proof of Work)」を採用しており、膨大な計算処理(マイニング)によって取引を検証します。この方式は非常に安全性が高い一方で、大量の電力を消費するという課題がありました。
対照的に、イーサリアムは2022年の大型アップデート「The Merge」によって、PoWから「PoS(Proof of Stake)」へと移行しました。PoSは、対象の仮想通貨を保有(ステーク)する量に応じて取引の承認権が与えられる仕組みです。これにより、イーサリアムは電力消費量を99.95%以上削減したとされ、環境負荷を大幅に低減しました。(参照:ethereum.org)
4. ブロック生成時間
ブロック生成時間とは、取引が記録された新しいブロックがチェーンに追加されるまでの時間です。ビットコインが約10分であるのに対し、イーサリアムは約12秒と非常に短く、より迅速な取引処理が可能です。この速さは、DAppsなどリアルタイム性が求められるアプリケーションを動かす上で大きな利点となります。
これらの違いから、ビットコインとイーサリアムは競合するものではなく、それぞれが異なる役割を持つ補完的な関係にあると考えることができます。
イーサリアムの買い方 簡単3ステップ
イーサリアムの購入は、一見難しそうに感じるかもしれませんが、実際には以下の3つのステップで誰でも簡単に行うことができます。ここでは、初心者がつまずきやすいポイントも押さえながら、具体的な手順を詳しく解説していきます。
- 仮想通貨取引所で口座を開設する
- 口座に日本円を入金する
- イーサリアムを購入する
この流れは、イーサリアムだけでなく、ビットコインなど他の仮想通貨を購入する際も基本的に同じです。一度覚えてしまえば、スムーズに取引を始められるでしょう。
① 仮想通貨取引所で口座を開設する
イーサリアムを購入するためには、まず仮想通貨(暗号資産)を取り扱っている「仮想通貨取引所」に自分の口座を開設する必要があります。取引所は、日本円と仮想通貨を交換してくれる場所と考えると分かりやすいでしょう。
日本国内で仮想通貨取引所を運営するには、金融庁・財務局への登録が義務付けられています。必ず登録済みの安全な取引所を選びましょう。
口座開設に必要なもの
口座開設の手続きは、ほとんどの取引所でオンライン完結し、スマートフォンがあれば簡単に行えます。事前に以下のものを準備しておくと、手続きがスムーズに進みます。
- メールアドレス: 登録や取引所からの重要なお知らせを受け取るために必要です。フリーメール(GmailやYahoo!メールなど)で問題ありません。
- スマートフォン: 本人確認の撮影や、二段階認証の設定に使用します。
- 本人確認書類: 以下のいずれか1点(または2点)が必要です。顔写真付きのものが推奨されます。
- 運転免許証
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- パスポート(2020年2月4日以降に申請されたものは住所記載がないため不可の場合あり)
- 在留カード(外国籍の方)
- 銀行口座: 日本円を入金したり、利益を出金したりするために、本人名義の銀行口座情報が必要です。
口座開設の具体的な流れ
取引所によって多少の違いはありますが、口座開設は概ね以下の流れで進みます。
ステップ1:公式サイトでメールアドレスを登録
利用したい取引所の公式サイトにアクセスし、「口座開設」ボタンからメールアドレスを登録します。登録したアドレスに確認メールが届くので、本文中のリンクをクリックして本登録に進みます。
ステップ2:基本情報の入力
画面の指示に従い、氏名、住所、生年月日、電話番号、職業、年収、投資経験などの基本情報を入力します。これらの情報は、犯罪収益移転防止法に基づいて確認が義務付けられているものです。正確に入力しましょう。
ステップ3:本人確認の実施
次に、本人確認書類を提出します。現在、主流となっているのが「スマホでかんたん本人確認(eKYC)」という方法です。スマートフォンのカメラを使い、本人確認書類の撮影と、自分の顔写真(セルフィー)の撮影を行うことで、オンライン上でスピーディーに本人確認が完了します。
この方法を利用すれば、郵送でのやり取りが不要になり、最短で即日中に口座開設が完了する場合もあります。
ステップ4:取引所による審査
提出された情報をもとに、取引所側で審査が行われます。審査基準は公開されていませんが、入力情報に誤りがないか、反社会勢力との関わりがないかなどが確認されます。通常、この審査は数時間から数営業日で完了します。
ステップ5:口座開設完了の通知
審査に通過すると、メールやアプリの通知で口座開設完了のお知らせが届きます。これで、取引所へのログインや日本円の入金が可能になります。
② 口座に日本円を入金する
口座が無事に開設されたら、次にイーサリアムを購入するための資金となる日本円を入金します。入金方法は取引所によっていくつか用意されていますが、主に以下の3つが代表的です。
主な入金方法の種類
| 入金方法 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |
|---|---|---|---|
| 銀行振込 | ほとんどの金融機関から入金可能 | 振込手数料は自己負担、金融機関の営業時間外は反映が翌営業日になることがある | 手数料を気にせず、自分の好きな銀行から振り込みたい人 |
| クイック入金(インターネットバンキング) | 原則24時間365日即時反映、手数料無料の取引所が多い | 提携しているネットバンクの口座が必要 | スピーディーに取引を始めたい人、手数料を抑えたい人 |
| コンビニ入金 | 24時間営業のコンビニから手軽に入金可能 | 手数料がかかる場合が多い、1回あたりの入金上限額が低いことがある | 近くにコンビニがあり、現金で手軽に入金したい人 |
・銀行振込
取引所が指定する銀行口座へ、自分の銀行口座から振り込む方法です。ATMやインターネットバンキングから手続きできますが、振込手数料は自己負担となります。また、銀行の営業時間外に振り込んだ場合、入金の反映が翌営業日になることがあるため、すぐに取引を始めたい場合には注意が必要です。
・クイック入金(インターネットバンキング入金)
多くの取引所が推奨しているのがこの方法です。取引所が提携しているインターネットバンキングを利用して入金する仕組みで、原則として24時間365日、ほぼリアルタイムで口座に資金が反映されます。さらに、入金手数料を無料としている取引所が多いため、コストを抑えたい方にも最適です。ただし、利用できるのは提携金融機関のインターネットバンキング契約をしている方に限られます。
・コンビニ入金
一部の取引所で対応している方法で、コンビニの端末を操作して発行した受付番号をレジに持っていき、現金で支払うことで入金できます。手軽さが魅力ですが、一般的に300円〜500円程度の入金手数料がかかります。
初心者の方には、手数料が無料で反映も早い「クイック入金」が最もおすすめです。利用したい取引所が、自分が使っている銀行のインターネットバンキングに対応しているか、事前に確認しておくと良いでしょう。
③ イーサリアムを購入する
日本円の入金が口座に反映されたら、いよいよ最終ステップ、イーサリアムの購入です。購入する際には、「取引所」と「販売所」という2つの形式があることを理解しておくことが非常に重要です。
取引所と販売所の違い
同じ取引所アプリ/サイト内にも、「取引所」と「販売所」という2つの購入場所が用意されていることがほとんどです。この2つは、取引の相手方と手数料の仕組みが大きく異なります。
| 形式 | 取引相手 | 手数料(コスト) | 価格 | 操作性 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 販売所 | 仮想通貨取引所 | スプレッド(広い) | 取引所が提示する価格 | 簡単 | 買値と売値の差額が実質的な手数料。初心者でも直感的。 |
| 取引所 | 他のユーザー | 取引手数料(狭い) | ユーザー同士の需給で決まる価格 | やや複雑 | 板情報を見ながら注文。コストを抑えて取引したい人向け。 |
・販売所形式
販売所は、ユーザーが仮想通貨取引所を相手にイーサリアムを売買する形式です。例えるなら、外貨両替所のようなイメージです。取引所が提示する購入価格と売却価格で取引するため、操作が非常にシンプルで、数量や金額を指定するだけで簡単に購入できるのが最大のメリットです。
ただし、購入価格と売却価格には「スプレッド」と呼ばれる価格差が設けられており、これが実質的な手数料となります。一般的にスプレッドは広めに設定されているため、取引所形式に比べて購入コストは割高になる傾向があります。
「とにかく簡単に、すぐにイーサリアムを買ってみたい」という初心者の方には、まず販売所での購入がおすすめです。
・取引所形式
取引所は、イーサリアムを買いたいユーザーと売りたいユーザーが直接マッチングして売買を行う形式です。株式取引のように、「板」と呼ばれる注文一覧を見ながら、いくらで何枚買いたいか(または売りたいか)を自分で決めて注文を出します。
メリットは、スプレッドがないため販売所に比べて取引コストを大幅に抑えられる点です。取引手数料は別途かかる場合がありますが、それを考慮しても販売所より有利な価格で取引できることがほとんどです。
デメリットは、板情報の見方や注文方法(指値注文、成行注文など)を理解する必要があるため、初心者には少し難しく感じられるかもしれません。また、希望する価格で売買相手が見つからないと、取引が成立しない可能性もあります。
「少しでも安くイーサリアムを購入したい」「本格的なトレードに挑戦したい」という方は、取引所形式の利用を目指しましょう。
イーサリアムの具体的な購入手順
ここでは、より簡単な「販売所」での購入手順を例に説明します。
- 取引所のアプリまたはサイトにログインし、「販売所」のページを開きます。
- 取扱通貨の一覧から「イーサリアム(ETH)」を選択します。
- 現在の購入価格と売却価格が表示されていることを確認し、「購入」ボタンをタップします。
- 購入したい分の「日本円の金額」または「ETHの数量」を入力します。(例:「10,000円分購入する」など)
- 入力内容と概算の購入数量、手数料などを確認し、問題がなければ「購入を確定する」ボタンをタップします。
以上で、イーサリアムの購入は完了です。購入したイーサリアムは、取引所の口座内の資産(ポートフォリオ)に反映されます。最初は無理のない少額から試してみて、操作に慣れていくのが良いでしょう。
イーサリアム購入におすすめの仮想通貨取引所5選
日本国内には金融庁に登録された仮想通貨取引所が多数ありますが、それぞれ手数料体系やアプリの使いやすさ、取扱通貨数などに特徴があります。ここでは、特に初心者の方でも安心して利用でき、イーサリアムの取引にも適した人気の取引所を5つ厳選してご紹介します。
※以下の情報は2024年時点の調査に基づきます。最新の情報は必ず各取引所の公式サイトでご確認ください。
① Coincheck(コインチェック)
Coincheckは、アプリのダウンロード数が国内No.1(※)を記録するなど、特に初心者からの支持が厚い仮想通貨取引所です。最大の魅力は、シンプルで直感的に操作できるスマートフォンアプリにあります。チャート画面も見やすく、仮想通貨の購入・売却が数タップで完結するため、初めての方でも迷うことなく取引を始められます。
イーサリアムはもちろん、ビットコインやリップルなど、取扱通貨の種類が豊富な点も特徴です。様々なアルトコインに分散投資をしたいと考えている方にも適しています。また、電気代やガス代の支払いでビットコインがもらえる「Coincheckでんき」「Coincheckガス」といったユニークなサービスも展開しています。
販売所のスプレッドはやや広めですが、それを補って余りある使いやすさから、「まずは手軽にイーサリアム投資を体験してみたい」という方に最初におすすめしたい取引所です。セキュリティ面では、過去の流出事件を教訓に、現在はマネックスグループ傘下で強固な管理体制を構築しています。
(※)対象:国内の暗号資産取引アプリ、期間:2019年〜2023年、データ協力:App Tweak
② DMM Bitcoin
DMM.comグループが運営するDMM Bitcoinは、各種手数料の安さに定評がある取引所です。日本円のクイック入金手数料や出金手数料、仮想通貨の送金手数料が無料となっており、コストを気にせず資金を移動できるのが大きなメリットです。
DMM Bitcoinの大きな特徴は、現物取引だけでなくレバレッジ取引の取扱通貨数が国内トップクラスである点です。少ない資金で大きな利益を狙えるレバレッジ取引に興味がある方にとっては、非常に魅力的な選択肢となります。
取引ツールも初心者向けのシンプルなモードと、上級者向けの多機能なモードを切り替えられるため、自分のレベルに合わせて利用できます。ただし、現物取引は販売所形式のみで、独自の「BitMatch注文」という仕組みを使わないとスプレッドが広めになる点には注意が必要です。コストを抑えつつ、いずれはレバレッジ取引にも挑戦してみたいという方におすすめです。
参照:DMM Bitcoin公式サイト
③ bitFlyer(ビットフライヤー)
bitFlyerは、国内最大級の取引量を誇る老舗の仮想通貨取引所です。ユーザー数が多く流動性が高いため、取引所形式での売買が成立しやすいというメリットがあります。セキュリティに関しても業界トップクラスの評価を受けており、長年にわたりハッキング被害ゼロを継続している実績は、大きな安心材料と言えるでしょう。
「bitFlyerかんたん積立」サービスを利用すれば、毎月一定額を自動で積み立て投資できるため、価格変動リスクを抑えながら長期的な資産形成を目指す方にも適しています。また、1円から仮想通貨を購入できるため、お試しで超少額から始めたいというニーズにも応えてくれます。
さらに、Tポイントをビットコインに交換できるなど、日常生活と連携したユニークなサービスも提供しています。信頼性と実績を最も重視する方や、少額からコツコツ積立投資をしたい方におすすめの取引所です。
参照:bitFlyer公式サイト
④ GMOコイン
GMOインターネットグループが運営するGMOコインは、総合力の高さでオリコン顧客満足度調査No.1(※)を何度も獲得している人気の取引所です。DMM Bitcoinと同様に、日本円の入出金手数料や仮想通貨の送金手数料が無料となっており、コスト面で非常に優れています。
GMOコインの強みは、「販売所」と「取引所」の両方でイーサリアムを取引できる点です。最初は簡単な販売所で、慣れてきたらコストの安い取引所で、といったようにステップアップが可能です。また、取扱通貨数も国内トップクラスで、現物取引だけでなくレバレッジ取引やステーキングサービスも充実しています。
アプリも使いやすく、取引に必要な機能がコンパクトにまとまっています。手数料の安さ、取引形式の豊富さ、サービスの充実度など、あらゆる面でバランスの取れた取引所を求めている方に最適な選択肢です。
(※)2024年 オリコン顧客満足度®調査 暗号資産取引所 現物取引 第1位
参照:GMOコイン公式サイト
⑤ bitbank(ビットバンク)
bitbankは、仮想通貨の取引量で国内No.1(※)の実績を持つ、トレーダーに人気の取引所です。最大の強みは、「取引所」形式の流動性が非常に高いことにあります。板が厚く、売買が活発なため、希望する価格でスピーディーに取引が成立しやすい環境が整っています。
特にイーサリアムをはじめとするアルトコインの取引に強く、多くの銘柄で板取引が可能です。販売所形式に頼らず、コストを抑えて本格的なトレードをしたい中〜上級者から絶大な支持を得ています。
アプリのチャート機能も充実しており、60種類以上のテクニカル分析ツールを利用できるため、詳細な相場分析が可能です。操作性はやや玄人向けですが、「最初から取引所形式でコストを意識した取引をしたい」という意欲的な初心者の方にもおすすめできる、実力派の取引所です。
(※)2021年4月28日 CoinMarketCap調べ
参照:bitbank公式サイト
初心者向け|仮想通貨取引所の選び方 4つのポイント
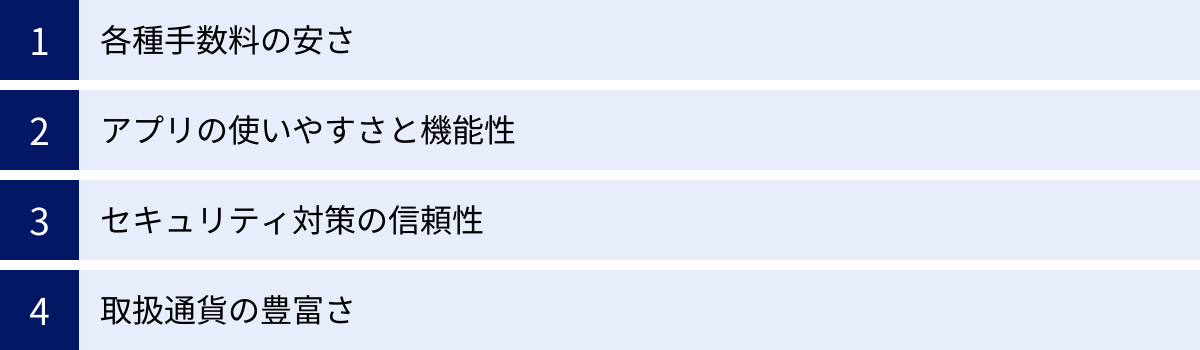
数ある取引所の中から自分に最適な一社を選ぶためには、いくつかの比較ポイントを知っておくことが大切です。ここでは、特に初心者が重視すべき4つのポイントを解説します。
① 各種手数料の安さ
仮想通貨取引では、様々な場面で手数料が発生します。これらのコストは、長期的に見ると利益を大きく左右する要因となるため、できるだけ安い取引所を選ぶのが基本です。
- 日本円の入出金手数料: 口座に日本円を入金したり、利益を出金したりする際にかかる手数料です。特にクイック入金が無料か、出金手数料が無料かは重要なチェックポイントです。GMOコインやDMM Bitcoinのように、両方無料の取引所は非常に魅力的です。
- 取引手数料: 「取引所」形式で売買する際にかかる手数料です。Maker(メイカー:板にない価格で注文を出す人)とTaker(テイカー:板にある価格で注文する人)で手数料率が異なる場合があります。中には、Maker手数料がマイナス(手数料がもらえる)の取引所もあります。
- スプレッド: 「販売所」形式で売買する際の、購入価格と売却価格の差額です。これは目に見えないコストであり、スプレッドが狭い(差が小さい)ほど、ユーザーにとって有利です。各社のアプリでリアルタイムの価格差を比較してみるのがおすすめです。
- 仮想通貨の送金手数料: 購入したイーサリアムを外部のウォレットや他の取引所に送金する際にかかる手数料です。将来的にDeFiやNFTを利用したいと考えている場合、送金手数料が無料の取引所(GMOコインなど)は大きなアドバンテージになります。
自分の投資スタイル(短期売買か長期保有か、販売所と取引所のどちらをメインで使うか)を考えながら、どの手数料を重視するかを決めると良いでしょう。
② アプリの使いやすさと機能性
仮想通貨の価格は24時間365日変動するため、スマートフォンアプリで手軽に取引や価格チェックができることは非常に重要です。
- UI(ユーザーインターフェース)の直感性: 初心者にとっては、専門知識がなくても直感的に操作できるシンプルなデザインが何よりも大切です。Coincheckのアプリは、この点で非常に高い評価を得ています。
- チャートの見やすさ: 価格の推移を示すチャートが見やすいか、拡大・縮小などの操作がスムーズに行えるかも確認しましょう。テクニカル分析に挑戦したい方は、描画ツールやインジケーターの種類が豊富なアプリ(bitbankなど)が適しています。
- 便利な機能の有無:
- 価格通知(アラート)機能: 設定した価格になると通知してくれる機能。売買のタイミングを逃さずに済みます。
- ウィジェット機能: スマホのホーム画面に気になる通貨の価格を常時表示できる機能。
- ニュース配信: 仮想通貨に関する最新ニュースをアプリ内で確認できると、情報収集が効率的になります。
多くの取引所では口座開設前にアプリをダウンロードして、実際の画面を確認できます。いくつか試してみて、自分にとって最も「しっくりくる」ものを選ぶのが良い方法です。
③ セキュリティ対策の信頼性
仮想通貨はデジタル資産であるため、ハッキングのリスクと常に隣り合わせです。大切な資産を守るためにも、取引所のセキュリティ対策は最も重視すべきポイントの一つです。
以下の項目を公式サイトで確認し、信頼できる取引所を選びましょう。
- 金融庁・財務局への登録: 日本国内で事業を行う上での大前提です。無登録業者は絶対に利用してはいけません。
- 顧客資産の分別管理: 会社自身の資産と、ユーザーから預かった資産を明確に分けて管理しているか。これは法律で義務付けられています。
- コールドウォレットでの資産保管: インターネットから完全に切り離された「コールドウォレット」で顧客資産の大部分を保管しているか。これにより、オンラインでのハッキングリスクを大幅に低減できます。
- 二段階認証の提供: ログイン時や送金時に、パスワードに加えてスマートフォンアプリ(Google Authenticatorなど)で生成されるワンタイムコードの入力を求める仕組みです。不正ログインを防ぐために、ユーザー側で必ず設定しましょう。
- マルチシグ: 仮想通貨を送金する際に、複数の秘密鍵を必要とする技術です。これにより、単独の担当者による不正や、一つの鍵の漏洩による資産流出を防ぎます。
bitFlyerのように、長年にわたってセキュリティインシデントを起こしていない実績のある取引所や、大手金融グループ(マネックス証券、GMO、DMMなど)の傘下にある取引所は、資本力やノウハウの面で安心感が高いと言えます。
④ 取扱通貨の豊富さ
最初はイーサリアムのみの購入を考えていても、慣れてくると他のアルトコインにも興味が出てくるかもしれません。その際に、取扱通貨が豊富な取引所であれば、新しく口座を開設する手間が省けます。
ただし、単に数が多いだけでなく、どのような種類の通貨を扱っているかも重要です。時価総額が大きく、将来性が見込まれる主要な通貨をバランス良く揃えている取引所が望ましいでしょう。
一方で、取扱通貨が多いということは、それだけリスクの高い草コイン(時価総額が非常に小さい無名な通貨)も含まれている可能性があります。初心者のうちは、ビットコインやイーサリアムといった主要な通貨から投資を始め、知識を深めながら徐々に投資対象を広げていくのが賢明です。
CoincheckやGMOコイン、DMM Bitcoinなどは取扱通貨数が国内トップクラスであり、多様なポートフォリオを組みたい方にとって魅力的な選択肢となります。
イーサリアムを購入する際の3つの注意点
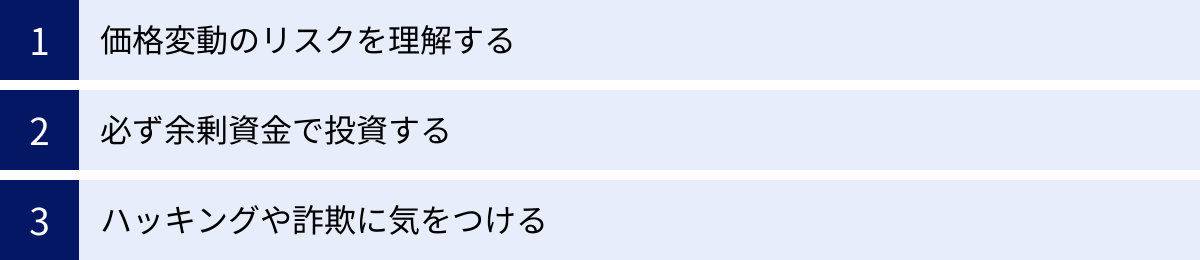
イーサリアム投資は大きな可能性を秘めている一方で、無視できないリスクも存在します。購入に踏み切る前に、以下の3つの注意点を必ず理解し、健全な投資を心がけましょう。
① 価格変動のリスクを理解する
イーサリアムを含む仮想通貨は、株式や為替(FX)といった従来の金融商品と比較して、価格変動(ボラティリティ)が非常に大きいという特徴があります。1日で価格が10%以上、時には数十%も上下することも珍しくありません。
価格が大きく変動する要因は様々です。
- 世界経済の動向: 金融緩和や引き締めなど、各国の金融政策。
- 規制関連のニュース: 特定の国での仮想通貨に対する規制強化や容認の動き。
- 技術的なアップデート: イーサリアム自体の大型アップデートの成功や延期。
- 著名人の発言: 影響力のある起業家や投資家の発言。
- 市場心理: 投資家全体の楽観的なムードや悲観的なムード。
大きな利益を得られる可能性がある反面、購入した時よりも価格が大きく下落し、元本割れ(投資した金額を下回る)するリスクも常に存在します。この価格変動リスクを十分に認識し、「価格が半分になっても冷静でいられるか」を自問自答した上で、投資判断を行うことが極めて重要です。価格が下落した際に狼狽して売却(狼狽売り)してしまうと、大きな損失を被る可能性があります。
② 必ず余剰資金で投資する
価格変動リスクと密接に関連するのが、この「余剰資金で投資する」という鉄則です。余剰資金とは、日常生活に必要なお金(生活費、教育費、緊急用の予備費など)を除いた上で、当面使う予定のないお金のことです。
絶対にやってはいけないのが、生活費を切り詰めたり、借金をしたりして仮想通貨に投資することです。もし価格が暴落した場合、生活が破綻してしまうだけでなく、精神的にも追い詰められ、冷静な判断ができなくなってしまいます。
仮想通貨投資は、「最悪の場合、そのお金がゼロになっても生活に支障が出ない範囲」で行うのが大原則です。幸い、多くの取引所では数百円〜数千円といった少額からイーサリアムを購入できます。まずは無理のない範囲で、失っても惜しくないと思える金額からスタートし、市場の雰囲気に慣れていくことを強く推奨します。
③ ハッキングや詐欺に気をつける
仮想通貨は、その注目度の高さから、常にサイバー犯罪者の標的となっています。リスクは、取引所自体がハッキングされることだけではありません。むしろ、ユーザー個人を狙ったフィッシング詐欺やハッキングのリスクの方が身近で、より注意が必要です。
- フィッシング詐欺: 取引所やウォレットサービスを装った偽のメールやSMSを送りつけ、偽サイトに誘導してログイン情報(ID、パスワード)や秘密鍵を盗み出す手口です。公式からの連絡に見えても、安易にリンクをクリックせず、必ずブックマークした公式サイトからアクセスする癖をつけましょう。
- SNSでの詐欺: Twitter(X)やDiscordなどで、「必ず儲かる」「エアドロップ(無料配布)で高額なトークンがもらえる」といった甘い言葉で誘い、詐欺サイトに接続させたり、ウォレットの秘密鍵を聞き出そうとしたりする手口です。うまい話には必ず裏があると考え、知らない人からのDMや怪しいプロジェクトには関わらないようにしましょう。
- 個人のPCやスマホのウイルス感染: 不審なフリーWi-Fiへの接続や、怪しいファイルのダウンロードによってデバイスがウイルスに感染し、パスワードなどの情報が抜き取られるケースもあります。
これらのリスクから資産を守るために、以下の対策は必須です。
- パスワードは複雑で使い回さない
- 二段階認証は必ず設定する
- ソフトウェアは常に最新の状態に保つ
- 秘密鍵やリカバリーフレーズは誰にも教えず、オフラインで厳重に保管する
自己防衛の意識を常に高く持つことが、仮想通貨の世界で生き残るための鍵となります。
購入したイーサリアムの管理方法
イーサリアムを購入した後、その資産をどのように保管・管理するかも重要なポイントです。管理方法には大きく分けて2つの選択肢があり、それぞれにメリットとデメリットが存在します。自分の投資スタイルや保有量に合わせて、最適な方法を選びましょう。
取引所に預けたままにする
最も手軽な方法が、購入した仮想通貨取引所の口座にイーサリアムを預けたままにしておく管理方法です。
- メリット:
- 手軽さ: 特別な手続きは不要で、購入後そのまま保管できます。
- 取引のしやすさ: 価格が変動した際に、いつでもすぐに売却したり、他の通貨に交換したりできます。
- 秘密鍵の管理が不要: 資産へのアクセスに必要な秘密鍵は取引所が管理してくれるため、自分で管理する手間や紛失リスクがありません。
- デメリット:
- カウンターパーティリスク: 取引所がハッキング被害に遭ったり、万が一倒産したりした場合、預けていた資産が失われるリスクがゼロではありません。(ただし、日本の登録業者は顧客資産の分別管理が義務付けられており、信託保全などの補償制度を設けている場合もあります)
- 取引所のシステムメンテナンス: 取引所がメンテナンス中の場合、一時的に資産の移動や売買ができなくなることがあります。
この方法は、頻繁に取引を行うトレーダーや、保有量が比較的少ない初心者の方に適しています。ただし、ログインパスワードや二段階認証の設定など、自分自身で行うべきセキュリティ対策は万全にしておく必要があります。
自分でウォレットを用意して管理する
よりセキュリティを重視する場合や、DeFi、NFTゲームといったDAppsを利用したい場合には、自分で「ウォレット」を用意して管理する方法が推奨されます。ウォレットとは、仮想通貨を保管・管理するためのデジタル上の財布のことです。
ウォレットには、インターネットに接続されているか否かで「ホットウォレット」と「コールドウォレット」の2種類があります。
| ウォレットの種類 | 接続状況 | 主な形態 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |
|---|---|---|---|---|---|
| ホットウォレット | オンライン | PCソフト、スマホアプリ、ウェブブラウザ拡張機能(例:MetaMask) | 利便性が高い、DAppsとの連携が容易、送金が手軽 | ハッキングのリスクが常にある | 少額の保管、DeFiやNFTを頻繁に利用する人 |
| コールドウォレット | オフライン | USBメモリのような専用端末(例:Ledger、Trezor) | セキュリティが非常に高い | 利便性が低い、高価(1万〜3万円程度)、操作がやや複雑 | 多額の資産を長期保有(ガチホ)したい人 |
・ホットウォレット
代表的なものに、ブラウザ拡張機能やスマホアプリとして利用できる「MetaMask(メタマスク)」があります。常にオンライン状態にあるため、送金やDAppsへの接続がスムーズに行える利便性の高さが魅力です。しかし、オンラインである以上、ウイルス感染やハッキングによって資産が盗まれるリスクは常に伴います。日常的に使う少額のイーサリアムを入れておくのに適しています。
・コールドウォレット(ハードウェアウォレット)
Ledger社やTrezor社が販売しているような、USBデバイス型のウォレットです。取引の承認時のみPCに接続し、それ以外はインターネットから完全に切り離して保管するため、ハッキングのリスクを極限まで低減できます。多額のイーサリアムを長期的に安全に保管したい場合には、最も推奨される方法です。
ウォレットで自己管理する際の最重要事項は、「秘密鍵」と「リカバリーフレーズ(シードフレーズ)」の管理です。これらは、ウォレットにアクセスするための唯一の鍵であり、これを紛失したり盗まれたりすると、二度と資産を取り戻すことはできません。絶対にデジタルデータで保存せず、紙に書き写して誰にも見られない安全な場所に複数保管するなど、厳重な管理が求められます。
イーサリアムの今後の見通しと将来性
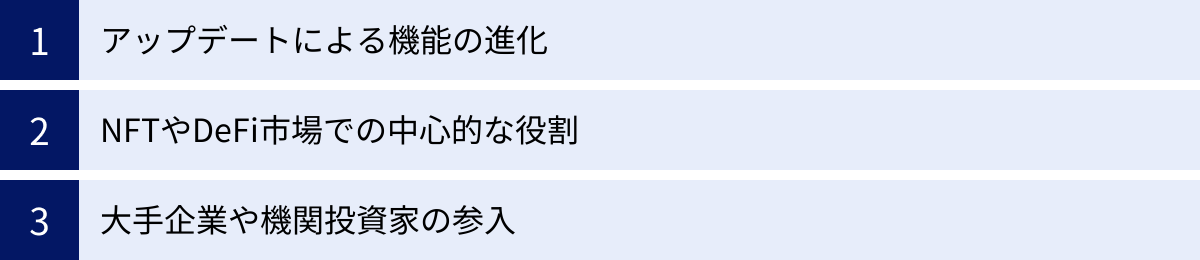
イーサリアムへの投資を検討する上で、その将来性は最も気になる点の一つでしょう。ここでは、イーサリアムの価格や価値にポジティブな影響を与えうる3つの主要な要因について解説します。
アップデートによる機能の進化
イーサリアムは、現在も活発に開発が続けられているプロジェクトです。継続的なアップデートによって、スケーラビリティ(処理能力)、セキュリティ、持続可能性といった課題を解決し、プラットフォームとしての性能向上を目指しています。
特に画期的だったのが、2022年9月に実施された「The Merge(マージ)」です。これにより、前述の通りコンセンサスアルゴリズムがPoWからPoSへ移行しました。この変更は、イーサリアムのエネルギー消費量を99.95%以上も削減するという劇的な効果をもたらし、環境負荷に対する懸念を払拭しました。また、PoSへの移行により、イーサリアムを保有してネットワークの維持に貢献することで報酬を得られる「ステーキング」が可能になり、新たな需要を生み出しています。(参照:ethereum.org)
今後も、「シャーディング」と呼ばれる技術の導入が計画されています。これは、データベースを複数の小さな部分(シャード)に分割して並行処理することで、取引の処理能力を飛躍的に向上させ、ガス代(取引手数料)の高騰問題を解決することを目的としています。
こうした一連のアップデートが成功裏に進むことで、イーサ-リアムネットワークはより多くのユーザーやアプリケーションを処理できるようになり、プラットフォームとしての価値がさらに高まることが期待されます。
NFTやDeFi市場での中心的な役割
イーサリアムの価値を支える最も強力な基盤の一つが、NFT(非代替性トークン)とDeFi(分散型金融)のエコシステムです。
NFTの標準規格である「ERC-721」や「ERC-1155」はイーサリアム上で誕生し、現在、世界最大のNFTマーケットプレイスであるOpenSeaをはじめ、多くのプラットフォームがイーサリアムを基盤としています。デジタルアート、コレクティブル、ゲーム内アイテム、会員権など、NFTのユースケースが拡大すればするほど、その取引や発行のためにイーサリアムが必要となり、需要が増加します。
また、DeFiの世界においても、イーサリアムは圧倒的な存在感を放っています。Uniswapのような分散型取引所(DEX)、AaveやCompoundのようなレンディングプロトコル、MakerDAOのようなステーブルコイン発行プラットフォームなど、数多くの主要なDeFiアプリケーションがイーサリアム上で稼働しています。DeFi市場全体の規模が拡大するにつれて、その中心にあるイーサリアムの重要性も増していくと考えられます。
イーサリアムは、これらの革新的な分野における「デファクトスタンダード(事実上の標準)」としての地位を確立しており、この先行者利益と強固なネットワーク効果が、今後の成長を牽引する大きな要因となるでしょう。
大手企業や機関投資家の参入
かつて仮想通貨は、一部の技術者や個人投資家が中心のニッチな市場でした。しかし近年、その状況は大きく変化しています。世界的な大手企業や、年金基金・ヘッジファンドといった機関投資家が、イーサリアムの技術的価値と資産価値を認識し、市場に参入し始めています。
MicrosoftやAmazon (AWS) といった巨大IT企業は、企業がイーサリアムのブロックチェーンを容易に利用できるようなサービスを提供しています。また、多くの金融機関がイーサリアムに関連するカストディサービス(資産管理サービス)や金融商品の開発を進めています。
特に注目されているのが、イーサリアムの現物ETF(上場投資信託)の動向です。米国などで現物ETFが承認されれば、個人投資家が証券口座を通じて手軽にイーサリアムに投資できるようになり、市場に莫大な資金が流入する可能性があります。
このように、社会的な信用度の高い大手企業や機関投資家の参入は、市場の流動性と信頼性を高め、イーサリアムがより成熟した資産クラスとして認められていく上で、非常にポジティブな材料と言えます。
イーサリアムの買い方に関するよくある質問
最後に、イーサリアムの購入に関して初心者が抱きがちな質問とその回答をまとめました。
イーサリアムは最低いくらから購入できますか?
取引所によって異なりますが、多くの国内取引所では数百円程度の非常に少額からイーサリアムを購入できます。
例えば、bitFlyerでは「1円」から、Coincheckでは「500円」から購入が可能です。GMOコインやDMM Bitcoinでは、金額指定ではなく数量での指定(例:0.0001 ETHから)となりますが、こちらも日本円に換算すると非常に少額です。
そのため、「まずは少しだけ試してみたい」という方でも、気軽に投資を始めることができます。いきなり大きな金額を投じるのではなく、まずはご自身が安心できる少額からスタートし、取引のプロセスに慣れることをおすすめします。
購入時にかかる手数料には何がありますか?
イーサリアムを購入する際には、主に以下の手数料がかかる可能性があります。
- 日本円の入金手数料: 銀行振込の場合は振込手数料が自己負担となることが多いです。クイック入金を利用すれば無料になる取引所が多数あります。
- 取引コスト:
- 販売所の場合: スプレッド(購入価格と売却価格の差額)が実質的な手数料となります。
- 取引所の場合: 取引手数料(約定金額の0.01%〜0.15%程度、または無料)がかかります。
- 仮想通貨の出金(送金)手数料: 購入したイーサリアムを外部ウォレットなどに送金する際にかかる手数料です。これは無料の取引所と有料の取引所があります。
最もコストを抑える方法は、「クイック入金が無料の取引所を使い、取引所形式でイーサリアムを購入する」ことです。ただし、初心者のうちは操作の簡単さを優先して販売所を利用するのも一つの選択肢です。
スマホアプリでも簡単に買えますか?
はい、主要な国内仮想通貨取引所はすべて、高機能で使いやすいスマートフォンアプリを提供しており、スマホだけで簡単にイーサリアムを購入できます。
口座開設の手続き(本人確認含む)から、日本円の入金、イーサリアムの購入・売却、資産管理まで、すべての操作がスマートフォン一台で完結します。
アプリを使えば、通勤中や休憩時間など、いつでもどこでも価格をチェックしたり、取引したりできるため非常に便利です。UIも直感的に作られていることが多く、特にCoincheckなどのアプリは初心者でも迷わず操作できるように設計されています。
イーサリアム投資で得た利益に税金はかかりますか?
はい、イーサリアムを含む仮想通貨取引で得た利益は、原則として課税対象となります。
日本の税法上、仮想通貨の売買によって生じた利益は「雑所得」に分類されます。雑所得は、給与所得などの他の所得と合算して総所得金額を計算する「総合課税」の対象となります。
所得税は、総所得金額が大きくなるほど税率が高くなる「累進課税」が採用されており、住民税(一律10%)と合わせると、最大で55%の税率が適用される可能性があります。
会社員などの給与所得者の場合、仮想通貨による利益(所得)が年間で20万円を超えると、原則として確定申告が必要になります。利益の計算は「総平均法」または「移動平均法」で行う必要があり、少々複雑です。
税金の計算や申告を怠ると、追徴課税などのペナルティが課される可能性があります。利益が出た場合は、必ず国税庁の公式サイトで最新情報を確認するか、税理士などの専門家に相談するようにしましょう。
参照:国税庁「暗号資産に関する税務上の取扱いについて」